
【引用:ミリタリーウィキ】衛星とドローンが空を覆う現代に、時代遅れと思われていた「軍用風船」が再び注目を集めている。米国を中心に各国軍が、かつて監視や通信、偵察に用いた熱気球や係留型プラットフォームを低コストで高効率な戦場資産として再導入し始めた。背景には、中国が相次いで偵察風船を飛ばしたことによる警戒感の高まりがある。

【引用:ミリタリーウィキ】今年4月、米陸軍は防衛関連企業10社と、低高度で滞空して監視・通信を行う「エアロスタット(aerostat)風船」の改良契約を締結した。契約規模は42億ドル(約6,340億円)とされ、昨年の太平洋での大規模演習では、電磁スペクトルセンサーを積んだ熱気球を高高度まで上げて新型誘導兵器の標的誘導に利用する場面が確認された。もはや風船は単なる観測装置ではなく、戦闘ネットワークの一環として機能し始めている。

【引用:ミリタリーウィキ】この動きは米国に限らない。ポーランドはロシアからのミサイルや航空機を検知する早期警戒網整備の一環として米製エアロスタットを導入し、イスラエルは国境地帯にロケット探知用の風船を配備している。ウクライナでも長距離ドローンの通信中継として風船を活用するなど、「風船戦術」が多方面で実用化されつつある。

【引用:ミリタリーウィキ】エアロスタットは通常3〜5km上空に係留して低空のドローンやミサイルを継続的に探知でき、数週間にわたる任務遂行が可能だ。高高度の自由飛行型風船は成層圏(24〜37km)付近で通信傍受や高解像撮影を行い、AIと組み合わせれば風向を解析して長期間特定地域上空に留まらせる運用も可能になる。コスト面と持続性で航空機や衛星を補完する存在として期待が高まっている。

【引用:X】とはいえ脆弱性も無視できない。成層圏の強風に流されやすく精密な制御が難しいこと、小型太陽電池に頼るため電力供給が途絶える危険があること、外交問題や事故の誘発といったリスクを抱えている。2015年には係留索が切れた軍用エアロスタットが遠方まで飛散して住民を驚かせる事故も発生しており、各国は利点と危険を秤にかけて慎重に運用を進めている。






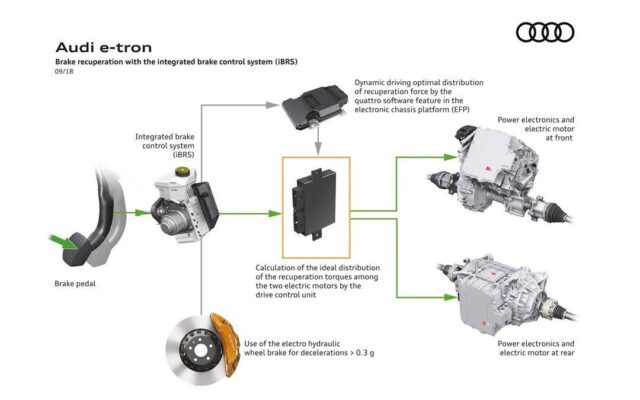



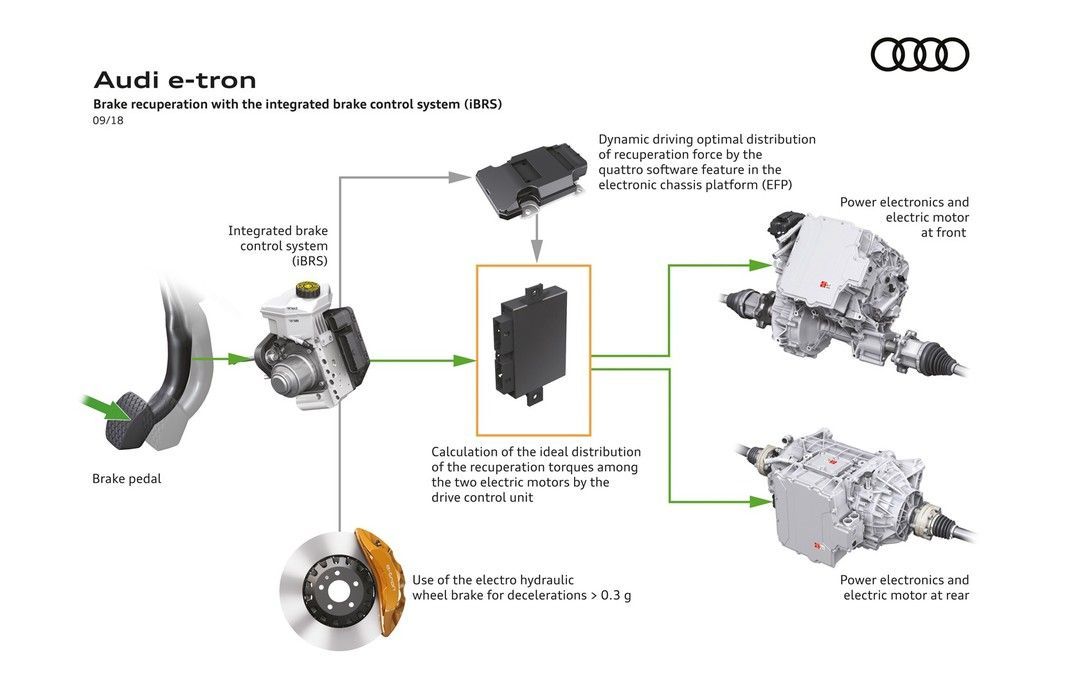









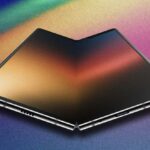
コメント0