
「癲癇」は世界人口の約1%が患っている神経系疾患である。適切な治療と管理が行われれば日常生活に大きな支障をきたすことはない。近年、薬物治療の進歩と社会の認識変化により、てんかんへの理解が徐々に広がりつつある。
てんかんは、脳の電気信号が突然過剰に放出されることによって引き起こされる神経学的疾患である。患者は、意識喪失、けいれん、感覚や感情の一時的な異常など、さまざまな症状を経験する。症状は個人差が大きく、数秒間のぼんやりとした状態から全身けいれんを伴う大発作まで多岐にわたる。
てんかんは大きく、原因不明の特発性てんかんと、脳損傷や基礎疾患など明確な原因がある症候性てんかんに分類される。新生児期や幼児期では、分娩中の酸素不足、熱性けいれん、脳損傷などが原因となりうる。思春期では遺伝的要因が、成人以降では脳卒中、外傷性脳損傷、脳腫瘍などが主な原因となる。しかし、全患者の約60%は正確な原因の特定が困難である。
てんかんは一般的な遺伝性疾患とは異なる。家族歴が影響する場合もあるが、家族歴がなくても発症することが多い。「てんかんは遺伝する」という偏見は誤った認識であり、患者の社会活動、結婚、就職に不必要な差別をもたらす可能性がある。
てんかんの代表的な症状は「発作」である。発作は一度きりの場合もあれば、繰り返し起こることもあり、タイプによって異なる。大発作では突然意識を失い全身がけいれんし、小発作では短時間のぼんやりや口をもぐもぐさせるなどの軽い症状が現れる。
てんかんの診断には、病歴聴取と脳波検査(EEG)が不可欠である。脳波検査で異常な脳電気活動を確認し、必要に応じてMRIやCTなどの画像検査で脳構造の異常の有無も調べる。特に初回発作の場合、てんかん以外の疾患(一過性脳虚血発作、失神、睡眠障害など)との鑑別が極めて重要となる。
てんかんは、適切な治療を受ければ発作をコントロールしながら日常生活を送ることが可能である。薬物治療で発作が抑えられない場合には、外科的治療(てんかん病巣切除術)、迷走神経刺激療法(VNS)、ケトン食療法などが検討される。また、一定期間発作がなく、脳波検査で異常が認められなければ、医師の判断により薬剤の減量または中止が行われることもある。重要なのは、治療中に自己判断で薬を中止しないことであり、無断で中止すると発作の再発リスクが非常に高まる。
てんかん患者も、適切な治療と自己管理を行えば、仕事、学業、運動などほとんどの活動を通常通り行うことができる。ただし、発作を誘発する要因(睡眠不足、ストレス、過度の飲酒、不規則な服薬など)には十分に注意し、定期的な検診と薬の服用を欠かさないことが重要である。
特に2年以上発作がなく、医師から運転可能と判断された場合は、自動車運転免許の取得も可能である。ただし、発作が再発した場合は運転が禁止される。兵役については一定の基準に基づき免除されることもあるが、公務員や企業への就職時にてんかんの病歴だけで差別を受けることは法的に認められていない。近年では、てんかんに対する社会の認識が改善され、「管理可能な慢性疾患」として受け入れられる風潮が広がりつつある。
周囲の人が突然発作を起こした場合、慌てず冷静に対処することが必要である。まず、患者を安全な場所に移動させ、頭部を保護する。無理に動かしたり口を開けさせたりせず、発作が収まるまで見守る。通常、発作は数分以内に自然と収まる。5分以上発作が続く場合や、初めての発作、呼吸困難を伴う場合には直ちに救急車を呼ぶべきである。
てんかんは誰にでも発症しうる疾患である。重要なのは、早期診断と継続的な治療、そして周囲の理解と支援である。病気そのものよりも「病気に対する偏見」が患者をより深く傷つける可能性があることを忘れてはならない。てんかんは隠すべき病気ではなく、適切に管理し克服可能な「日常の中の疾患」である。










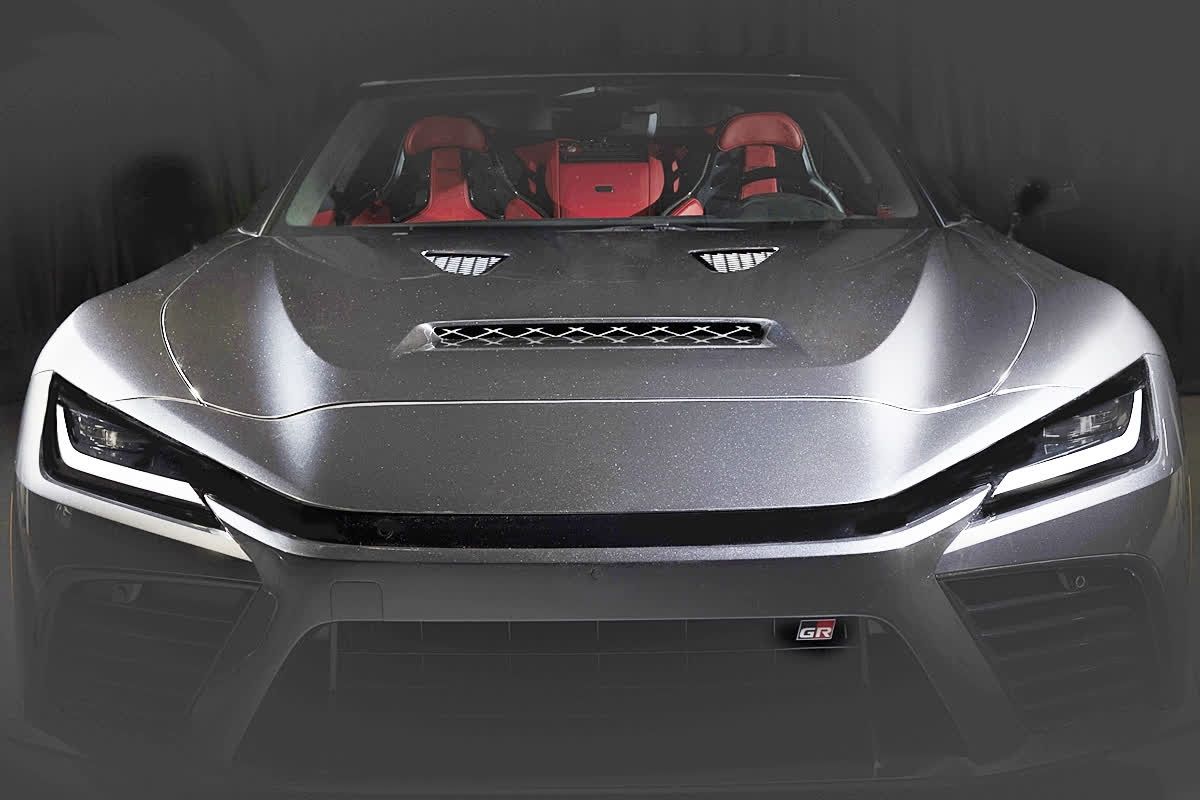











コメント0