組織の時間を浪費するリーダー、なぜ問題なのか?

業務指示を適切に行えないリーダーは、組織にどのような影響を及ぼすのか?
リーダーとしての役割が高まるにつれ、「業務指示」の重要性は増大する。しかし、自身が求める成果を明確に伝えられないリーダーが意外に多い。「明日までにマーケティングトレンドを調査して」といった曖昧な指示は、従業員の時間を無駄にする典型的なケースだ。新入社員時代は、リーダーを単なる業務指示者と捉えがちだ。しかし、組織運営側の立場に立つと、単なる業務遂行より「何をすべきかを決定すること」がはるかに重要だと気づく。
業務指示が難しい理由は、単に「誰が、いつまでに、何をするか」を決めるのがすべてではないからだ。期待する成果物のレベル、活用目的、優先順位まで考慮する必要がある。さらに、従業員が業務遂行の過程で自律的に判断できるよう、背景や文脈も説明すべきだ。この過程を省略すると、従業員は混乱し、試行錯誤を繰り返して時間を浪費する。結果、組織全体の生産性低下という悪循環に陥る。
「優れたリーダー」はどのように組織の時間を節約するか
リーダーが業務の枠組みを明確に設定すれば、従業員は無駄な時間を費やさずに業務を遂行できる。例えば、具体的な指針なしで進められたプロジェクトは、期待と異なる結果を生み、再作業を強いられることが多い。一方、最初から明確な基準が示されれば、こうした試行錯誤を減らせる。そして、業務進行中にリーダーのフィードバックを待つ時間も最小限に抑えられる。
リーダーが業務指示前に10分ほどに考えれば、従業員の業務時間を1時間以上短縮できる。複数の従業員が同じ業務に取り組む場合、組織全体で節約される時間はさらに大きくなる。リーダーの時間の機会費用は高いとされるが、組織全体の効率性を考慮すれば、「リーダーが時間を投資する方が得策」という結論に至る。
ただし、リーダーがすべての詳細を直接決定すべきというわけではない。すべての情報を完璧に把握しているリーダーはいない。そのため、業務指示の際には、どの部分が確定事項で、どの部分が従業員に委任されるのかを明確に区別して伝えることが重要だ。例えば、「今月の広告予算は10万円で、クリック数を最大化することが目標だ。どのコンテンツにいくら配分するかはあなたが決めてほしい」というように指示すれば、従業員は自身の役割をより明確に理解できる。
最大の問題は「リーダー自身が望むことを把握していないこと」
本当の問題は、リーダーが自身の求める結果を正確に理解していないことだ。特に大企業でこのようなケースがよく見られる。上司からの指示に慣れたリーダーほど、「なぜこの業務を行うのか」を考えずに仕事を指示しがちだ。スタートアップと大企業の両方を経験した人なら、この状況に共感するだろう。
さらに深刻なのは、最終意思決定者であるリーダーが自身の目標すら適切に設定できないケースだ。例えば、あるブランドの代表が「日本のデパートに納品したい」という目標を持ちながら、具体的な計画なしに従業員に「日本進出戦略を立案せよ」と漠然と指示することがある。従業員は方向性が不明確で困惑するが、質問すると逆に「なぜそれを私に聞く」と叱責される。結果として、不要な時間が消費され、組織の資源も非効率的に運用される。
組織の時間浪費を削減し、早期退勤文化を確立する
リーダーは業務指示前に必ず「業務の枠組みを構築する訓練」を行うべきだ。会社の優先順位、自身の権限と責任、関連部署との協力関係などを考慮しつつ、従業員に期待する成果を具体的に説明することが重要である。この習慣が定着すれば、組織の運営効率が向上し、従業員の業務満足度も高まる。
不要な時間浪費を避け、効果的に機能する組織を目指すべきだ。業務を効率的に完了し、早めに退勤して私生活を楽しめる企業文化を創出することこそ、優れたリーダーの役割ではないだろうか。


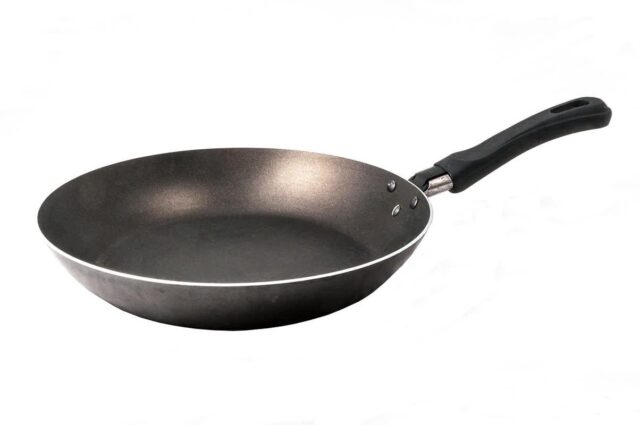





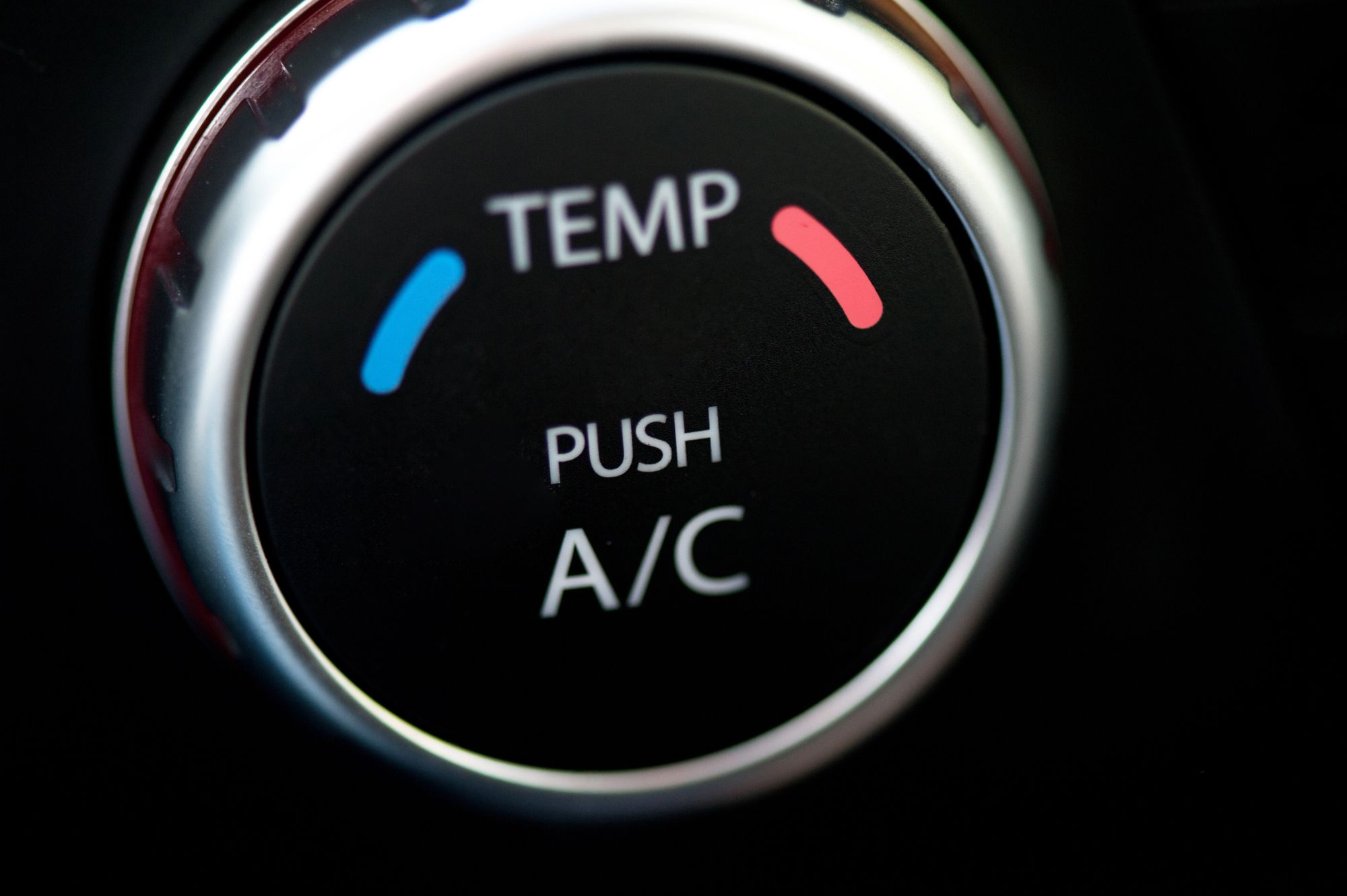





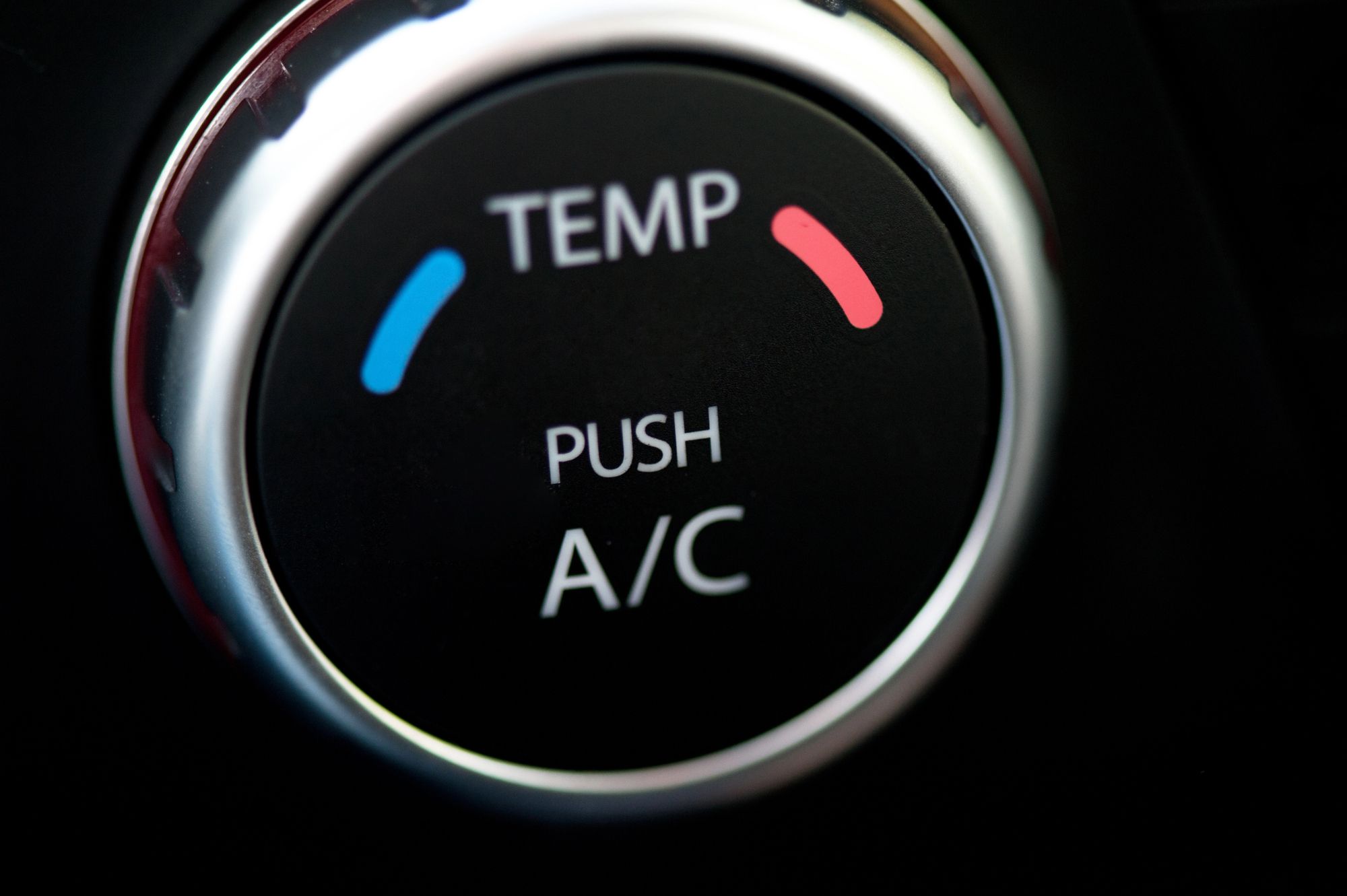






コメント0