
日本が水深8,000mの海底を調査できる無人深海探査機の開発を完了し、来年から運用を開始すると、読売新聞や共同通信などが13日報じた。
海洋研究開発機構(JAMSTEC)は最近開発した無人深海探査機「うらしま8000」を前日メディアに公開した。
無人潜水艇「うらしま」を改造したこの深海探査機は、既存のうらしまと比べて潜水可能深度が2倍以上に増加した。
うらしまは水深3,500m程度までしか探査できないが、うらしま8000は水深8,000mでも運用可能だ。
水深8,000mまで探査する性能は、広範な地域を航行できる「巡航型」無人深海探査機としては世界最高水準だと、JAMSTECは評価している。
エネルギー効率も改善され、約40時間の水中活動が可能になった。これは既存のうらしまより1.5倍以上長い。全長約10mのうらしま8000の重量は約7tで、指定された経路に沿って自律航行も可能だ。
音波で海底の地形と地層を調査し、1回の潜航で最大100㎢に及ぶ海域を探査できる。この深海探査機の運用により、排他的経済水域(EEZ)の探査可能範囲も従来の45%から98%に拡大される。
日本EEZの半分以上は水深4,000mを超え、既存の無人探査機が最大で潜航できる6,000mを超える場所も多いため、これまで日本では高性能探査機の必要性が継続的に指摘されてきた。うらしま8000は2002年から開発が進められてきた。
高水圧に耐えられるよう、主要機器を収納する圧力容器の素材をアルミニウムからチタンに変更した。
JAMSTECは、今年7〜8月と11月に地震震源地として知られる日本海溝などで試験潜航を実施した後、来年からうらしま8000の本格運用を開始する方針だ。
政府は深海探査機を用いて海底断層の動きを調査し、海底地図を作成。これを地震や津波の研究に活用するとともに、海底資源の確認も行う計画だ。
産経新聞は「海洋進出を強化する中国は深海探査を重視している」とし、うらしま8000の開発には中国に対抗する意味合いもあると指摘した。


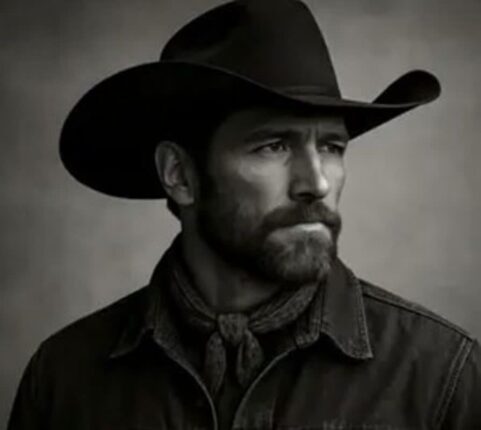


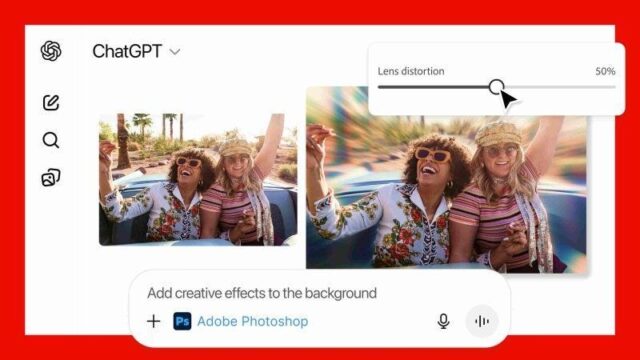















コメント0