
電子決済が活発な中国で、現金のない社会への移行が急速に進んでいる。中国では5年間でATM(現金自動預け払い機)の数が約4分の1減少したことが明らかになった。
26日、中国の界面新聞など現地メディアの報道によると、2024年末時点での中国のATM設置台数は80万2,700台で、5年前の2019年(109万7,700台)と比較して26.87%も急減した。現地メディアは、中国人民銀行(中央銀行)が発表した「2024年決済システム運営の全体状況」を引用し、わずか5年間で中国から約30万台のATMが消えたと伝えた。
2024年に銀行が処理した電子決済の取引件数は3,016億6,800万件で、5年前の2019年(2,233億8,800万件)と比べて35.04%増加した。2024年の電子決済取引総額は3,426兆元(約6京8,182兆円)に達し、2019年(2,607兆元・約5京1,922兆円)と比べて約30%増加した。
特に中国では、クレジットカード決済よりもアリペイやウィーチャットペイなどのモバイル決済が圧倒的に多く利用されている。このため、ATMを主力事業としていた上場企業は、ここ数年で収益が悪化している。
また最近、工商銀行、交通銀行、農業銀行、建設銀行などの大手国有銀行が次々とカードレスATMの入出金サービスを縮小または廃止する動きを見せており、主要な市中銀行もこれに追随する傾向にある。QRコードを利用したカードレスの入出金サービスは、実物のカードが不要なため、犯罪に悪用される可能性が指摘されてきた。
ただし、界面新聞は、僻地や高齢者層、外国人などの間では依然として現金需要があると指摘している。特に外国人観光客の場合、中国現地のスマートフォンと連動する必要があるQRコード決済に大きな困難を感じており、中国当局は現場での現金決済を可能にするよう促している。
あるアナリストは中国メディアの時代財経に対し、「特殊な需要が存在し、決済手段の多様性確保の観点からATMが完全に消滅することはないだろう」とし、「今後ATMは単なる現金引き出し機から、金融と生活を包括するサービスを提供する媒介へと進化するだろう」と述べた。












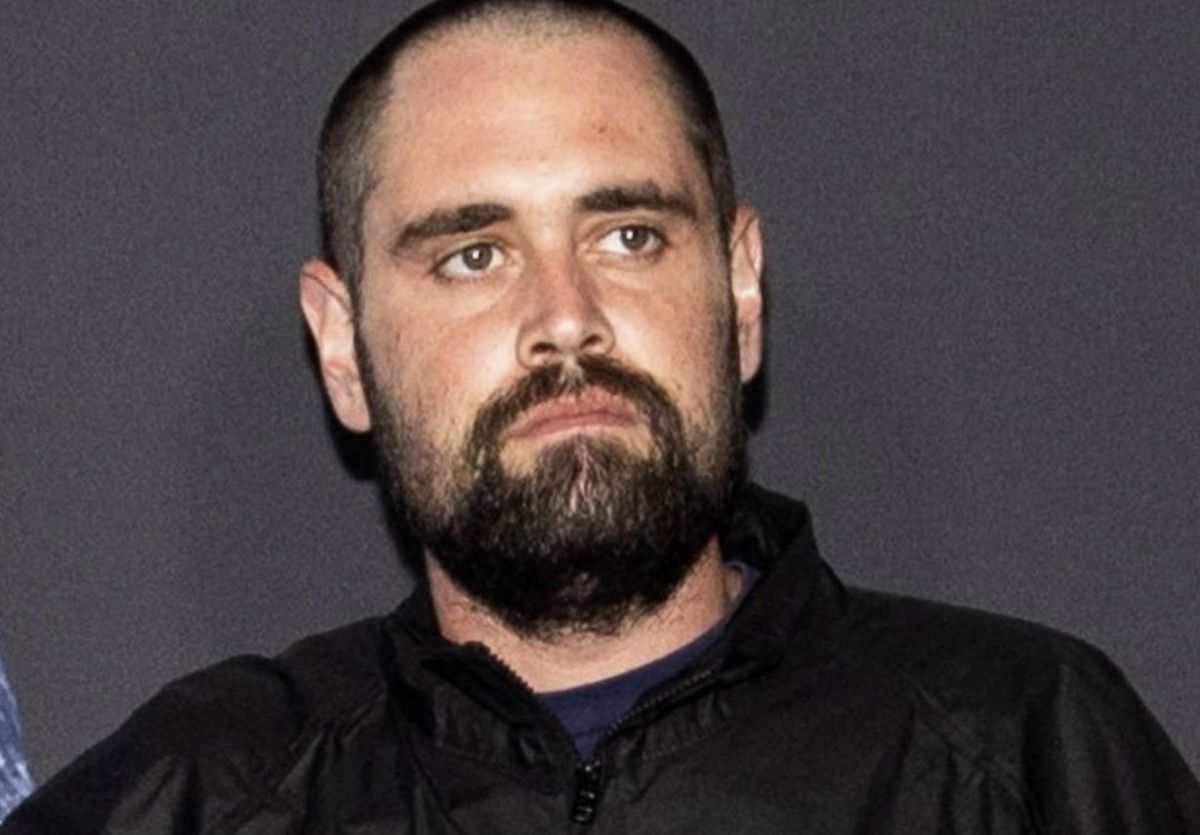








コメント0