0〜3歳児に年間3,600元支給、過去出産分にも遡及適用

人口減少と内需低迷という「二重苦」に直面する中国が、初めて全国レベルで現金による育児手当制度を導入する。0〜3歳の乳幼児を持つ家庭に対し、子ども1人あたり年間3,600元(約7万4,000円)を支給する内容で、出生率回復と消費促進の両面を狙った政策だ。
人口減少と消費低迷に対応する民生対策
29日付の中国国営新華社通信や英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)によると、中国共産党中央弁公庁と国務院弁公庁は「育児手当制度実施案」を発表したという。まずは2024年1月1日以降に生まれた子どもが対象となるが、2022〜2023年に出生した子どもについても一部遡及的に支給される予定だ。
支給開始時期や具体的な運用方針については、各省や自治区、直轄市が今後決定するという。
中国国家衛生健康委員会はこの制度を「育児負担を軽減し、出産を奨励する全国的な民生政策」と位置づけており、毎年2,000万人を超える乳幼児家庭が恩恵を受ける見通しだと説明している。
この措置は、出生率の低下と高齢化による労働力人口の減少、いわゆる「人口の崖」に対応するためのもの。あわせて内需の停滞を打開する狙いもあるとみられている。
中国では1978年に人口抑制策として「一人っ子政策」を導入したが、少子化が進む中で2016年に二人目、2021年には三人目までの出産を容認する方針へと転換している。
しかし、合計特殊出生率は人口維持に必要とされる2.1を大きく下回る水準にとどまり、実際に年間出生数は2022年以降、3年連続で1,000万人を下回った。総人口も同様に減少傾向が続いている。
専門家「効果は限定的でも政策転換の象徴」
経済専門家の間では、今回の育児手当の金額規模では、出産率や消費喚起に対する即効性は限定的との見方が多い。
英調査会社キャピタル・エコノミクスのエコノミスト、ホアン・ズーチュン氏はFTの取材に対し、「手当の規模は小さく、出生率や消費に大きな影響は与えないだろう」と指摘する一方で、「政府が初めて現金を直接家庭に支給する試みであり、政策転換の象徴となる可能性がある」と評価した。





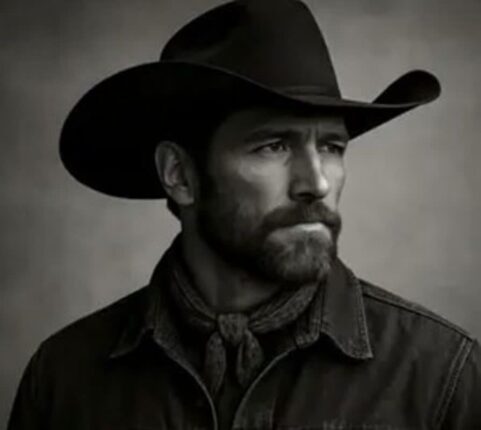















コメント0