
米国が予告していたインドへの報復関税発動まで残り数日と迫る中で、主要経済国の多くが対応を急ぐ一方、インドは比較的落ち着いた姿勢を崩していない。インド太平洋地域において、中国を牽制するうえで米国にとって不可欠な存在とされるインドが、その地政学的に優位性を交渉カードとして活用しているとの見方が広がっている。
29日(現地時間)、香港のサウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)などによれば、ドナルド・トランプ米大統領は今年4月、インドに対して26%の相互関税を課す方針を表明した。以降、インド側の交渉団は米国を5度にわたって訪問し、関税率の引き下げを求める交渉を続けてきたという。
トランプ大統領は今月7日、「インドとの合意はほぼ最終段階にある」と発言し、一時は交渉妥結が近いとの観測も出ていたが、8月1日に予定されている関税発動を目前に控えた29日時点でも、合意に至ったという発表は出ていない。専門家の間では、米国とインドが期限までに交渉をまとめるのは難しいとの見方が強まっている。
米国との関税交渉が難航している最大の要因は、農業分野の市場開放問題にあるとされる。インドにとって米国産の農産物や乳製品に対する関税を大幅に引き下げることは、ナレンドラ・モディ政権の主要支持層である農民の反発を招く懸念があるためだという。農業はインド国内で人口の約42%が生計を立てている重要な産業でもあり、政治的にも極めてデリケートな分野となっている。
さらに、ヒンドゥー教における牛の神聖視という文化的背景から、乳製品の輸入も厳しく制限されており、輸入牛乳がインド同様の放牧飼育によって生産されたものであるかまでが問われるという。こうした事情からインド側は農産品の市場開放に慎重な姿勢を取っているが、これに対し米国は、鉄鋼・アルミニウム・自動車への高関税の引き下げを求めるインド側の主張に応じない構えだと報じられている。
インドのピユシュ・ゴヤル商工相は、「いかなる貿易合意も、期限や締め切りによって決めるものではない」と述べ、焦らず交渉を進める方針を示している。
米国による関税発動が目前に迫る中でも、インドが交渉を急いでいない背景には、インドがインド太平洋地域において中国の影響力を抑制できる重要な国として、米国からも一目置かれているという自負があるとみられている。米メディアCNBCも、軍事的にも製造業分野でも中国の代替となる可能性があるインドの存在を、米国が重視していると指摘している。
また、ブラジル・ロシア・インド・中国など10の新興経済国で構成される「BRICS」においても、インドは中国と主導権を争う立場にあり、国際的な存在感を高めている。
現在、インドと米国は包括的な貿易協定の第1段階合意案を策定中とされており、今年10月に予定されている日米豪印の安全保障枠組み「クアッド(Quad)」首脳会談の際、トランプ大統領のインド訪問にあわせて合意が発表される可能性も取り沙汰されている。


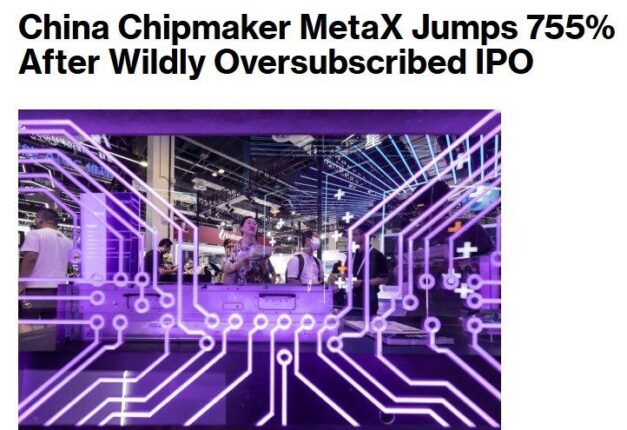


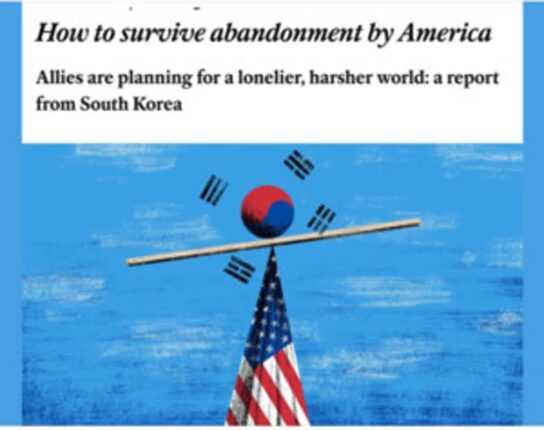

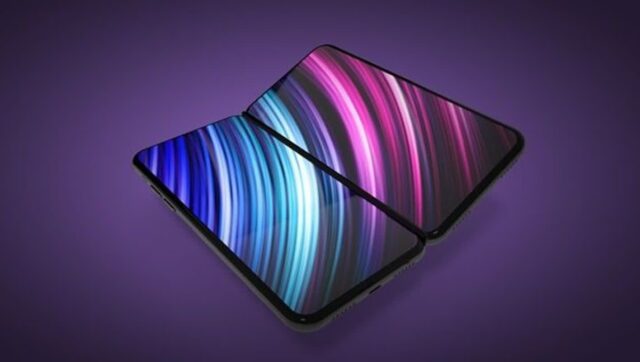




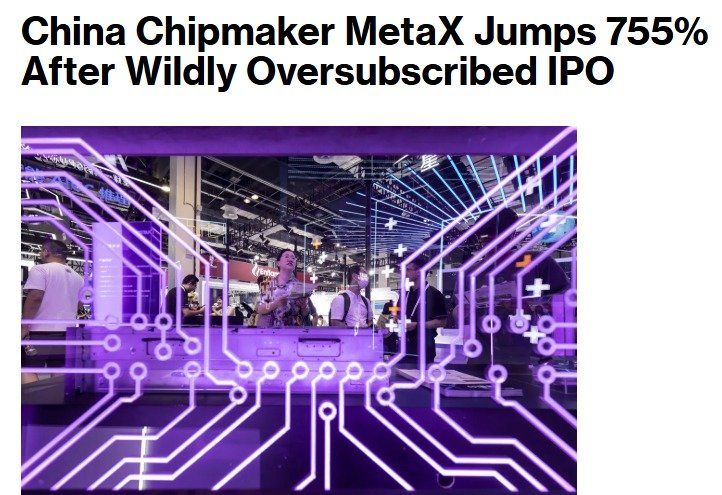







コメント0