
ドナルド・トランプ米大統領の復帰後、経済への政治的統制が一層強まり、中国共産党を模倣する動きが見られている。米国は国家資本主義へ向かっており、米国的特色を持ちながらも中国の手法も一部取り入れていると、『ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)』が11日に分析した。
海外メディア『ニューシス』によれば、過去にも政府が経済に介入した事例はあったが、いずれも一時的な措置だった。
かつては「中国が自由化すれば経済は米国に近づく」との見方が一般的だったが、現状ではむしろ米国の資本主義が中国に近づいているとWSJは指摘する。
WSJは、トランプ大統領がインテルのCEOに辞任を要求した事例を筆頭に、複数の政治介入を挙げた。エヌビディアとAMDが中国向けに販売する特定チップの収益15%を政府と共有することで合意した件や、日本製鉄によるUSスチール買収の条件として「黄金株」を政府に提供した件などである。さらに、貿易交渉の中で相手国から1兆5,000億ドル(約222兆円)の投資を約束させたことも経済統制の一例とされた。
これは国家が生産手段を所有する社会主義ではなく、国家資本主義に近い。WSJはこれを社会主義と資本主義の混合体で、国家が名目上私企業の意思決定を主導する形態と定義している。
米国政府は過去にも、第二次世界大戦中の生産独占、国防物資生産法に基づく緊急時の生産統制、2007〜2009年の金融危機における銀行・自動車会社救済など、直接的介入を行ってきた。ただし、これらはいずれも短期的対応だった。
バイデン政権では、インフレ削減法(IRA)による4,000億ドル(約59兆円)規模のクリーンエネルギー融資や、国内半導体製造への390億ドル(約5兆7,600億円)補助金が承認された。そのうち85億ドル(約1兆2,550億円)はインテルに支給され、トランプ大統領が同社CEOの解任要求を行う根拠の一つとなった。
また、バイデン政権は中国依存が高い重要鉱物分野への投資促進を目的に国富ファンド設立を検討。国防総省は先月、重要鉱物採掘企業MPマテリアルズの株式15%取得を表明した。
WSJは、国家資本主義は市場より効率的に資本を配分できず、歪みや浪費、縁故主義などの副作用を招くと警告する。早期に導入したロシア、ブラジル、フランスはいずれも成長が鈍化した。中国も習近平国家主席の下で統制を強化した結果、過剰貯蓄や過剰生産が生じ、鉄鋼や自動車などの価格・利益が急落している。
米国でも国家安全保障を名目とする介入や誘致策が、フォックスコンのウィスコンシン州工場やテスラのニューヨーク州バッファロー工場のような無駄な事業につながったとWSJは指摘している。
さらに同紙は、国家資本主義が政治的統制の手段として使われる点を問題視。中国では習主席が経済的手段を動員して政敵を排除し、アリババ共同創業者の馬雲氏は金融革新を批判後、IPO中止や巨額罰金を受け、長期間公の場から姿を消した。トランプ大統領も批判的なメディアや企業に行政命令や規制権限を行使し、独立性を持ってきた労働統計局やFRBに対して政治的統制を試みている。WSJは、これが官僚組織が共産党に完全従属する中国の体制と類似していると結んでいる。





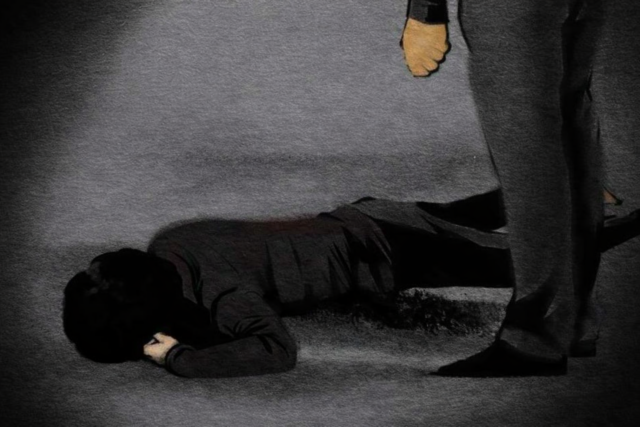
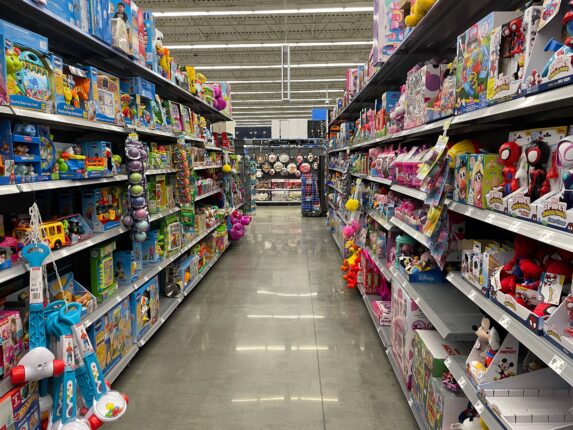



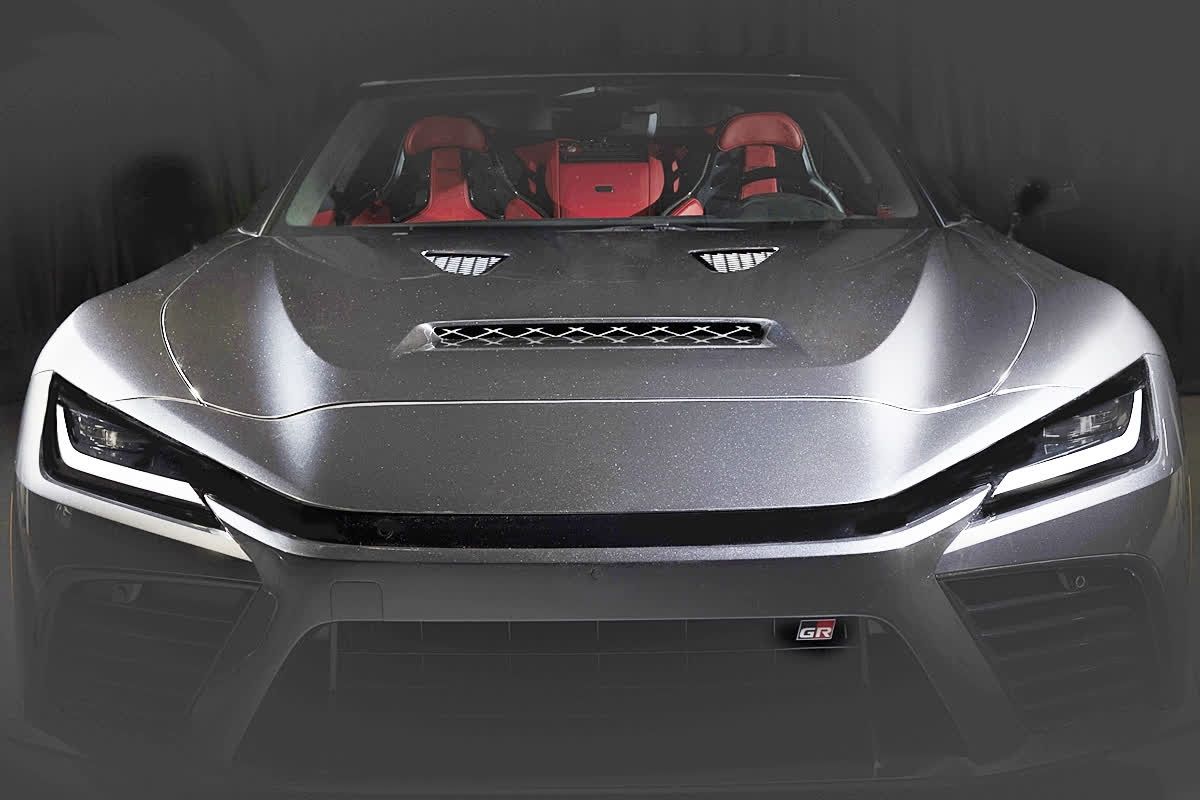











コメント0