
米政府はインテルに続き、他企業の株式取得に乗り出す方針だ。25日(現地時間)のCNBCによると、米国家経済会議(NEC)のケビン・ハセット委員長は同日のインタビューで、米政府がインテルに続き他企業の株式取得に乗り出すことを明らかにし、これを米国型国富ファンド設立戦略と位置付けた。ハセット委員長は「将来的にさらなる取引が行われると確信している」と述べ、「この産業に限らず、他の産業でも可能性がある」と語った。
米政府はインテルの普通株4億3,330万株を1株当たり20.47ドル(約3,016円)で購入し、9.9%の株式を取得した。総投資額は89億ドル(約1兆3,113億円)に上る。この資金の大部分は、ジョー・バイデン前政権下で成立した半導体法の助成金に関連するものである。米政府は取締役会の議席やその他の経営権は保持しないことを決定した。米国のドナルド・トランプ大統領は「こうした収益性の高い取引を行う企業を支援する」とし、「彼らの株価上昇は望ましい。米国がより豊かになる」と主張した。
一方、ハセット委員長は政府が企業経営に関与しない方針を強調した。彼は「選挙運動時からトランプ大統領は米国が国富ファンドを設立すべきだと明言していた」と述べ、「将来的にさらなる取引が行われると確信している」と語った。
トランプ大統領は今年2月初旬、国富ファンド設立のための大統領令に署名した。国富ファンドは、主に豊富な天然資源を有する小国が投資資金として活用する手段である。ノルウェーが約1兆8,000億ドル(約265兆2,031億円)規模の世界最大の国富ファンドを保有しており、中国やサウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)なども大規模な国富ファンドを運用している。
米政府が企業株式を大量に取得するのは異例だ。しかし、ハセット委員長は2008年の金融危機時に米政府がファニーメイ(Fannie Mae・連邦住宅抵当公庫)とフレディマック(Freddie Mac・連邦住宅金融抵当公庫)の株式を取得した例を挙げ、前例が全くないわけではないと説明した。





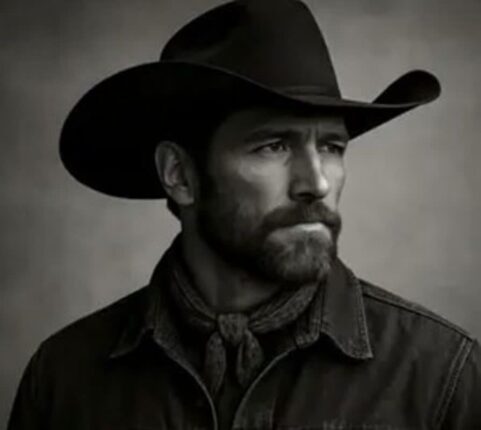
















コメント0