
東京の繁華街・渋谷駅から徒歩30分の場所にある東京大学・生産技術研究所に足を踏み入れると、至る所に外国人留学生で賑わっていた。半導体や精密加工製品の研究用クリーンルーム、細菌研究を行うP2レベルの生体実験室では、フランスからの留学生が研究に従事していた。教授研究室はもちろん、学内食堂でも日本語よりも英語やフランス語が飛び交っていた。外国人の姿がほとんど見られない本郷キャンパスとは対照的に、フランス、中国、インドなど各国の学生が集まる「人材のるつぼ」と呼べる光景だった。
駒場キャンパスに位置する生産技術研究所は、日本の宇宙工学の扉を開いた超小型ロケット「ペンシルロケット」や、日本自動車産業の復興を牽引した日産自動車の「オートマチックトランスミッション」などが開発された産業技術のメッカだ。この研究所で働く外国人大学院生の割合は全体の約48.2%に上り、東京大学学部生(15%)の3倍以上となっている。年吉洋所長は「国際化こそがこの研究所の最大の特徴だ」と語った。
生産技術研究所における外国人比率の高さは、長年の国際協力の歴史によるものだ。1995年以降、「フランス国立科学研究センター(CNRS)」との相互訪問研究が継続されていることが代表例だ。また、超精密工学機械研究のために、30年以上にわたり「マイクロナノメカトロニクス国際研究センター(LIMMS)」を共同運営している。LIMMS所属のキム・ボムジュン東京大学教授は「日本の精密機械製造能力とフランスの化学・生物学の基幹技術が融合した国際共同研究の好例」と説明した。
これまでに研究所を訪れた海外研究者の数は380名を超える。一度訪れると、2~3年にわたり共同研究が行われる。年吉所長は「生産技術研究所は東京に所在するが、その研究レベルは欧州の研究機関にも引けを取らない」と自負するほど、両者の協力関係は非常に強固だ。
強固な産学連携も、留学生が多数集まる背景の一因になっている。生産技術研究所は、トヨタ自動車や三菱などの日本を代表する大実業家と緊密な協力関係を築いている。革新的シミュレーション研究センター(CISS)の吉川暢宏所長は「日本の大企業への就職可能性は、留学生が日本を選ぶ主な動機のひとつであり、東京大学の大きな魅力の一つだ」と語った。
これまで外国人留学生の受け入れに消極的だという批判を受けていた東京大学も、最近では180度の変革を遂げつつある。先端技術を背景に「グローバル人材ブラックホール」となった米国や、豊富な自国の人材プールを有する中国との工学人材競争に打ち勝たなければならないという切迫感がその背景にある。
東京大学と文部科学省は、今年から日本で学ぶインド人留学生約270名に対して、年間300万円の支援を開始することを決定した。政府は、産学連携の強化も図りながら、2028年までに国内のインド人留学生数を現状の2倍に増やす計画だ。昨年11月時点で、東京大学に在籍するインド人学生は83名で、全留学生の1.6%にとどまっている。東南アジア(インドネシア、タイ、フィリピン)出身の留学生は195名(3.72%)程度だ。インドおよび東南アジア出身の留学生が、中国(67.7%)や韓国(6.8%)に比べて少ないのは、相対的に距離が遠く、言語の壁があるためだという指摘がある。
こうした障壁を打破するために、東京大学は昨年、英語のみを使用し、学部と大学院修士課程にまたがる5年制の教育課程「UTokyo College of Design」を新設した。海外の高校の卒業時期に合わせ、学期開始が4月ではなく9月となる。定員100名のうち、約半数が海外留学生だ。東京大学工学部の岡部徹教授は「英米圏に合わせたカリキュラムの構築により、インドやフィリピンなど英語圏出身の留学生の受け入れに大いに貢献できると期待している」と語った。



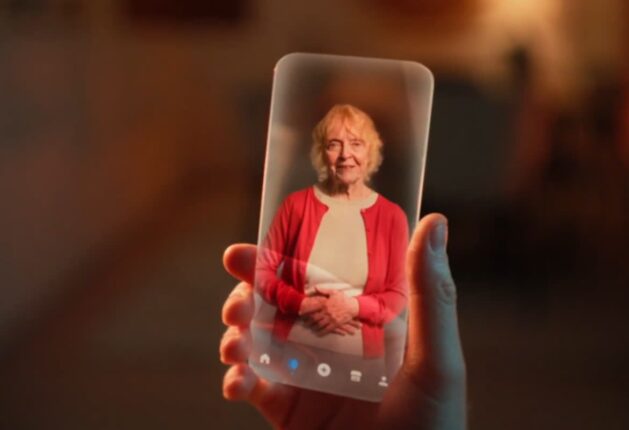








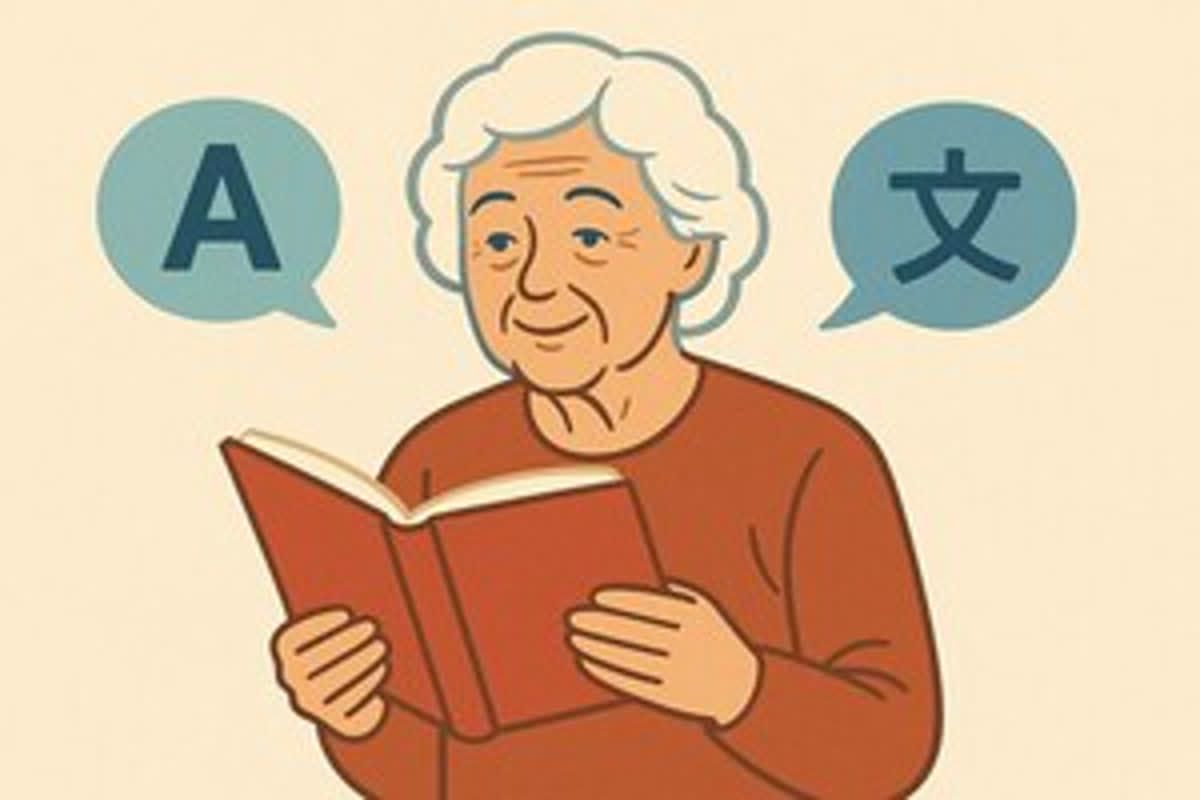








コメント0