
宇宙に送られた実験用マウス75匹のうち10匹が生還できなかった。ロシア国営宇宙公社「ロスコスモス」は、実験用動植物を搭載した衛星「ビオンM(Bion-M)2号」が30日間の宇宙軌道飛行を終え、19日(現地時間)にカザフスタン国境近くのオレンブルク草原地帯に着陸したと発表した。
先月の20日に打ち上げられたこの衛星には、マウスのほかショウジョウバエ1,500匹、アリ、菌類、種子、海藻類などが搭載されていた。今回の宇宙実験は、強い放射線と無重力状態にさらされる宇宙環境が生物に与える影響を調べるためのものであった。
この目的のため、衛星は高度370~380kmの上空で、通常の傾斜軌道よりも放射線が強い97度の傾斜角の極軌道を飛行した。極地に近づくほど地球の磁場が弱まり、宇宙放射線にさらされる量が増加する。ロスコスモスによると、極軌道は他の地球低軌道と比べて放射線の曝露量が最低でも10倍以上だが、宇宙船内では30%高いレベルに調整したという。

宇宙でマウスは3匹ずつのグループに分けられ、それぞれ25個の円筒形容器に入れられて宇宙を飛行した。この容器には照明、換気、給餌、排泄物処理など、マウスが宇宙で生存できるシステムが整えられている。地球に戻った動植物は翌日モスクワの国立研究所に送られた。
今回の実験を担当するロシア科学アカデミー生物医学問題研究所(IBMP)のオレグ・オルロフ所長は、「(生還した)生物はすべて良好な状態だ」とし、「マウスが死亡した原因はそれぞれ異なる」と述べた。彼は宇宙に送られたマウスがオスで攻撃的なため、集団内の対立が激しかったことも一因として指摘した。さらに「データを基にマウスがどの段階でなぜ死亡したのかを分析する計画だ」と語った。
ロスコスモスのドミトリー・バカノフ社長は、「ビオンM 2号の実験結果を基に宇宙飛行士を極軌道に送ることができるかどうかを検討する」と述べた。実験結果は数か月後に公開される予定だという。ただし、12テラバイトに及ぶ映像データの分析完了までには、さらに長期間を要すると予想される。科学者たちは作業の効率化を図るため、人工知能の活用を計画している。

今回の実験は2013年の「ビオンM 1号」以来、12年ぶりに行われたロシアの2回目の大規模宇宙動物実験だ。1号機にはマウスなどの齧歯類53匹、トカゲ15匹、カタツムリ20匹などが搭載されていた。地球上空575kmの軌道で30日間滞在した最初の実験では、実験動物の半数以上が死亡した状態で帰還した。
ロシアの科学者たちは今回の実験のために2グループの対照群マウスも用意した。一方のグループは地上環境の実験室、もう一方のグループは宇宙環境を模した実験室に入れ、同じ期間中にマウスの状態をリアルタイムで観察した。一部のマウスには生理的データを収集するチップも埋め込まれた。

科学者たちは着陸直後に現場で1次解剖分析を実施し、その後1日、5日、15日、30日目にそれぞれ追加解剖を行い、宇宙放射線がマウスに与えた影響を分析し、対照群と比較する計画である。
軌道再突入中には、カプセル外部に設置した隕石シミュレーターを通じて、隕石に埋もれている微生物が極度の圧力と高熱に耐えられるかどうかを評価する実験も行われた。これは地球上の生命の起源が宇宙にあるとする「パンスペルミア説」を検証する試みの一環だった。





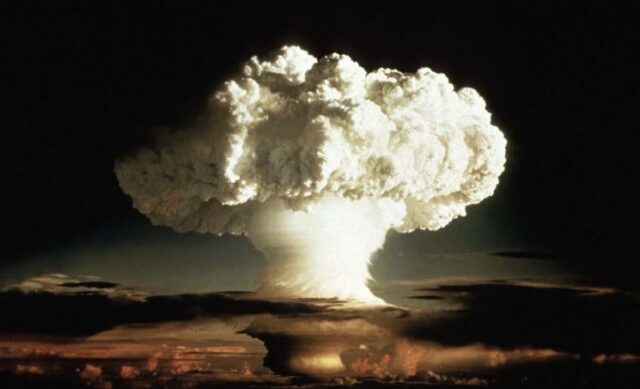










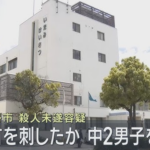



コメント0