中国経済メディアの第一財経は25日、中国畜産業協会ロバ産業分会の関係者の発言を引用し、中国で深刻化している「ロバ供給不足」の背景には、ロバの皮を原料とする滋養食品の需要急増があると報じた。

第一財経によると、中国は1990年代初めまで世界最大のロバ飼育国で、一時は1,120万頭を飼育し、世界全体の25%を占めていた。多くの農家が1、2頭を飼い、畑仕事や荷物の運搬に利用していた。ロバは体力があり道を覚えるのが得意で、馬に比べ飼料代が安く、農民に重宝されてきた。
しかし時代の変化とともに、農耕や運搬手段としての価値が低下し、2015年には約400万頭まで減少し、現在は146万頭ほどにまで落ち込んでいる。こうしたなかで予想外の事態が起きた。経済成長とともに中間層を中心に健康・美容への関心が高まり、ロバの皮を煮詰めて固めた伝統補養食「阿膠(アギョウ)」の需要が爆発的に増加したのである。
阿膠は濃い褐色の固形物で、水に溶かして服用する。漢の時代から宮廷の滋養薬として用いられ、貧血改善、老化防止、体力増強に効果があるとされている。近年はコラーゲン補給効果も注目され、美容・アンチエイジング食品として宣伝され、需要は一層拡大した。
国内供給が追いつかず、阿膠関連業者は海外に目を向けた。第一財経は「中国の商人が数年前から世界中を巡り、ロバを探し回ってきた」とし、中央アジアやパキスタンを経て、アフリカや南米にまで輸入ルートを広げたと伝えている。
最初の輸入先は、中国に近接し輸送経路が短い中央アジアだった。新華社通信によると、2016年に中国はキルギスとの国境で初めてロバ560頭を輸入し、カザフスタンからも98頭を調達した。しかし中央アジアの飼育頭数は限られており、中国の阿膠需要を賄うには不十分だった。
次に目を向けたのがアフリカである。国連食糧農業機関(FAO)によれば、アフリカは2008年にアジアを抜き世界最大のロバ飼育地域となった。だが中国の輸入急増により、アフリカでは価格高騰と個体数減少が深刻化。ブルキナファソでは2014年から2016年にロバ価格が60%以上上昇し、ケニアの飼育頭数は2009年から2019年の10年間で半減した。ついに2024年2月、アフリカ連合(AU)第37回首脳会議で、加盟国はロバの皮取引を今後15年間禁止する決定を下した。
中国国内で再び飼育頭数を増やせば解決できるが、それも容易ではないという。遼城大学ロバ生態飼養研究院の王昌波院長は「ロバの妊娠期間は1年から1年半、子ロバは生後6カ月まで授乳が必要で、成体として出荷できるのは4年目になってからだ」と説明した。その上で「雌1頭が一生に産む子は10頭ほどにとどまり、個体数増加のペースは極めて遅い」と指摘している。



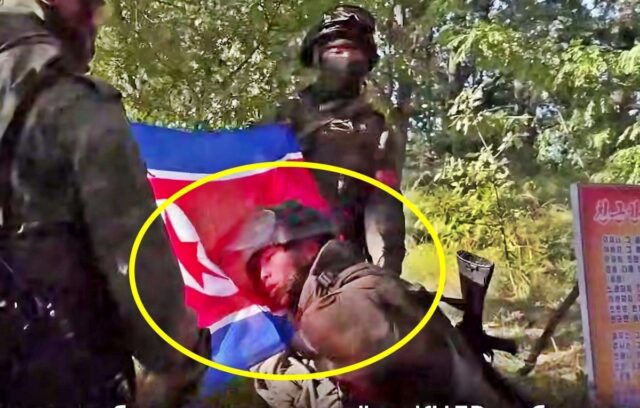











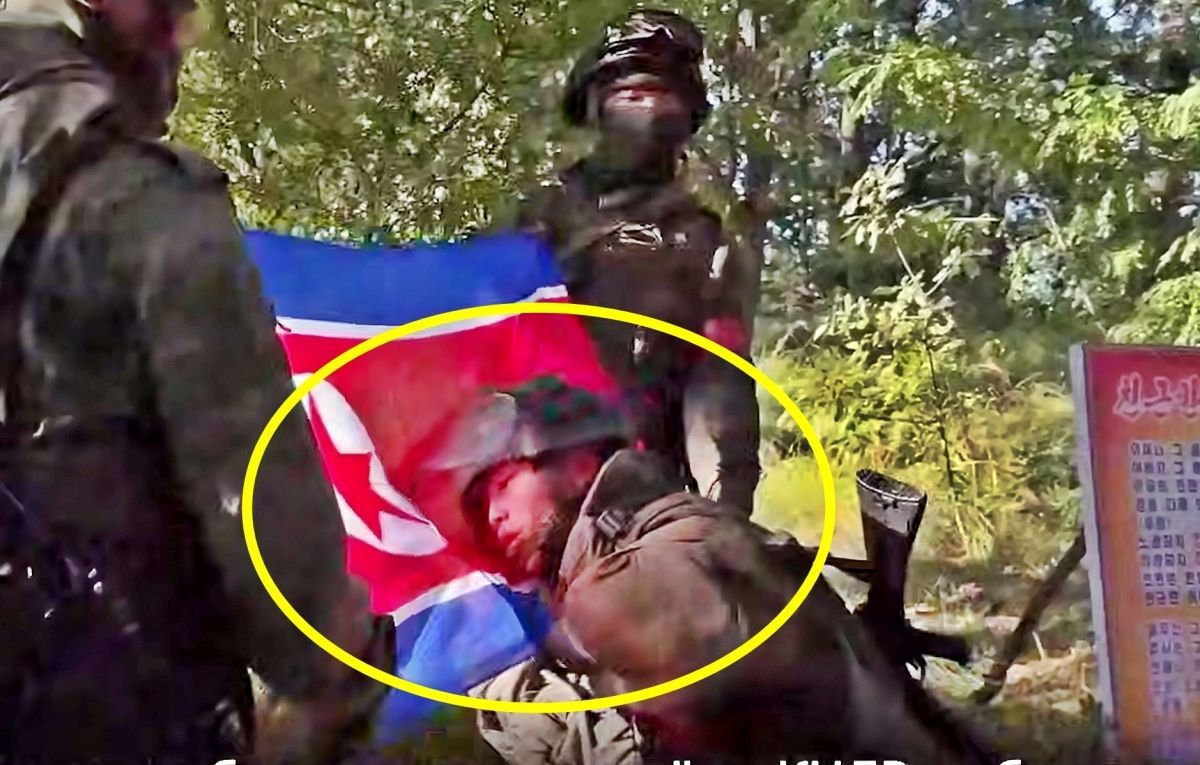






コメント0