
安全資産を好み、これまで銀行の預金や定期積金に資金を預けてきた投資スタイルが、近年変化しつつある。
近年の物価上昇を背景に老後資金への不安が高まる中、昨年リニューアルされた少額投資非課税制度(NISA)が「実践的な資産運用手段」として注目を集め、資産構成に占める株式などの割合が急速に拡大している。
日本経済新聞によると、同紙が読者1,934人を対象に実施したアンケート調査(8月28日〜9月2日)では、回答者の72%が預金以外の金融商品に投資していると回答した。
また、29%が2020年以降に投資を始めたと答え、そのうち45%が「NISAがきっかけ」と回答した。NISA口座を開設し株式などを取引した場合、得られた利益に課税されない仕組みとなっている。
政府は投資活性化策として、昨年からNISAの年間非課税枠を120万円から360万円へ、総投資上限額を800万円から1,800万円へと大幅に拡大した。さらに、非課税期間を最長20年から無期限へ延長している点が大きな特徴である。
調査によると、毎月の平均投資額は約10万円。30〜40代では月10万〜20万円を投資している人が3割にのぼる。新規投資額を3年前と比べると、20〜40代の約3割が「2倍以上に増やした」と回答した。
日経は「家計金融資産のうち、現金・預金が51%を占める一方、株式・投資信託は18%にとどまる」とし、「若年層の投資意識が高まることで、資産構成が米国型に近づく可能性がある」と分析している。米国では株式・投資信託が55%、現金・預金は12%にすぎない。
投資目的では、「老後資金の形成」が67%(複数回答)で最多。次いで「インフレ対策」が49%を占めた。
2019年、金融庁が「公的年金だけでは老後に約2,000万円不足する」とする報告書を公表し、いわゆる「老後2,000万円問題」が社会的関心を集めた。平均寿命の延びと少子高齢化が進む中、安定した老後生活にはかつてより多くの資金が必要とされている。
今回の調査でも、こうした「老後2,000万円問題」と継続する物価高が、個人投資家の意識を「貯蓄から投資へ」と向かわせていることが明らかとなった。東京在住の40代男性は「消費を抑えてでも投資に回している。インフレの時代に投資をしないことの方がリスクだ」と語っている。





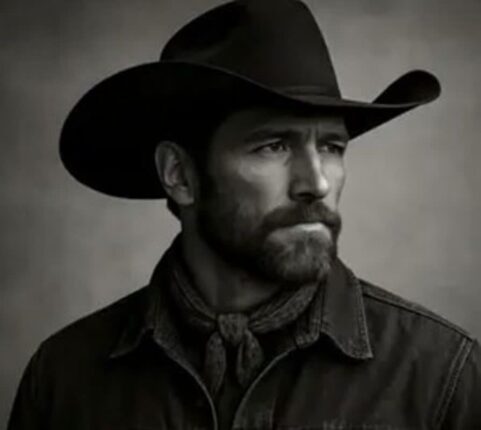
















コメント0