
国内で、女性の身体的特徴を維持したまま男性への性別変更を希望する申請者に対し、性別変更を認める裁判所の判決が下された。
この判決は、性別変更の過程で身体的変化を強制する従来の法律条項が、憲法に抵触する可能性があるとの重要な判断として注目されている。
24日付けの『日本経済新聞』によると、札幌家庭裁判所は19日、性同一性障害を持つ申請者A氏に対し、健康上の理由からホルモン治療や乳房切除手術などを行っていないにもかかわらず、女性から男性への性別変更を認める決定を下した。
国内で性別変更を行うには、『性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律』に基づき、5つの要件すべてを満たす必要がある。
①18歳以上であること
②婚姻していないこと
③未成年の子供がいないこと
④生殖機能がないこと(子宮や卵巣、精巣などの生殖器を手術で除去し、子供を産むことができなくなることを意味する)
⑤身体の性器が変更後の性別と近い外観になっていること
札幌家庭裁判所によると、A氏は①18歳以上、②婚姻していない、③未成年の子供がいない、の3要件は満たしているものの、喘息やアレルギーのためホルモン治療を受けられず、乳房切除術なども行っていなかったことから、⑤の「外観」要件は満たしていなかったという。
しかし、札幌家庭裁判所は「法制定以降、医学的知見の進展により、外観要件の要求は合理的関連性を欠く」として、これを憲法違反と判断した。
また、特例法の外観要件は公衆浴場などでの混乱を考慮したものと説明しつつ、裁判所は「性同一性障害を持つ人々の多くは、自身の身体に違和感を抱き、他人に見せることを避ける傾向が強いため、公衆浴場などで混乱が生じる可能性は極めて低い」と指摘した。
近年、性的マイノリティの権利を尊重する司法判断が相次いで下されている。
最高裁判所は2019年、生殖機能要件について「合憲」と判断したが、2023年10月には同要件を「違憲」と判示した。当時、請求人は男性から女性への性別変更を希望していたが、性器切除を行っていなかったため、「生殖機能」要件および「外観」要件の両方を満たしていなかった。
最高裁は「生殖機能」要件について、憲法第13条が保障する「自己の意思に反して身体を侵されない自由」を重大に制限するものと判断し、違憲と結論付けた。ただし、「外観」要件については直接判断せず、事件は広島高等裁判所に差し戻された。
広島高等裁判所は2024年7月、当該要件について「違憲の余地がある」と判断した。裁判所は、ホルモン治療によって外部性器の形状が変化する可能性を認め、実際に申請者もホルモン治療により体の複数の部位で女性的特徴が見られたことから、結果的に外観要件を満たしたと認定した。これにより、性別適合手術を行わなくても、男性から女性への性別変更が認められた。
この判決は、外観要件に対する裁判所の慎重な姿勢を示すとともに、手術を強制しない性別変更の認定範囲を広げる重要な一歩として評価されている。
一方、非婚要件については、京都家庭裁判所が今年3月「直ちに憲法違反とは言えない」とし、性別変更を認めなかった。
最高裁の違憲判断を受け、国会では法改正の検討が始まったものの、現時点では結論には至っていない。




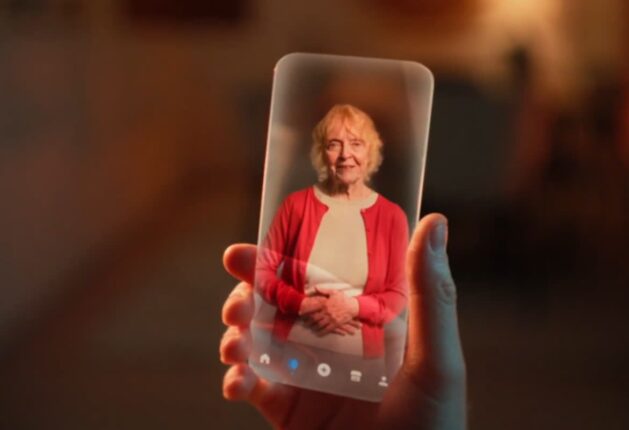









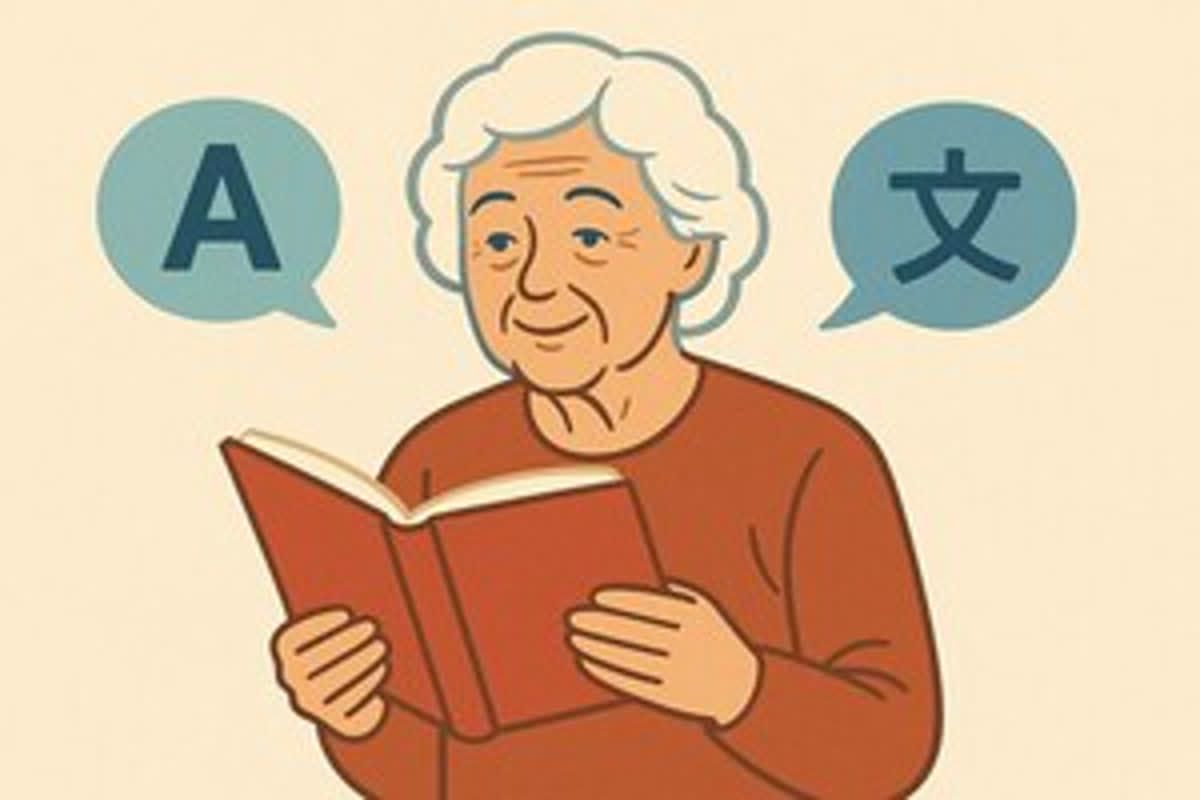






コメント0