気候変動によるバニラ危機、食品産業への打撃懸念
バニラアイスやバニララテなどを愛する「バニラ愛好家」に絶望的なニュースが報じられた。気候変動の影響で、バニラと受粉を担う昆虫の生息地がかけ離れ、自然な受粉が難しくなりつつあるという。
4日(現地時間)、ベルギーのルーヴァン・カトリック大学のシャーロット・ワテイン博士の研究チームは国際学術誌『フロンティアーズ・イン・プラント・サイエンス(Frontiers in Plant Science)』にバニラ植物と受粉媒介昆虫の生息地の変化に関する分析結果を発表した。
研究チームはバニラ種の11種の植物とそれらの受粉を助ける7種の昆虫を対象に気候変動による生息地の変化を予測した。分析結果、気温上昇時にバニラ種の植物のうち7種は生息地が拡大する可能性があるが、残りの4種は生息地が縮小すると判明した。

さらに深刻なのは、気温の上昇によって植物と花粉媒介昆虫の生息地が乖離し、自然受粉が不可能になる恐れがあることだ。
気温上昇に伴いすべての花粉媒介昆虫の生息地は縮小傾向を示し、気温上昇幅が大きいほど生息地の縮小幅も拡大することが研究で判明した。
特に大半のバニラ種は特定の昆虫に依存した受粉メカニズムを持つため、植物と昆虫の生息地の重複範囲が縮小すれば自然受粉が不可能になる恐れがあると研究チームは警告した。
さらに懸念されるのは、単一種の昆虫にのみ依存するバニラ品種の場合、植物と昆虫の生息地の重複面積が60~90%も減少する可能性があるという予測だ。これはバニラ生産に深刻な打撃を与える要因となりうる。
バニラは世界的にコーヒー、チョコレートと並ぶ高付加価値の熱帯作物として分類され、天然バニラの大半はプラニフォリア種から供給される。この品種は高温、干ばつ、病害などに脆弱で、気候変動による影響を受けやすいことであることが知られている。
バニラの香りはバニララテやアイスクリームといった食品だけでなく、製薬や化粧品など多様な産業分野で活用されており、世界的な供給障害が生じれば経済的な波及効果も甚大になると懸念されている。
研究チームは「バニラ種と特定の花粉媒介昆虫の特殊な関係のため、新たな昆虫がこれに代わることは困難かもしれない」とし、「気候変動に対する熱帯地域のバニラ農業システムのレジリエンス強化対策が急務だ」と強調した。
共同著者のバート・マイス教授も「野生バニラ種の個体群とその持つ膨大な遺伝的多様性を保全することは、世界の食品産業の主要な熱帯作物であるバニラの将来を保証するために不可欠だ」と補足した。




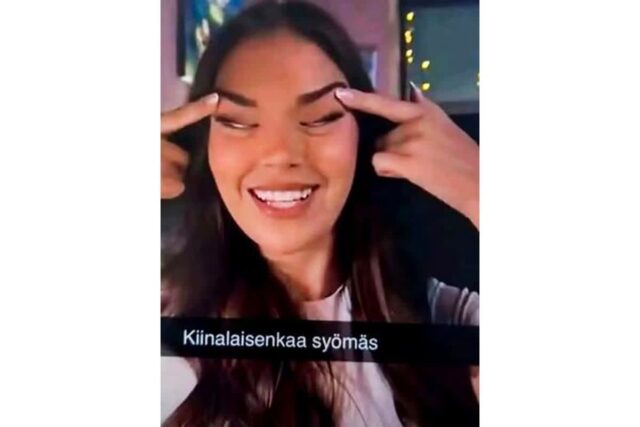








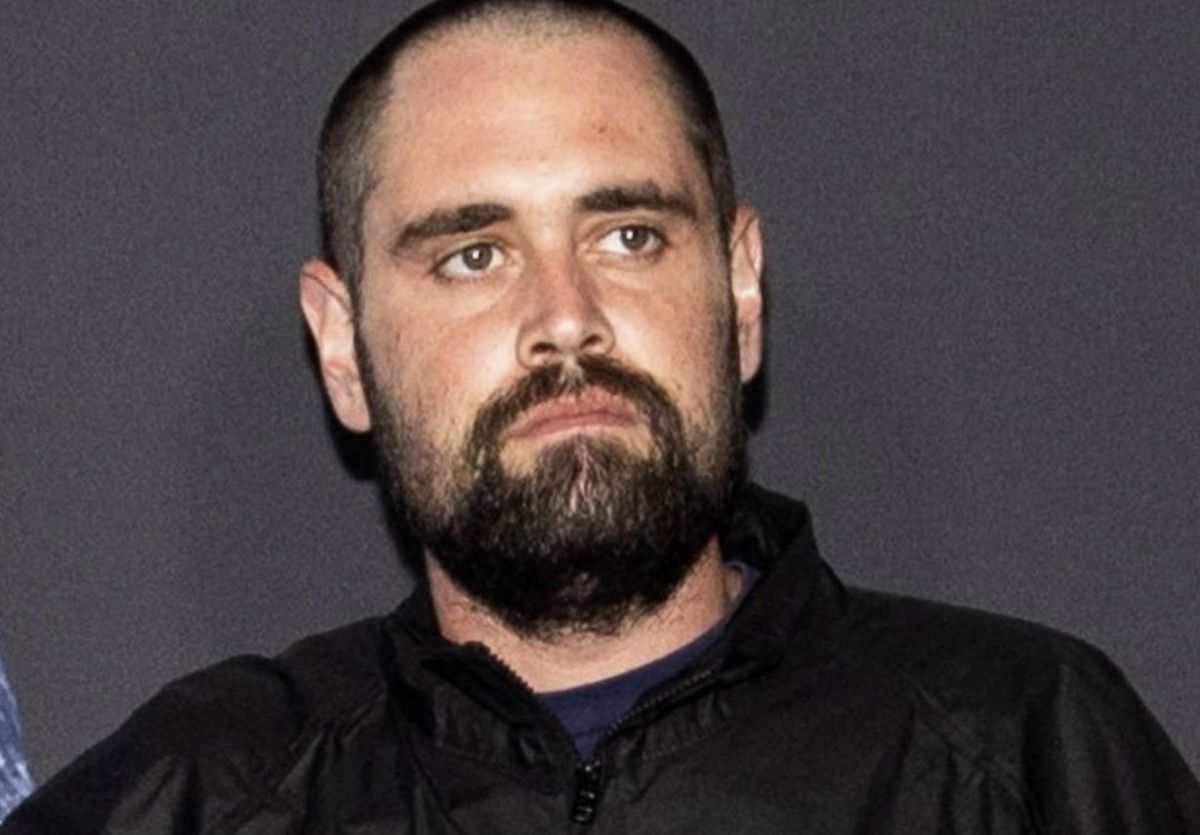








コメント0