
遺伝子を編集した豚の肺を初めて脳死者に移植し、9日間機能を維持できたとする画期的な研究成果が報告された。これまで心臓、腎臓、肝臓などに限られていた異種移植を肺にまで拡大できる可能性が示唆された。
26日付の医学誌『ネイチャー・メディシン(Nature Medicine)』によると、中国・広州医科大学附属第一病院のフー・ジェンシン博士率いる中国・韓国・日本・米国の国際研究チームは、CRISPR-Cas9遺伝子編集技術で改変した豚の左肺を39歳の脳死者に移植し、9日間にわたって機能を維持できたと報告した。

これまで、拒絶反応を抑えるために遺伝子編集した豚の臓器を用いた移植手術は、腎臓、心臓、肝臓などの臨床試験で行われ、一部は実際にレシピエントに対する「最後の手段」として実施されてきた。
しかし、肺移植は解剖学的・生理学的な複雑さから、異種間移植の実現が最も困難な分野の一つとされてきた。
英国・ニューカッスル大学呼吸器移植医学科のアンドリュー・フィッシャー教授はガーディアン紙に対し、「呼吸の瞬間ごとに外部環境を体内に取り込んでいる。これは肺が汚染や感染、その他の脅威にいかに迅速に対応しなければならないかを意味する」と述べ、「そのため、肺の免疫システムは非常に敏感で活発だ。臓器移植手術はさらなる難題を突きつける」と説明した。
研究チームは、6種類の遺伝子改変を加えた中国産「バーマ香豚」の左肺を、39歳の男性脳死者に移植した。その結果、移植された肺は216時間、つまり9日間生存し機能を維持した。同時に、レシピエントの体内で急速かつ激しい免疫反応である超急性拒絶反応を引き起こすこともなく、感染の兆候も見られなかった。
ただし、移植24時間後に肺に体液が蓄積し、損傷の兆候が現れた。これは移植過程で生じた炎症が原因である可能性がある。オックスフォード大学のピーター・フレンド教授は、「脳死自体が急性炎症状態を引き起こすため結果の解釈は複雑だ。一部の結果は脳死状態に起因する可能性もある」と指摘した。
また、手術3日目と6日目には、レシピエントの抗体が豚の肺を攻撃する免疫反応が観察された。9日目には損傷が一部回復する兆しが見られた。フィッシャー教授は、「人間のレシピエントに残っていた自身の肺が移植された豚の肺を補完していた可能性があるため、損傷の程度が過小評価されている可能性がある」と説明した。
今回の研究は、異種間移植を肺にも適用できる可能性を示した画期的な事例だが、実際のレシピエント治療に応用するには、さらなる動物実験や事前研究が必要とされる。
研究チームは、「免疫抑制療法の最適化、遺伝子改変の改良、肺保存戦略の強化、そして急性期を超えた長期的な移植臓器機能の評価など、継続的な取り組みが必要だ」と結論づけている。









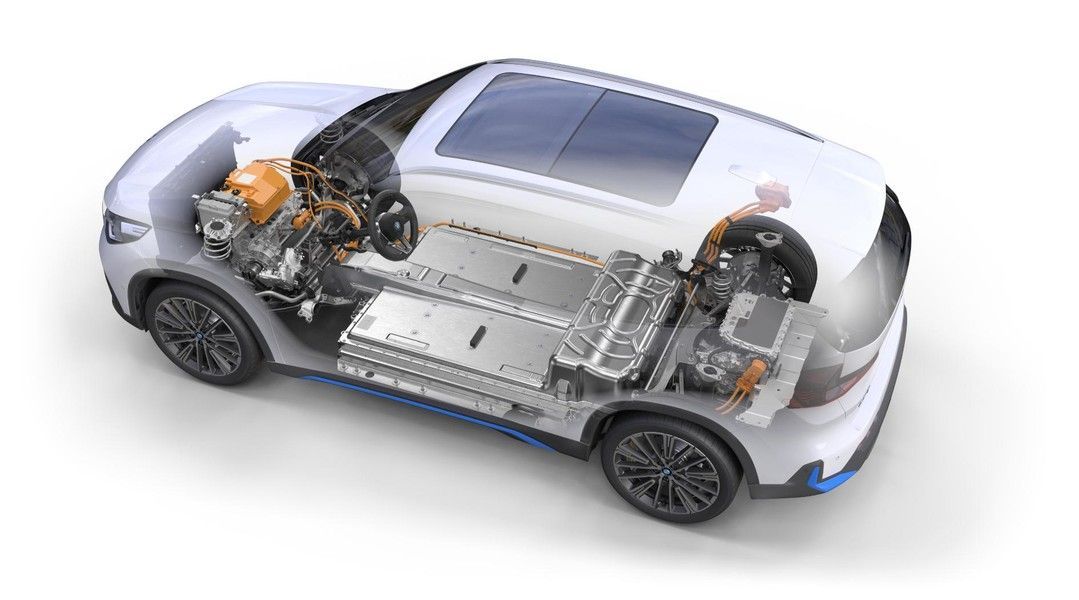



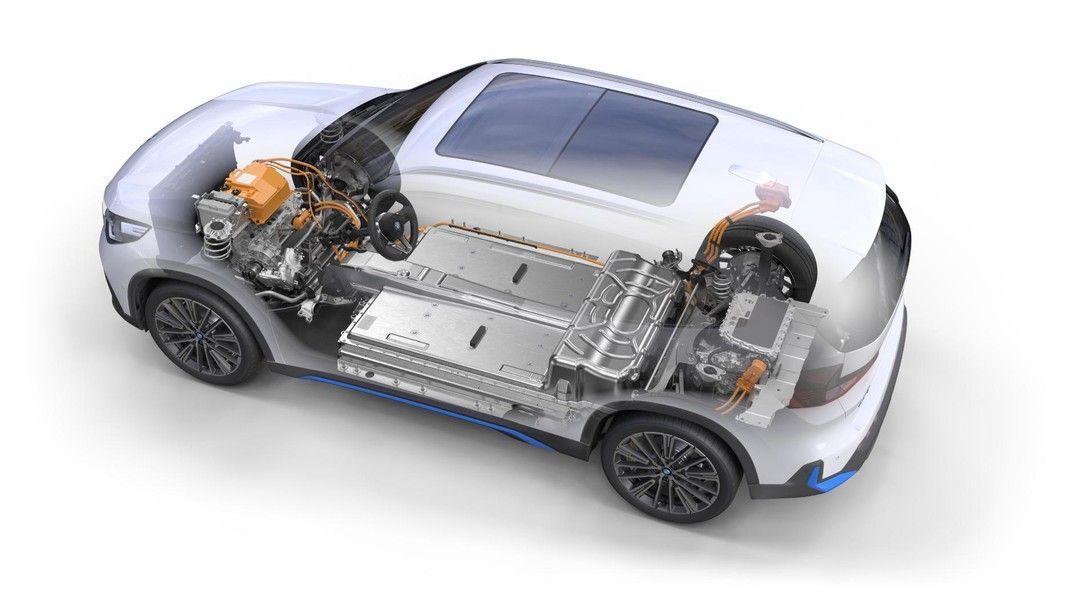







コメント0