4万年前の「冷凍マンモス」のRNAを分析したところ…死ぬ前に「ストレス」を受けていた
筋肉からRNA分子を検出することに成功
代謝調節に関与するRNAを確認
氷河期ウイルス研究への期待高まる

科学者たちは、これまでに発見されたリボ核酸(RNA)の中で最も古いRNAを分析した初の研究成果を発表した。氷河期に生息していた絶滅動物「マンモス」から分離したRNAの塩基配列を解読することに成功したのだ。RNAは、生命活動の基本であるタンパク質合成の際にDNAの遺伝情報を伝達する役割を持つ。今回、RNAが長期間保存され得ることが確認されたことで、絶滅種の遺伝情報や進化を解き明かす研究に転換点がもたらされると期待されている。
スウェーデン・ストックホルム大学の博士研究員、エミリオ・マルモル氏(現・デンマーク グローブ研究所研究員)らの研究チームは、シベリアの永久凍土層に4万年間保存されていたマンモスの組織からRNAを採取し分析した研究結果を14日、国際学術誌『Cell』に発表した。
絶滅動物から遺伝情報を採取して分析することは、絶滅種や進化に対する人類の理解を深める上で重要だ。特にRNAを調べることで、当時どの遺伝子が発現していたかについての直接的な証拠を得ることができる。これはDNAだけでは得られない情報である。
DNAは遺伝情報を含んでいるが、どの遺伝子が発現していたかについての情報は含んでいない。遺伝子が発現するということは、遺伝情報に基づいてタンパク質が合成されることを意味する。DNAの遺伝情報がRNAにコピーされる転写が行われた後、タンパク質合成が行われる。したがって、DNAが「タンパク質の設計図」であれば、RNAは「設計図のコピー」と見なせる。RNAにDNAの塩基配列が転写された状態ということは、タンパク質が作られるための機構が正常に稼働していることを意味する。マンモスのRNA塩基配列は、当時実際に発現した遺伝情報の直接的な証拠といえる。
研究チームは、「ユカ」という名前を持つ4万年前に死んだ幼いマンモスの凍結筋肉サンプルからRNA分子を検出することに成功した。検出されたRNAの塩基配列を調べた結果、ストレスを受けた際に起こる筋収縮や代謝調節に重要な機能を持つタンパク質が合成されるようにするRNAであることが確認された。研究チームは、ユカが死ぬ直前にライオンの攻撃を受けるストレス状況に置かれていた可能性があると推定している。
研究チームは、ユカの筋肉サンプルから遺伝子の活動を調節するマイクロRNA分子も発見した。マイクロRNAはタンパク質合成に関与するRNAではなく、細胞内で遺伝子発現を調節するRNAである。マイクロRNAの存在は、マンモスが生きていた当時にも生物の遺伝子発現調節が行われていたことを示す直接的な証拠だ。研究チームは、マイクロRNAからマンモスの起源を証明できる希少な突然変異も発見した。
今回の研究は、絶滅した生物からRNAを発見したという意義もある。RNA分子が長期間保存され得ることが確認されたためだ。研究チームは、氷河期に保存されているインフルエンザやコロナウイルスのようなRNAウイルスの塩基配列も今後分析できるようになるだろうという期待感を示した。
研究チームは「古代RNA、DNA、タンパク質、その他の保存された生体分子を組み合わせる研究を行えることを期待している」とし、「絶滅した種に対する我々の理解を根本的に再編成すれば、生物についてこれまで明らかにされていなかった隠れた層が明らかになるだろう」と述べた。




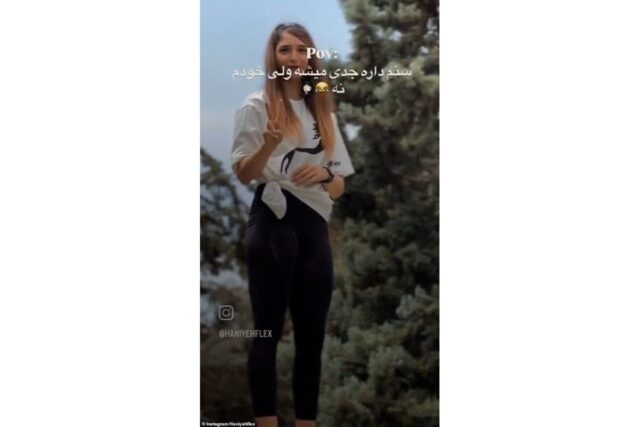
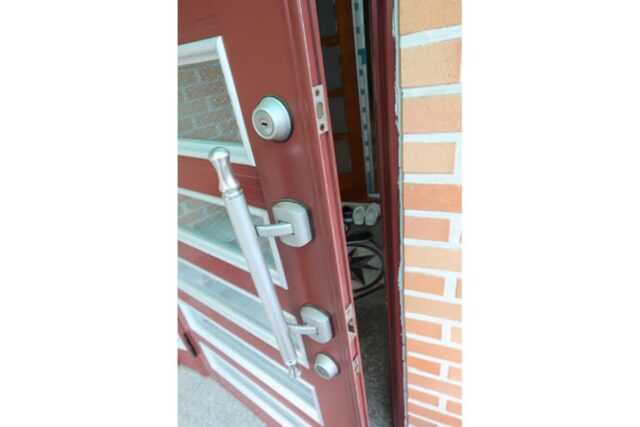

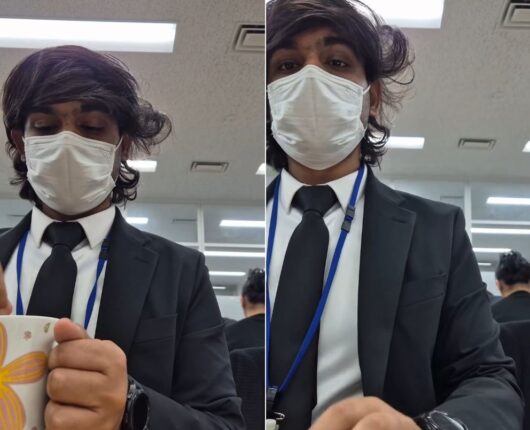













コメント0