衛星の急増に伴い、1,200基が大気圏再突入
宇宙ごみも急増…衝突リスク上昇

任務終了後も運用軌道に留まる衛星は、破片に分解され数年間軌道にそのまま残る可能性がある。衛星を軌道に打ち上げたロケットの一部も同様に軌道に残る。これらの宇宙物体は、他の衛星や宇宙船と衝突する危険性がある。また、重力の影響で徐々に高度が下がり、地球に落下するリスクもある。
欧州宇宙機関(ESA)が最近発表した宇宙環境報告書によると、完全な形の衛星やロケット本体が毎日3基以上地球の大気圏に再突入しているという。ESAは、2017年から毎年、宇宙環境報告書を作成・発表している。
報告書によれば、2024年の1年間で約1,200基が地球の大気圏に再突入した。1日平均3基強、再突入していることになる。
報告書は、「打ち上げられる衛星の急増により、宇宙から戻ってくる物体の数は今後も増加し続ける」と警告している。これは、最終的に地球大気の健全性と地上の人間の安全に対する懸念となりうる。現在、地球軌道上で活動中の衛星は1万1,000基、10cm以上の宇宙ごみは5万個を超える。その重量は1万4,000トンに達する。
このうち、米国や欧州などの宇宙監視ネットワーク(Space Surveillance Networks)が追跡しているのは約4万個だ。昨年だけでも、衝突や爆発などにより3,000個以上の宇宙破片が新たに発生した。
ESAは、レーダーや望遠鏡で追跡可能な10cm以上の物体に加え、1~10cmの破片が120万個、1cm未満の破片が1億4,000万個以上存在すると推定している。
米国の天体物理学者ジョナサン・マクダウェル氏は先月4日、スペースドットコムのインタビューで「今日だけでも3つの物体が宇宙から戻ってきた」と述べた。彼が言及した3つの物体は、スペースXのインターネット衛星群スターリンク2基と、43年前に打ち上げられたロシアの偵察衛星「コスモス1340(Cosmos 1340)」だ。マクダウェル氏によれば、現在、地球に落下してくる物体の大半はスターリンク衛星だという。
スペースXは、今後スターリンク衛星の数を数万基増やす計画だ。マクダウェル氏は、「そうなれば、地球の大気圏に落下する宇宙物体の数が1日15個にまで増加する可能性がある」と予想した。さらに、アマゾンのカイパー衛星や中国の衛星群など、スターリンクと競合する衛星の打ち上げも控えられている。

大気圏再突入時にオゾン層破壊物質を排出
衛星運用会社は、概ね5年ごとに衛星を新型に交換し、旧型は任務終了後5年以内に地球大気圏に再突入させて焼却処分する。
しかし、この過程で有害物質が発生する。衛星本体の主要素材は、アルミニウムだ。アルミニウムが高温の摩擦熱に晒されると酸化アルミニウムが生成される。
酸化アルミニウムは、オゾン層の破壊を加速させる。ロンドン大学のエロイーズ・マレ教授(大気化学)は「酸化アルミニウムをはじめとする金属酸化物や気体状の窒素酸化物など、オゾン破壊および汚染物質がかつてないほど多く追加されている」と警告している。
大半の宇宙ごみは大気との摩擦熱で燃え尽きるが、一部が生き残って地上に落下すれば、財産や人命に被害を及ぼす可能性がある。例えば、2月にはスペースXのファルコン9ロケットの破片がポーランドとウクライナの一部地域に落下した。また3月には、長さ10cmの正体不明の金属破片がフロリダの民家の屋根を貫通した。後にこの物体は、3年前に国際宇宙ステーションから廃棄されたバッテリーの残骸であると判明した。
もちろん、地球表面の70%は海洋であるため、人が負傷するリスクは極めて低い。しかし、マクダウェル博士は、現在人類が直面している宇宙ごみの脅威について「サイコロを振るようなもの」と表現し、「結局、運が悪ければ誰かが怪我をするだろう」と警告している。

衝突リスクで一部の軌道が使用不能に
軌道に配置される衛星が増加の一途をたどる中、宇宙ごみも必然的に増え続ける。報告書によれば、すでに低軌道(LEO)の一部領域では、運用中の衛星数が宇宙ごみの数に迫っているという。報告書は、積極的な除去対策が講じられなければ、一部の軌道は今後利用できなくなる可能性があると警告している。
いわゆる「ケスラーシンドローム」の発生も懸念される。ケスラーシンドロームとは、人工衛星や宇宙破片の密度が臨界値を超えた場合、これらの間で連鎖的な衝突が発生し、宇宙ごみが爆発的に増加。その結果、地球軌道全体が宇宙ごみで覆われ、宇宙活動が事実上不可能になる状況を指す。
宇宙ごみの移動速度は時速2万7,000kmにも達するため、1cm程度の物体でも衝突すれば衛星システムを機能不全に陥らせるなど、甚大な被害をもたらす可能性がある。2016年には、国際宇宙ステーション(ISS)の観測用モジュール「キューポラ(Cupola)」の窓に、直径わずか1,000分の数mmの極小破片が7mmもの穴を開けた事例がある。











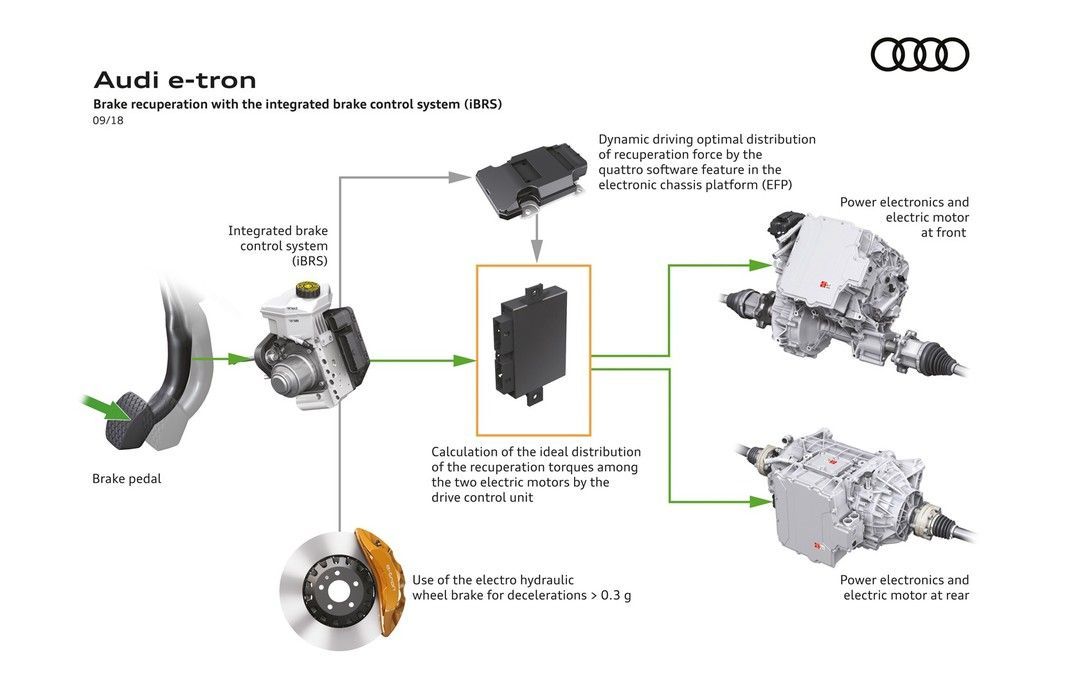









コメント0