アメリカ合衆国では、オンラインレビューを武器にして個人経営者から金銭を巻き上げる新たな詐欺が横行している。詐欺師たちはGoogleマップや総合レビュー・プラットフォーム「Yelp」、TripAdvisorなどに次々と偽の悪質なレビューを投稿し、削除の対価として金品を要求する。
14日(現地時間)時点で、関連業界およびアメリカ合衆国の規制当局、各プラットフォームによると、このようなレビューを利用した恐喝行為は全米に広がっている。アメリカの消費者関連民間機関ConsumerAffairsによれば、昨年6月、ロサンゼルス市の小規模内装業者の代表がメッセンジャーサービスWhatsAppで「貴社に1点の偽レビュー20件を投稿するようにという注文が入った」というメッセージを受信した。発信国番号はパキスタンであった。問い詰めると、「金銭を支払えばその注文を防止する」と要求が続いた。この業者は過去に、バングラデシュの番号を使う相手に150ドル(約2万円)を支払い、悪質なレビューを削除させられた経験があり、その経験を踏まえ、今回も100ドル(約1万5,000円)を送金した。しかし、数週間後、Googleマップには偽レビューが10件余り一斉に投稿され、5.0満点だった評価は3点台へと急落した。8年間かけて築き上げた名声が、たった一日で、一人の手によって崩壊した。金銭を一度渡すと、アカウントを変えて再び攻撃してくる、いわゆる『レビューテロ』の典型的な手口である。

このように、レビューを悪用した詐欺は全米に広がっている。詐欺師たちは、主に引越し業者、屋根修理、家電修理業者など、オンライン評価に依存する小規模事業者を狙っている。ConsumerAffairsによれば、彼らは単に「サービスが悪かった」という不明確な悪評を残すのではなく、「引越し業者の従業員が私の目の前でわざと箱を地面に投げ捨てた」といった精巧で悪意ある内容を盛り込み、そのレビューを読む消費者を混乱させる手法を取っている。
オーランドで引越し業を営むロバート・レジェスは、フロリダ地域放送WKMGのインタビューで「『完全な詐欺業者』や『予約時間より数時間も遅れた』といった偽レビューが十数件も続けざまに投稿された」と述べ、「このレビュー・テロが一体いつまで続くのか途方に暮れている」と語った。この引越し業者に悪評を残したGoogleアカウント、エズラ・マックス(Ezra Max)は、翌日、近隣の屋根工事業者にも『悪い会社』というレビューを投稿するなど、組織的な動きを見せていた。

専門家によれば、かつては偽レビューは人間が直接作成していたが、最近では人工知能(AI)が悪用されるようになった。偽レビュー監視団体「Fake Review Watch」によると、オンラインレビュー詐欺師たちは複数の偽アカウントでAIを駆使し、一斉に犯罪行為を行っているという。
レビュー関連プラットフォームが毎年削除する悪質なレビューの数を見るだけでも、「レビュー恐喝」が蔓延する仕組みの大きさが分かる。
Googleは昨年、ポリシー違反レビューを2億4000万件以上ブロック・削除したと公表。加えて、偽のビジネスプロファイル1200万件や、レビュー規定に繰り返し違反したアカウント90万件に対し制裁を加えた。TripAdvisorも昨年、『偽レビュー』270万件を摘出した。毎月ほぼ100万件近いレビューが投稿されるウェブサイトTrustpilotでは、約4ヶ月分にあたる450万件を削除した。それにもかかわらず、被害者たちは詐欺師が別のアカウントで再び悪質なレビューを投稿する悪循環が続いていると口を揃えている。

オンライン評判管理業者『Better Reputation』の代表ケリー・カリーチェックは、経営専門誌Entrepreneurのインタビューで「潜在消費者の90%以上が主要なサービスや製品購入前にレビューを確認することが分かった」と述べ、「悪いまたは凡庸なレビューだけでも潜在消費者を失う原因になる」と説明した。名誉毀損や脅迫などの法的問題については、「法的削除請求」の手続きが最も一般的とされ、専門家はまず対象プラットフォームに対し、そのプラットフォームが犯罪に悪用されていることを知らせる法的請求書を直接提出するよう助言している。
最近では、国家レベルで悪質なレビューに対する歯止め措置が加速している。連邦取引委員会(FTC)は昨年10月、『消費者レビュー・推薦規則』を確定・施行し、金銭取引により売買される偽レビュー、AI生成の虚偽レビュー、実体験のないレビュー等を禁止した。この規定に故意に違反した場合、1件あたり最大5万ドル(約700万円)の罰金が科される可能性がある。
英国では、競争・市場庁(CMA)の調査を受けて、Googleが偽レビューに「疑わしい」と表示するバッジを付与し、該当アカウントの新規レビューを制限する措置を導入・拡大すると約束した。














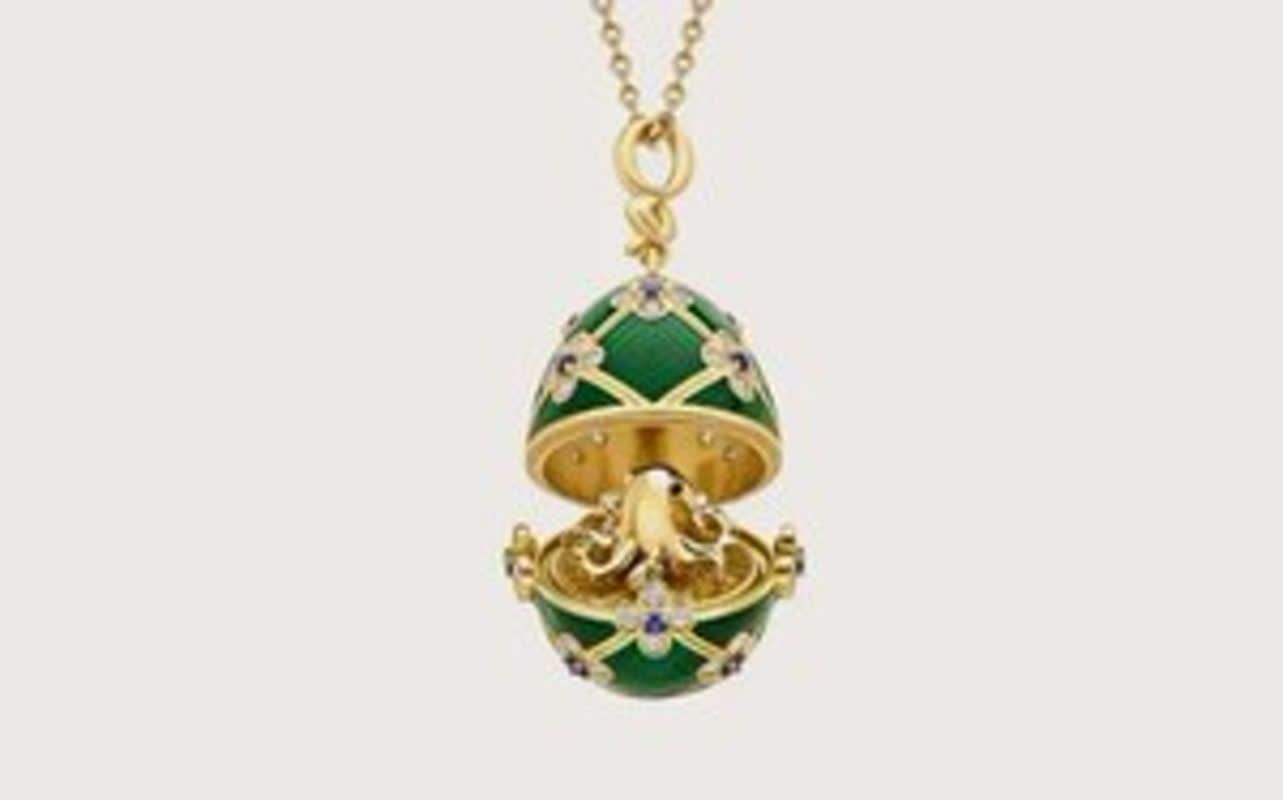





コメント0