
4万年前に絶滅した現生人類のいとこであるネアンデルタール人が、腐肉とウジ虫を食料としていた可能性が浮上し、数十年にわたり人類学界を悩ませてきた骨にある窒素成分の謎を解明する新たな仮説として「ウジ虫食」が注目を集めている。
ニューシスの報道によれば、現地時間27日、CNNやザ・サンなどの海外メディアは、米パデュー大学人類学科のメラニー・ビズリー教授率いる研究チームが、最近、学術誌『サイエンス・アドバンシズ(Science Advances)』に発表した論文において、ネアンデルタール人の食生活において、ハエの幼虫であるウジ虫が重要な役割を果たしていた可能性を示したと伝えられた。
これまで、ネアンデルタール人の骨からは、ライオンやオオカミなどの頂点捕食者に匹敵するレベルの窒素-15同位体(δ¹⁵N)が検出され、極端な肉食中心の食生活を送っていたという仮説が長年有力視されてきた。
しかし、過剰なタンパク質摂取は「ウサギ飢餓(rabbit starvation)」と呼ばれるタンパク質中毒を引き起こし、重症の場合には死に至る可能性があるため、一部の研究者はネアンデルタール人の食生活についてさまざまな解釈を展開してきた。
今回の研究では、腐敗した肉とそこから湧き出るウジ虫に着目。ビズリー教授は「ネアンデルタール人の窒素-15値を上昇させた別の要因として、脂肪とタンパク質が豊富なウジ虫の可能性を仮定し、これを実験で検証した」と説明した。
研究チームは、死後間もない人体組織とそこに発生したウジ虫を採取し、腐敗の進行とともに窒素-15の値がどのように変化するかを詳細に追跡した。その結果、筋肉組織が腐敗する際に窒素-15値が -0/6 から7.7‰(パーミル)まで上昇し、この組織を摂取して成長したウジ虫の窒素値はさらに高くなった。
研究チームは「高窒素ウジ虫を摂取した場合、ネアンデルタール人の骨から検出された高い窒素-15値が部分的に説明できる」と述べ、「ネアンデルタール人は単に生肉を食していただけでなく、発酵、乾燥、保存、調理など、複雑な食文化や保存技術を用いて多様な方法で肉を摂取していた可能性がある」と指摘した。
ビズリー教授は「今回の研究だけではネアンデルタール人の“ライオン級”の窒素濃度すべてを説明することはできない」としながらも、「先住民の伝統的な食文化や保存・調理技術を手がかりに、古代人類の実際の食生活をさらに正確に再現できる可能性がある」と語った。




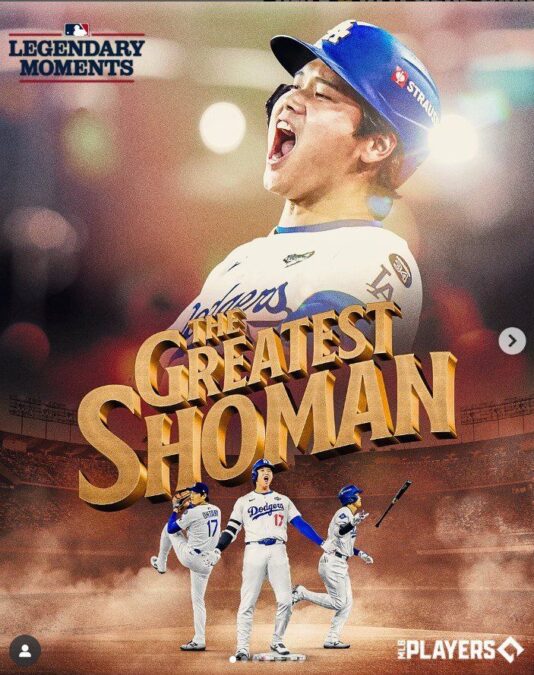
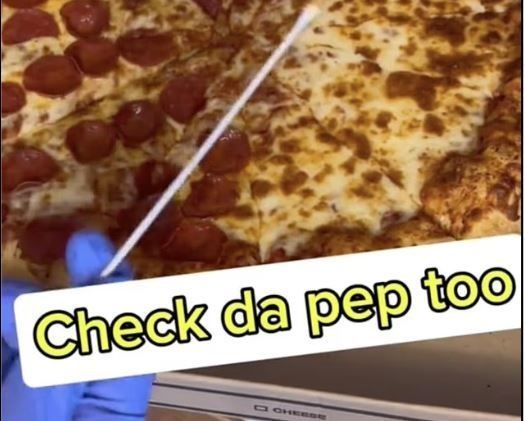

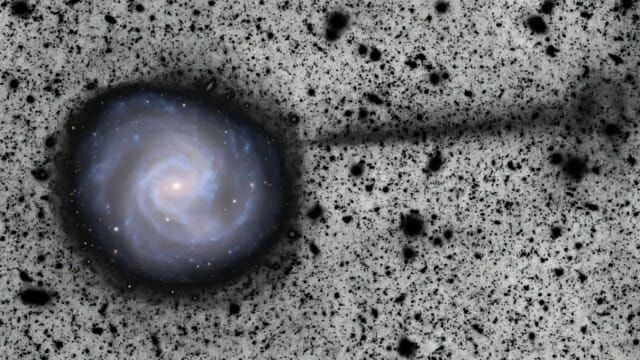







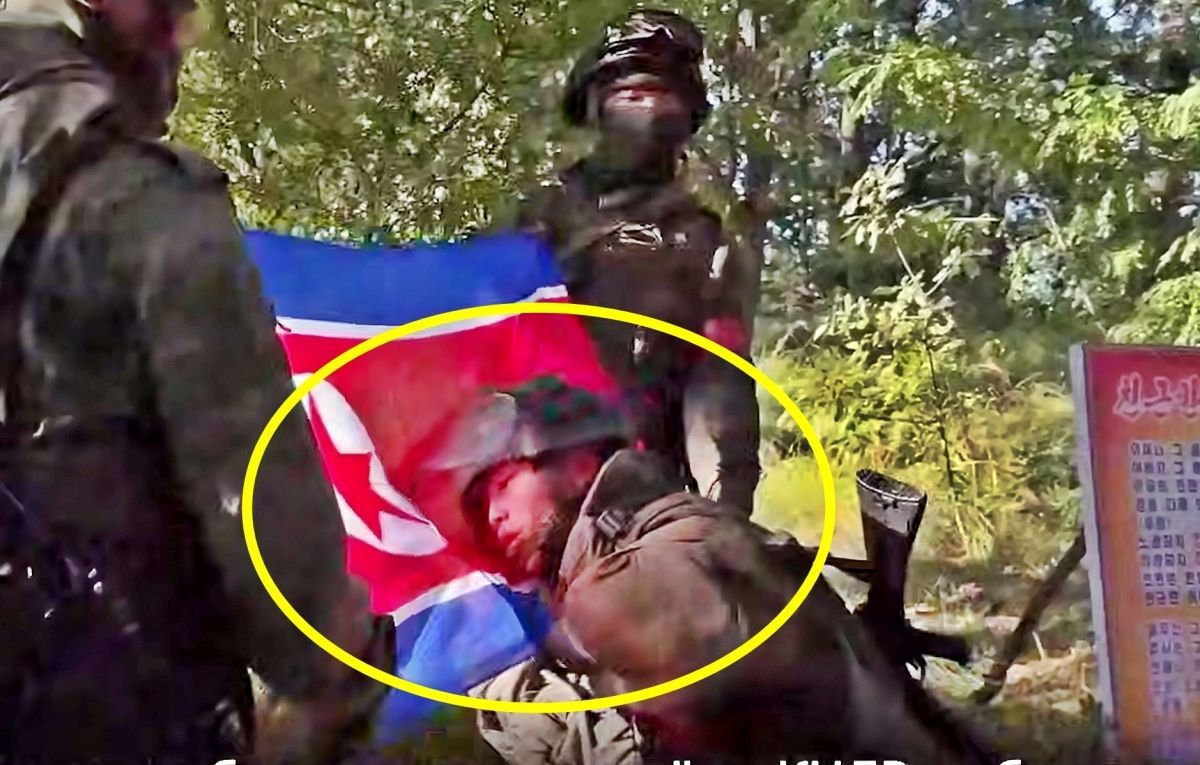






コメント0