
ドナルド・トランプ米大統領が課した相互関税率の解釈をめぐり、日本でも既に議論となったが、台湾でも論争が拡大している。台湾に適用された20%の相互関税が今月7日に発効したが、実際の課税方式が「20%の一律税率」ではなく、既存の関税に20%を上乗せする仕組みであることが後になって判明したためだ。
11日の台湾メディア『聯合報』によると、台湾行政院経済貿易交渉弁公室(OTN)は8日午後、「台湾の相互関税は既存の最恵国待遇税率に20%を加算したものだ」と説明。「工作機械類の場合、既存の4.7%に20%を上乗せし、合計24.7%に達する」としている。
経済部国際貿易局やOTNは、こうした計算方式をすでに4月から公表していたと主張しているが、野党や与党の一部議員は政府の対外説明が不十分だったと批判。第2野党・民衆党のフアン・グォチャン主席は政府発表を「極めて不透明」と指摘し、第1野党・国民党議員らも「国民に正確な情報を提供していない」と追及した。与党・民進党の一部議員も「国民が求めているのは事前発表の有無ではなく正確な現状だ」と述べ、「対外広報の危機」と強く批判した。
台湾産業界では、今回の税率引き上げにより基幹産業製品の生産コストが日本や韓国に比べて10%以上高くなるとの懸念が広がっている。その結果、価格競争力が低下し、日本、韓国、シンガポールなど競合国への受注移転や失業率の上昇など、悪影響が避けられないとの見方も出ている。ある専門家は「今回の関税賦課により、台湾と日本の農工業分野の関税格差は15〜27%に広がり、台湾の価格競争は事実上困難になった」とし、「米国の政策により『脱台湾化』の懸念が高まっている」と分析した。
こうした中、台湾立法院外交国防委員会は14日、外交部長(外相)や関連部処の次長(次官)、行政院OTNの副総交渉代表らを招致し、米台相互関税や国際情勢の変化による影響について報告を受ける予定だ。
日本では既に米国と15%の相互関税で合意していたが、米側が課す「15%関税」が一律税率ではなく、既存関税に上乗せする方式であることが後に判明し、国内でも物議を醸していた。















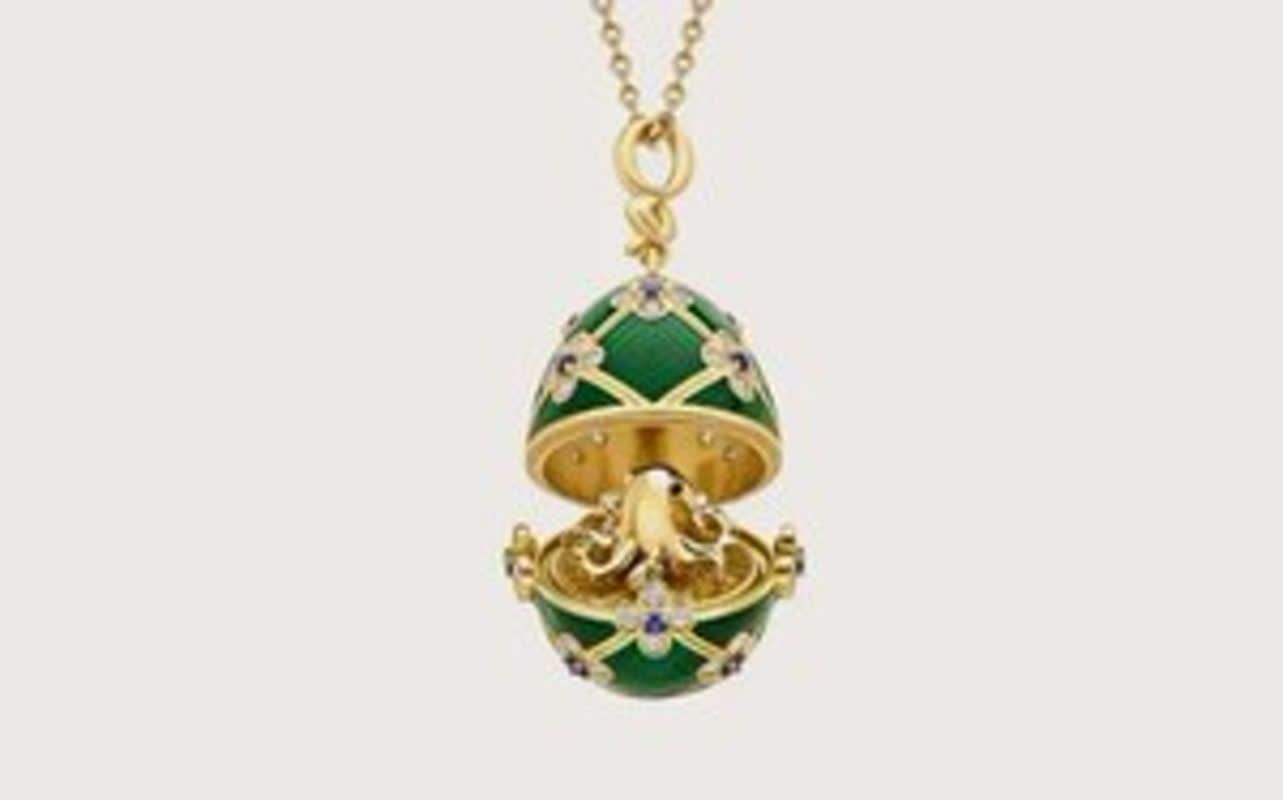






コメント0