
「ニコル」(二宮和也)は出勤途中の電話で思いがけない知らせを聞く。すでに別れた元恋人から妊娠を告げられたのだ。衝撃を受けた彼は慌てて携帯電話を落とし、返答を避ける。
しかし直後に元恋人の声は途切れ、外部とのあらゆる連絡が断たれた地下通路に自分が閉じ込められていることに気づく。どれだけ歩いても繰り返される地下道。彼は果たしてこの場所から脱出できるのか。

10月22日に公開される映画『8番出口』(川村元気監督)は、無限ループの地下通路に囚われた男が出口を探してさまよう物語だ。2023年にリリースされ、全世界累計ダウンロード数190万回(2025年9月時点)を記録した同名の一人称3Dウォーキングシミュレーションゲームを原作としている。本作は第78回カンヌ国際映画祭ミッドナイト・スクリーニング部門にも正式招待された。
物語はシンプルだ。ゲームのルールをそのまま踏襲している。「異常現象を見つけたら引き返し、なければ前へ進め」という単純な規則が緊張感のすべてを生み出す。この規則を正しく守れば0番から1番、そして2番へと進み、やがて8番出口にたどり着ける。しかし一度でも規則を破れば元の地点に戻される。単純な構造の中で常に潜む失敗の可能性が、不安と緊迫感を増幅させる。
脱出のために必ず見つけなければならない「異常現象」は「変則」として現れる。それは物の形であったり、人の姿として現れたりする。そこには象徴性や主題意識も内包されている。それを見過ごした主人公は、再び原点に戻されて初めて「異常現象」であったことを悟る。観客もまた、主人公とともに「異常現象」を探し当てようと能動的な感覚を呼び覚まされ、自らもゲームのプレイヤーとなるのだ。

『8番出口』の恐怖はリミナル・スペース(現実と非現実の境界が曖昧になった空間)から生じる。白い四角いタイルに覆われた過剰に整然とした廊下、均一な照明、方向感覚を失わせる通路は、時間が経つにつれ恐怖を増大させる。それはまるで地下道の壁に掛けられたエッシャーの「メビウスの帯」そのものだ。観客も方向感覚を失い、やがていくら歩いても抜け出せない無力感に囚われる。
映画は視覚・聴覚を総動員する体験型ホラーの醍醐味も見せる。「異常現象」を探す視覚的探索、モーリス・ラヴェルの『ボレロ』が繰り返し流れるサウンドによるスリル、予測不能な展開が恐怖と不安、希望と絶望を交錯させる。特にScreenX上映では三方向に広がる映像が「空間的恐怖」を極大化させる。通常の2D上映であっても家庭視聴には向かない。『8番出口』は劇場スクリーンでのみ完成する体験型映画だからだ。

キャスティングも原作との高いシンクロ率を誇る。ゲームに登場する「歩く男」を実写化した俳優・越智大和は、一言も発さずただ歩くだけで圧倒的な存在感を放つ。無表情な顔、均一な歩幅、繰り返される足取りは時間が経つにつれて恐怖の重みを増していく。
『8番出口』は恐怖の対象を実体化したり直接見せたりしない。抜け出したいのに決して抜けられない空間で、まるで「現代人の無限ループ」や「選択の連続である人生の循環」を描いているかのようだ。出口に近づいたと思えば、決して到達できない。その瞬間、映画は日常と異常現象が交錯する現代的恐怖の本質を浮かび上がらせる。上映時間95分。
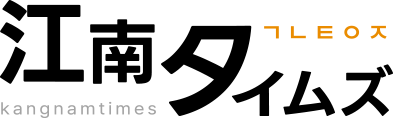





















コメント0