10年間の追跡研究、スマートフォンが子どもの脳発達に与える衝撃的な影響
東北大学の研究チームが10年に及ぶ調査を通じ、スマートフォン使用が子どもの学習能力を低下させ、脳発達を遅らせる可能性があるという衝撃的な結果を発表した。
川島隆太教授率いる研究チームは、2010年から宮城県仙台市の7万人の小中学生を対象に生活習慣と学習能力を調査した。特に3年ごとにMRI脳検査を実施し、スマートフォン使用が脳に及ぼす影響を詳細に分析した。
研究の結果、スクリーン使用時間(テレビ視聴、スマートフォンおよびゲーム機使用を含む)が1日1時間を超えると、子どもの学習能力が急激に低下することが判明した。使用時間が長くなるほど、全科目で学習能力が著しく低下した。研究チームは「スマートフォンが論理的思考力、記憶力、集中力、読解力など全般的な学習能力に影響を与えると推測される」と述べた。

スマートフォン使用と脳発達遅延の衝撃的な相関関係
研究チームは当初、成績低下の原因が学習時間や睡眠時間の減少にあると仮定していた。しかし、後続研究でスマートフォンの使用自体が学習に悪影響を及ぼすことが明らかになった。
驚くべきことに、1日2時間以上勉強しても、スマートフォン使用時間が3時間を超えると、勉強もせずスマートフォンも使用しない子どもたちより成績が低いという傾向が見られた。
MRI検査結果はさらに衝撃的だった。インターネットの使用時間が長いほど、3年前と比較して脳の状態変化が少なかったのだ。これは、脳発達が複数の領域で停滞していることを意味し、具体的には大脳皮質の3分の1が発達を停止し、脳の各領域を結ぶ神経網である白質全体でも発達停滞現象が確認された。
研究チームは、長時間のスマートフォン使用による学習能力低下の根本原因が子どもの脳発達の問題にあると結論づけた。
川島教授は「スクリーン使用時間を1日1時間以内に制限すれば、子どもの学習能力に明確な影響はないが、1時間を超えるとどのような場合でも学習能力が大幅に低下する」と強調した。
また、「保護者と学校が子どものスマートフォン使用に具体的かつ明確な制限を設ける必要があり、大人の模範が重要だ」と訴えた。
今回の研究は、デジタル機器が子どもの発達に与える長期的影響に関する重要な科学的証拠を提供し、スマートフォン使用に関する適切なガイドライン策定の必要性を浮き彫りにしている。
専門家らは、子どもの健全な脳発達のため、スクリーン時間の制限とともに、さまざまな身体活動、読書、対面でのコミュニケーションなど、バランスの取れた活動を推奨している。







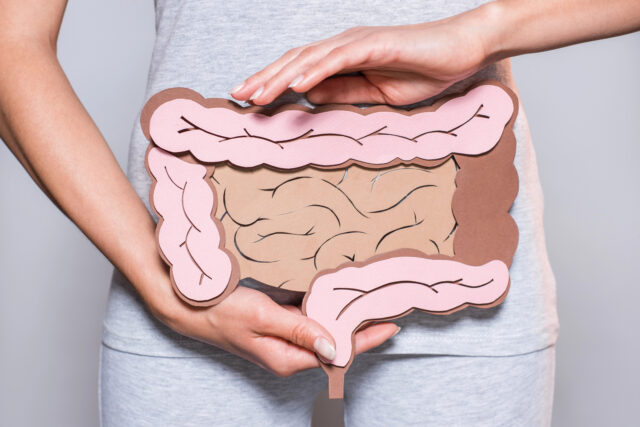













コメント0