抗生物質・ワクチンが効かない理由…細菌の「記憶」が原因
ヘブライ大研究チーム、細菌の記憶を解明する新技術を開発

細菌は、一般的に単純でランダムに動く微生物と考えられてきた。しかし最近の研究で、細菌も過去の経験を記憶し、その記憶を何世代にもわたって子孫に伝えることが明らかになった。これは、抗生物質やワクチンが効果を発揮しない理由を説明する鍵となる可能性がある。
イスラエル・エルサレムのヘブライ大学の研究チームは、新技術を用いて細菌の隠れた行動パターンを解析した研究成果を27日、国際学術誌『セル(Cell)』に発表した。
研究チームは、単一の細菌が増殖して形成した微小コロニーを個別に分離し、RNA、遺伝子、細胞特性を分析する新技術を開発した。この技術により、細菌間の違いが単なる遺伝的変異によるものか、遺伝子自体は変化せずに発現パターンが変わる「エピジェネティックな記憶」によるものかを区別できるようになった。
実験の結果、大腸菌や黄色ブドウ球菌などの病原菌は、単一の感染内でも複数の下位集団に分かれて存在していることが判明した。ある集団は、人体に効果的に付着するために病原性遺伝子を活性化し、別の集団は過酷な環境下で生存するための遺伝子を活性化していた。
このような環境に応じた記憶は、驚くべきことに20世代以上も持続した。例えば、抗生物質に曝露された細菌はその経験を子孫に伝え、子孫はより強力に抗生物質に耐える能力を獲得する。
ただし、細菌の記憶には限界がある。栄養が尽きて増殖が止まる定常期に入ると、細菌は記憶を失い、元の状態に戻ってしまう。状況に応じて戦略を切り替えているわけだ。
研究チームは、この発見が抗生物質やワクチンが時として効果を発揮しない理由を説明すると考えている。従来の診断法では、無作為に採取された1、2個の細菌集団のみを分析していた。しかし、実際の感染部位には異なる記憶を持つ複数の細菌集団が同時に存在しており、そのため、検査で検出されなかった他の集団が生き残れば、治療効果が得られにくくなる。
この新技術を実際の尿路感染症や血流感染症の患者に適用したところ、同一患者内でも抗生物質に強い耐性を持つ細菌とそうでない細菌が共存していることが確認された。
ヘブライ大学のナタリー・バラバン教授は「感染症は単一の細菌の塊ではなく、異なる戦略を持つ集団の集合体だ」と指摘し、「効果的な治療には、すべての集団を把握し、それぞれを狙い撃ちする必要がある」と強調した。







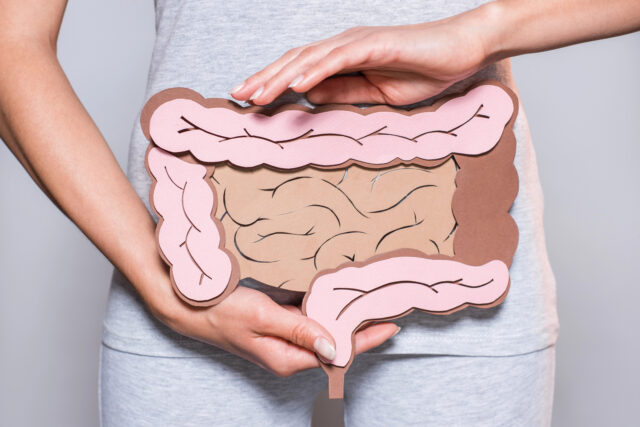




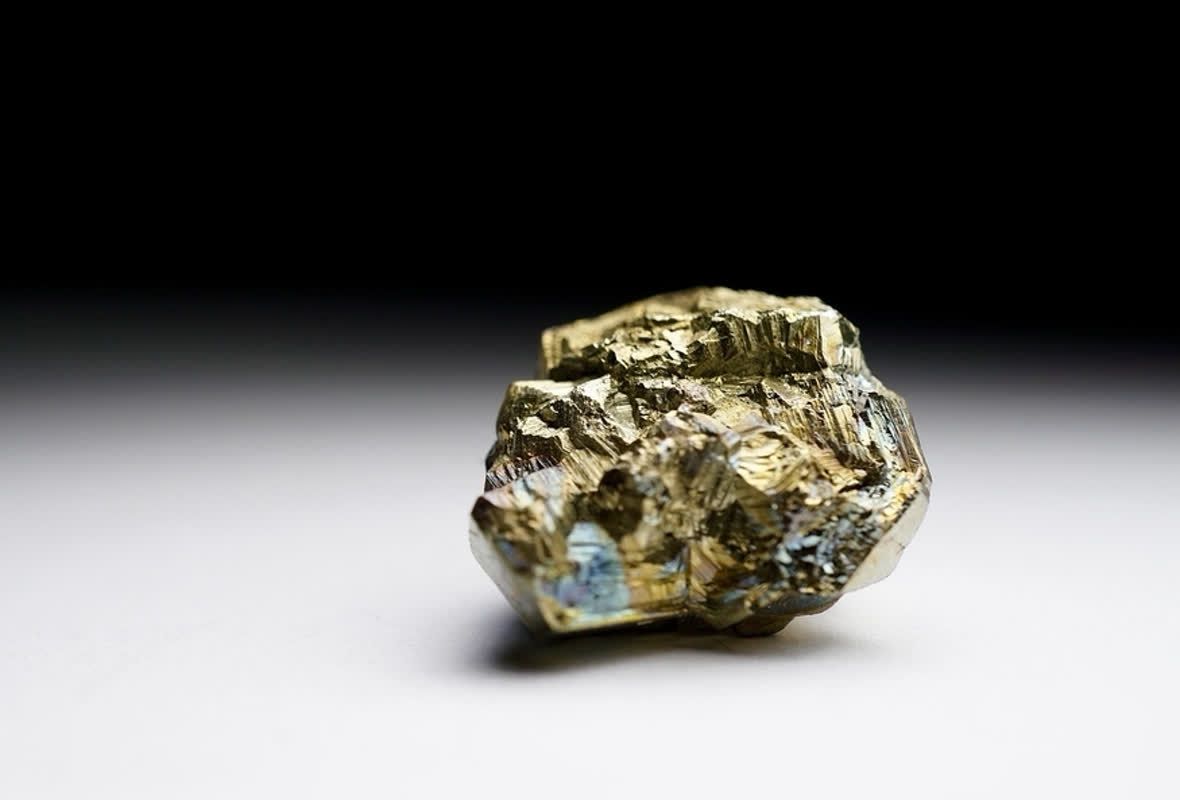


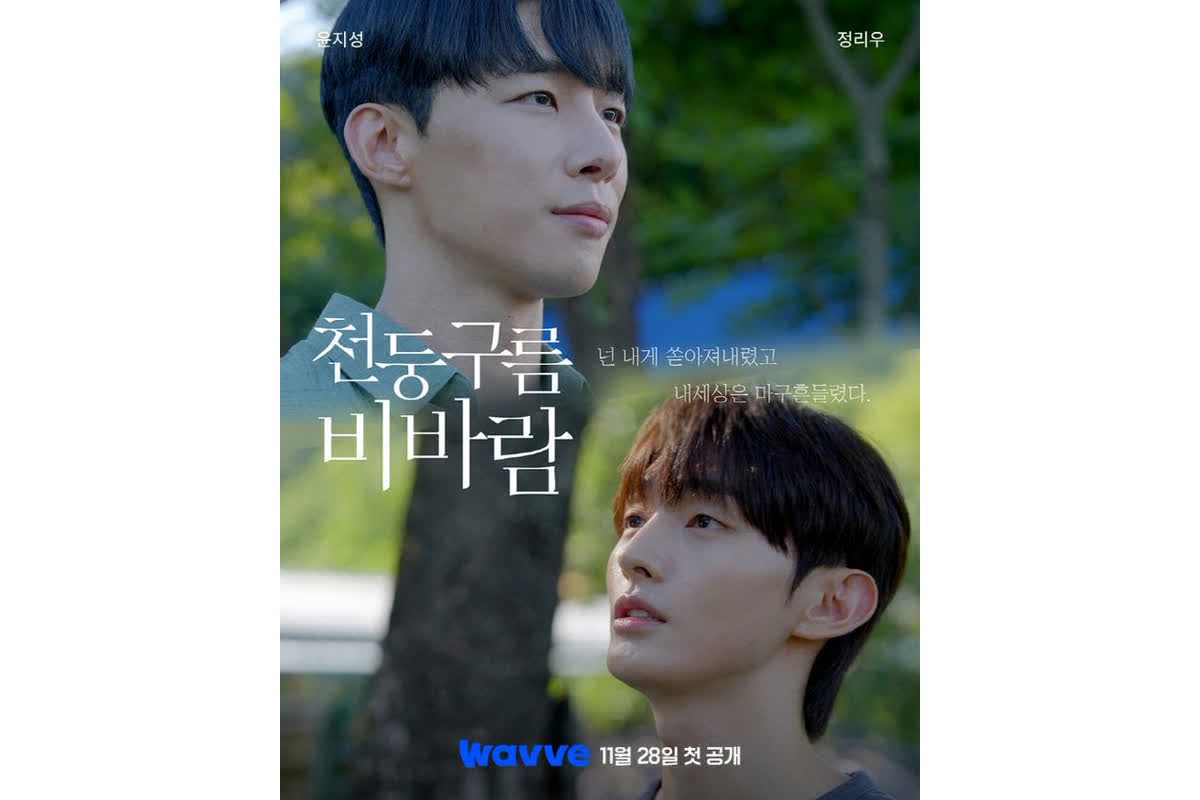






コメント0