
午前0時から日の出前までの周囲の明るさが増すほど、長期間にわたり心臓機能異常や脳血管疾患のリスクが高まる可能性があるという研究結果が発表された。
24日(現地時間)、フリンダース大学のダニエル・ウィンドレッド博士の研究チームは、アメリカ医師会傘下の学術誌『JAMAネットワークオープン』に掲載した論文で、UKバイオバンク登録者約8万8,900人を対象とした長期追跡調査の結果を公表した。
調査は約9年半にわたり実施された、夜間の照度レベルと心血管疾患発生率との統計的関連性が評価された。
分析の結果、午前0時以降に強い光に継続的に曝露された人ほど、心不全、心筋梗塞、脳卒中などの主な心血管疾患の発症率が有意に高かった。
研究チームは「心臓病予防ガイドラインに夜間の照明を最小限に抑える項目を追加する必要がある」と提言した。
夜間の光曝露は体内時計(サーカディアンリズム)を乱し、身体の回復や代謝過程に悪影響を及ぼす可能性があると知られている。しかし、夜間に曝露される光の明るさと心血管疾患リスクとの関係については、まだ明確には解明されていないと研究チームは指摘した。
参加者は手首に照度計を装着し、1週間にわたり午前0時30分〜午前6時まで平均光強度を記録した。その後、曝露レベルに応じて△0~50%(月明かりまたは暗室レベル、約0.6ルクス)△51~70%(薄明かり、約2.5ルクス)△71~90%(寝室の明かり程度、約16ルクス)△91~100%(テレビや携帯電話の光レベル、約105ルクス)の4区分に分け、NHSの医療記録と比較分析した。
その結果、最も明るい区分に属する人々は、最も暗いグループと比較して心不全リスクが約56%、心筋梗塞が47%、冠動脈疾患と心房細動がそれぞれ30%台、脳卒中が約28%高かった。
この傾向は喫煙、飲酒、運動量、食習慣、睡眠時間、社会経済的地位、遺伝的要因などを調整した後でも一貫して現れた。特に女性では、光曝露が多いほど心疾患の増加幅が男性よりも大きく、60歳以下では高齢者よりも心血管リスクの上昇幅が顕著だった。
研究チームは「個人の夜間光曝露を避けることが、健康的な食習慣や定期的な運動、禁煙・節酒と共に新たな心血管疾患予防戦略となる可能性がある」と述べた。












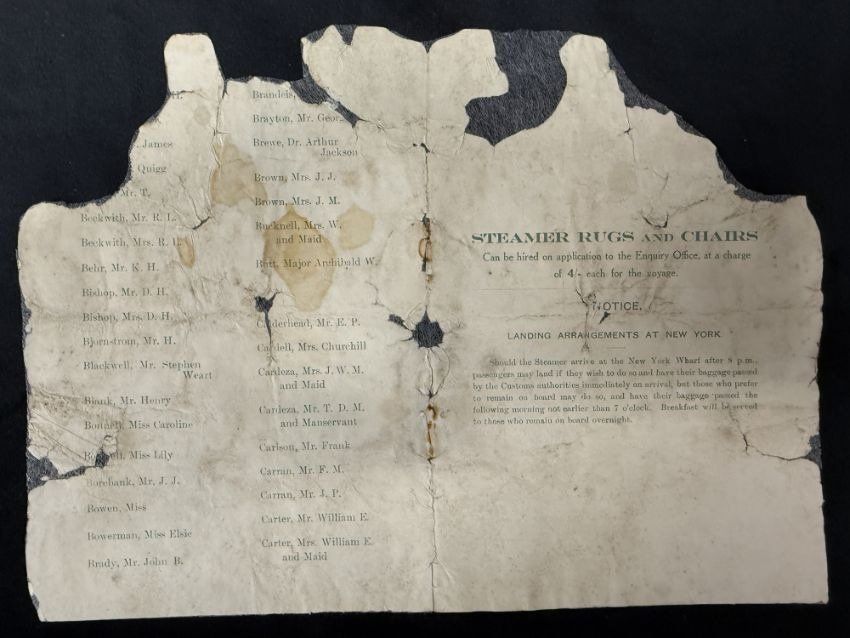

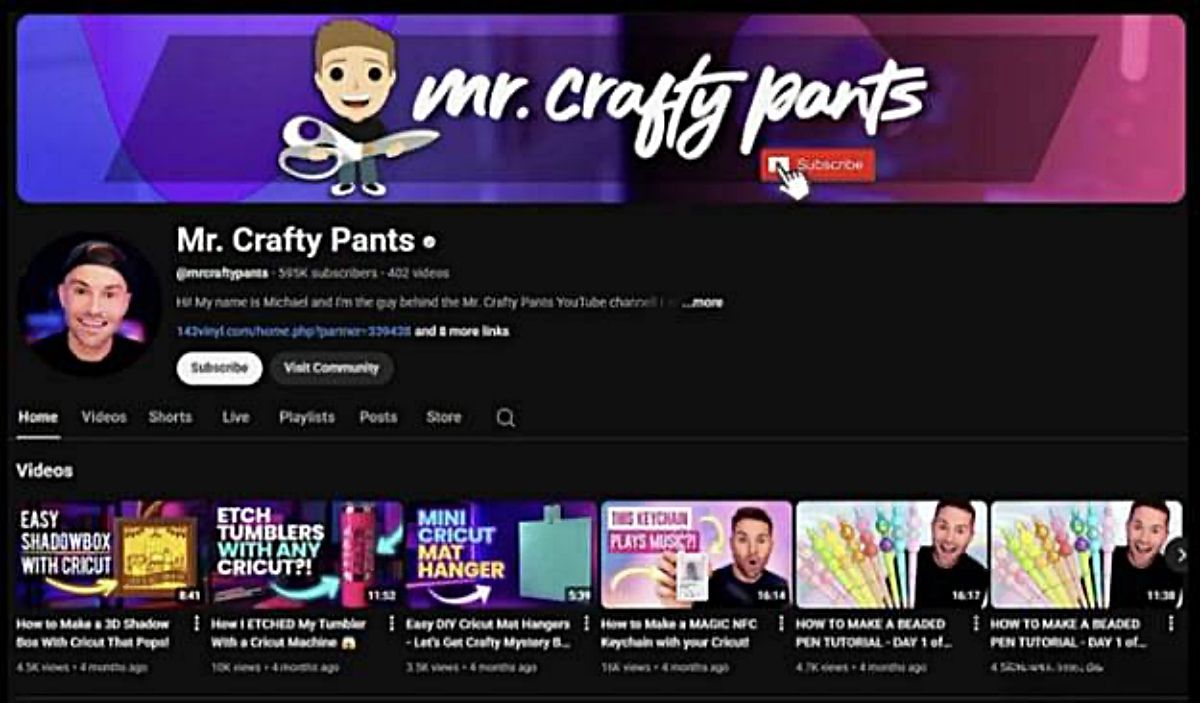






コメント0