今月1日より発効した米日関税合意により、日本の輸出企業は当面のコスト負担が軽減されたものの、中長期的な投資拡大には依然として慎重な姿勢を崩していない。米国が日本製自動車等に課す予定だった25%の関税が15%に引き下げられたが、投資報告義務や政治・安全保障分野での圧力が伴うため、不確実性は依然として大きいとの指摘がある。
3日、現地メディアなどによると、関税引き下げの恩恵を最も受ける業種とされる自動車業界は、今回の合意で輸出時のコスト負担が軽減されたことを一応評価している。しかし、日本の主要メディアは「15%の関税も決して低い水準ではない」という業界の反応を伝え、短期的な安堵感とは別に中長期的な投資拡大については慎重論が広がっていると報じた。
日本経済新聞(日経)は、米国内の電気自動車に対する税制優遇など政策の不確実性が残るとともに、通商政策が変化する可能性もあるため、企業は大規模な増設や投資決定に慎重を余儀なくされると分析した。実際、関税の引き下げ発表直後にトヨタ、日産など完成車メーカーの株価は一斉に上昇したものの、具体的な投資計画の発表はまだない。
半導体業界も関税引き下げによる直接的な影響は比較的限定的だが、今回の合意に含まれた四半期ごとの投資進捗報告やサプライチェーン関連の条件が新たな負担になる可能性があるとの見方が示されている。
日本政府はこれを民間の自主的投資だと強調しているが、米国側が四半期ごとの報告を求めている点から、企業は実質的に監視下に置かれているとの指摘がある。今回の合意構造が政治的リスクを経済界に転嫁する形になることへの懸念も大きい。

関税交渉が一段落した後、米国が安全保障分野で日本に対する防衛装備品購入の圧力を続ける可能性が指摘されている。ホワイトハウスは先月23日に発表した関税合意の声明で、日本が「毎年数十億ドル規模の防衛装備品を追加購入することになった」と明示した。これに対し、日本政府は「購入は既存の防衛力整備計画に沿って行われる」とし、拡大解釈を警戒している。
防衛省内では、中距離空対空ミサイル、迎撃ミサイル、ステルス戦闘機「F-35」などの追加購入が検討されている。これは既存計画に明記された目標数量を達成するための措置であり、ホワイトハウスが言及した購入規模と合致する可能性があるという。
石破茂首相は国会で「関税と防衛費の議論は切り離して取り扱うべきだ」と述べ、「両者を結び付けて議論すると問題の本質を見誤る」と強調した。しかし、米国のドナルド・トランプ大統領は関税交渉直前の4月16日、自身のSNSにおいて「日本は関税、軍事支援、貿易の公平性について交渉に来た」と投稿し、その後も米日間の防衛費負担の不均衡を繰り返し指摘していた。
現時点で米日間の正式な共同合意文は存在せず、両国間の認識の差も解消されないまま残っている。当初7月に予定されていた日米外務・防衛閣僚会合「2+2」は、関税交渉や参議院選挙の影響で延期された。今後、会合が再開される場合、より高額な防衛装備品購入の要請が続くと予想される。


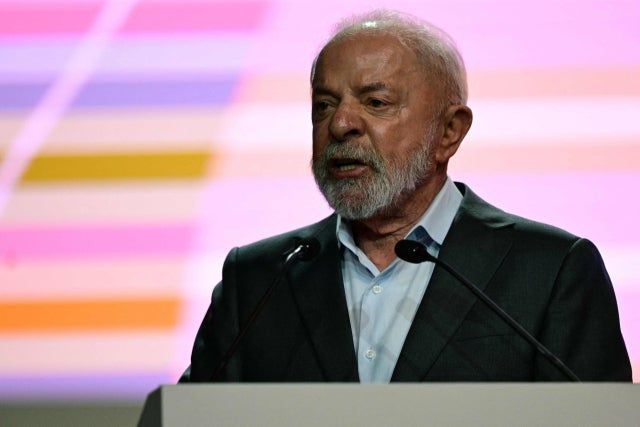
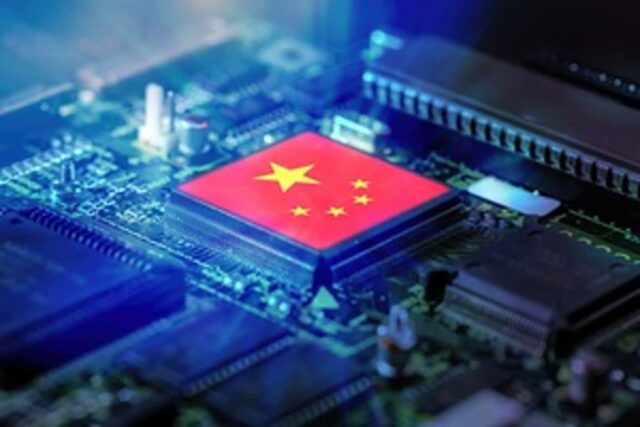


















コメント0