新興国が「資源戦争」の最前線に…米・EUが中国のレアアース覇権に対抗
世界第2位の埋蔵量を誇るベトナムに米中が相次いで接近

中国によるレアアース(希土類)覇権をめぐり、世界的な資源戦争が本格化するなか、豊富な天然資源を有する東南アジア諸国に各国の関心が集まっている。
アメリカをはじめ、欧州連合(EU)や主要7カ国(G7)などが、現地との連携を強化し、レアアースの採掘や精製に向けた動きを加速させており、ベトナムやミャンマーなどの開発途上国が、レアアース争奪戦の最前線となっている。
5日(現地時間)のサウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)の報道によると、アメリカは2023年、ベトナムと技術協力協定を締結し、レアアースの採掘や精製における連携を本格化させている。
ベトナムは、世界のレアアース埋蔵量の19%を占め、中国に次ぐ第2位の埋蔵国であり、すでにレアアースの採掘・精製・供給を国家主導で進めている中国も、昨年4月には中国稀土集団とベトナム石炭鉱物公社(ビナコミン)が共同声明を発表し、協力の可能性を模索している。
世界第3位のレアアース供給国であるミャンマーもまた、鉱物戦争の激戦地となっている。トランプ米政権は、世界最大級の重レアアース鉱山があるミャンマー北部カチン地域から、中国に輸出される資源を取り戻そうと動いてきた。
米政府は他にも、2023年にオーストラリアのレアアース企業ライナスに2億5,800万ドル(約380億1,563万円)を投資し、米テキサス州に生産拠点を設立。ライナスは今年5月、マレーシアで重レアアースであるジスプロシウムの酸化物を精製した。これは中国以外で初めて精製された重レアアースとなる。
また、アメリカは2022年、日本・韓国・インド・英国・オーストラリアなど14カ国と「鉱物安全保障パートナーシップ」を発足させ、コンゴ民主共和国やカザフスタン、ウクライナなども巻き込み、レアアースプロジェクトの開発と政策協議を進めている。
G7も昨年6月に重要鉱物に関する新たな行動計画を発表し、翌7月には供給網多様化を目指す「クアッド・イニシアティブ」を立ち上げた。
今年に入り、トランプ大統領が再び米政権を握った後、中国が鉱物資源を本格的に武器化し、世界各国のレアアース確保競争が激化している。中国は昨年4月に17種類のレアアースのうち7種類の重レアアースについて対米輸出を規制し、その影響により米国内では自動車工場の生産停止が相次いだ。これを受け、AI半導体の対中輸出を禁止していたアメリカも、一時的に姿勢を軟化させた。一定の成果を上げた中国は、レアアースの武器化をさらに加速させる構えを見せている。
こうした激化する国際競争を背景に、専門家の間では「中国の独占は長期的には持続不可能」との見方も出ている。米投資会社ストームクロウ・キャピタルのジョナサン・ハイカウィ氏は、「レアアースに関する知見は、今や中国以外にも広がっている。商業ベースでの生産は、時間と資金の問題だ」と指摘する。
また、米シンクタンク戦略国際問題研究所(CSIS)で鉱物安全保障プログラムを担当するグレイスリン・バスカラン氏も、米レアアース企業MPマテリアルズとの提携を引き合いに出し、「時間はかかるが、代替供給網の構築に向けたカウントダウンはすでに始まっている」と述べている。
一方、SCMPは、こうした米中の「激戦地」となっているレアアース埋蔵国にとって、これはチャンスであると同時にリスクでもあると警鐘を鳴らす。ベトナムやミャンマー、マレーシアなどの市場規模や地政学的な状況を踏まえると、中国のほうが米国より多くを提供できる可能性が高いが、中国のレアアース戦略には「アメとムチ」が含まれているとの見方もあるという。


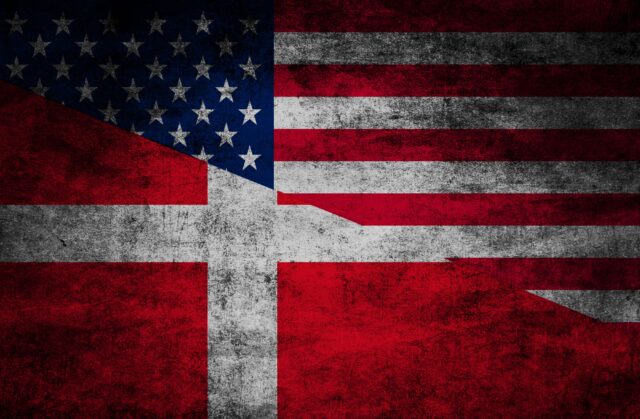



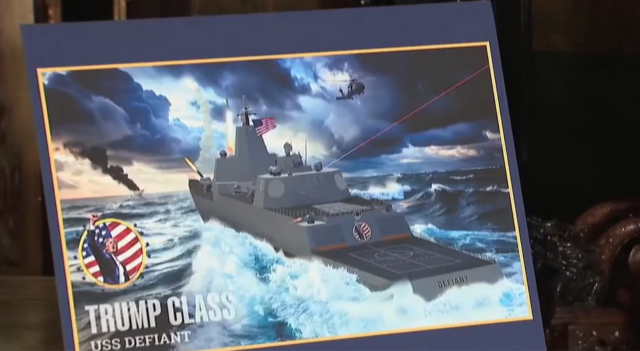





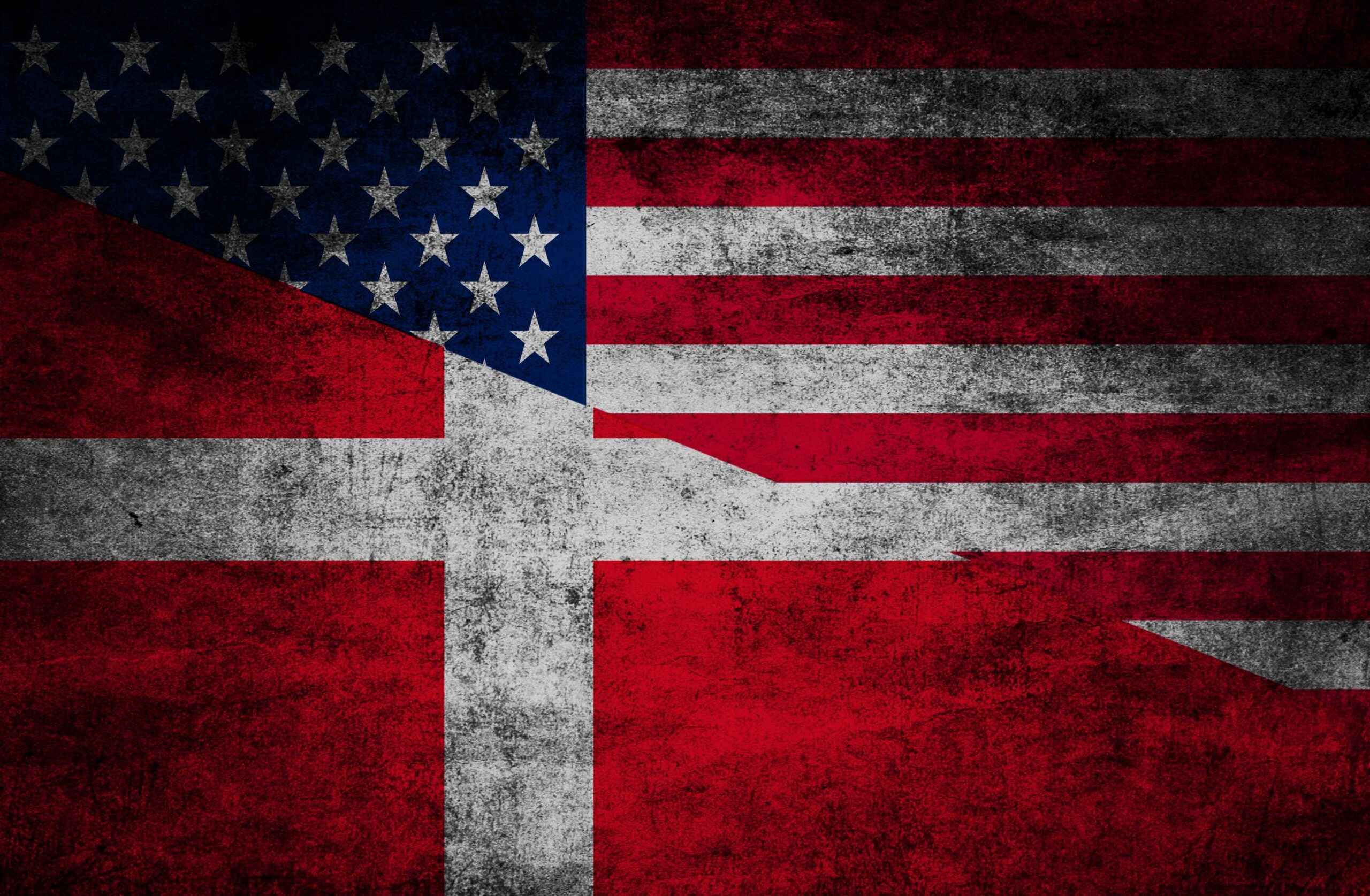








コメント0