
中国が地球上の多くの元素供給を事実上握っている実態が浮き彫りになった。『日本経済新聞』によると、米国地質調査所(USGS)のデータによれば、全118元素のうち少なくとも30種類で中国の生産シェアが50%を超える。
国別の生産割合が判明している65種類の元素のうち、36種類は一国が過半を占め、そのうち30種類を中国が押さえている。液晶ディスプレイ製造に不可欠なインジウムや医薬品原料のビスマスでは精錬製品シェアが70%超という支配的な状況だ。
日経は過去の事例として、中国が米国の関税措置に対抗してレアアース輸出を制限し、日本や米国の自動車メーカーの一部が生産停止に追い込まれたケースを指摘。「中国政府は戦略鉱物を政治的な交渉カードとして使っている」と警鐘を鳴らす。
こうした供給集中は中国に限らない。ブラジルは鉄鋼強化に用いられるニオブ生産の91%を独占、チリはヨウ素の67%、インドネシアは世界ニッケルの約60%を生産している。特にインドネシアはニッケル鉱石の輸出を禁止中だ。
鉱物採掘は人権侵害や環境破壊と隣り合わせで、採掘制限や中止が相次ぐ。これが一部国家への生産集中をさらに加速させているとの分析だ。元素が政治的武器として利用される動きが広がれば、世界の産業構造全体が揺らぐ可能性もある。
日本も資源依存低減へ動く。政府は2026年1月から小笠原諸島・南鳥島沖のEEZで希少金属の試掘を開始予定。民間や学界もリサイクル・抽出技術の開発を急ぐ。住友金属鉱山は来年6月までにリチウムイオン電池リサイクルの商業プラントを完成させる計画で、日産自動車と早稲田大学はハイブリッド車やEVからネオジムを回収する実証実験を進めている。日経は「安定的な希少金属確保には国内資源循環システムの強化と技術進化が欠かせない」と結んだ。



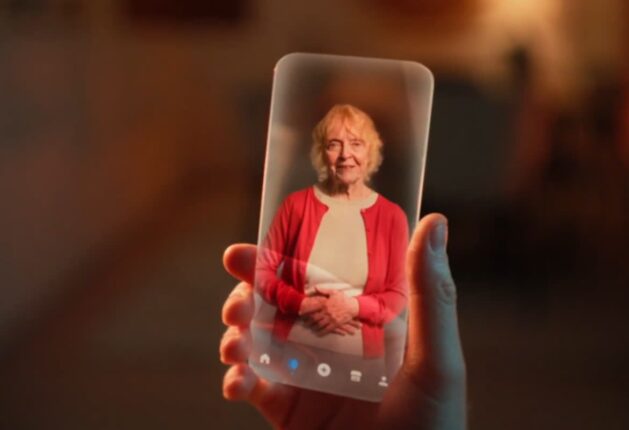


















コメント0