
米連邦準備制度理事会(FRB)の9月の金融政策決定で注目を集めたのは、15日に新たに理事に就任した大統領経済諮問委員会(CEA)のスティーブ・マイロン委員長の動向だった。
マイロン氏は、上院で賛成48、反対47という僅差で承認を受けた直後の連邦公開市場委員会(FOMC)で唯一、0.25%の利下げに反対票を投じた。投票権を持つ12人のうち、11人が0.5%幅の利下げではなく0.25%幅の利下げに賛成した。
7月に利下げを求めていたクリストファー・ウォラー理事とミシェル・ボウマン理事も今回は0.25%の利下げを支持した。ドナルド・トランプ大統領は両氏を「親トランプ」派に分類してきたが、マイロン氏の主張とは一線を画した格好だ。
TD証券は分析リポートで、ウォラー氏やボウマン氏が大幅な利下げに同調しなかったことについて「FRBの独立性を支持する姿勢を示した」と解釈した。パウエル議長も会見で「0.5%の利下げに幅広い支持はなかった」、「今回の決定は強い結束のもとで下された」と強調した。
政策金利見通しを示すドット・チャートでは、年末時点の中央値は年3.5~3.75%となった。ただ、マイロン氏とみられる1人は2.75~3.0%を示し、年内に1.25%幅の利下げが必要だとの強い見方を反映した。
マイロン氏の任期は来年1月までで、8月に辞任したアドリアナ・クグラー前理事の残任期を埋める形となる。共和党はマイロン氏が今回のFOMCに出席できるよう、通常は数カ月を要する承認手続きを異例の6週間に短縮した。CEA委員長職は休職扱いとされている。
政権高官がFRB理事に就くのは、1935年の銀行法改正で独立性が規定されて以降初めてとなる。会見で最初にこの点を問われたパウエル議長は「新理事を歓迎する。委員会は二重の使命達成に向け結束しており、独立性を守ることを強く約束している。それ以上申し上げることはない」と述べた。
FOMC参加者は会議終了から2日後に外部発言が可能となる。マイロン氏も19日以降、メディア出演や寄稿を通じて見解を表明できるようになる。これまでは大統領やベッセント財務長官ら政権幹部がFRBに圧力をかける構図だったが、今後は「FRB内部の対立」という新たな局面へ移行する。独立性への批判をかわす一方で、利下げの是非や規模をめぐる議論は一層激化する見通しだ。


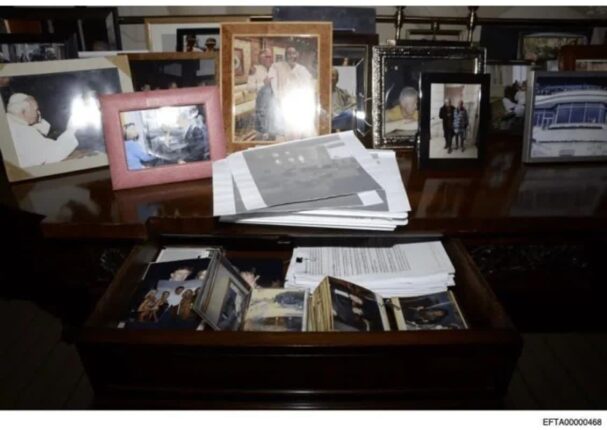


















コメント0