二分された北極圏、「評議会から脱退せよ」――ロシアへの非難の嵐
北極の多国間主義は生き残れるのか?
1996年の北極評議会設立を契機に、数十年にわたって続いてきた北極圏諸国の協力ネットワークが、ロシアのウクライナ侵攻を機に完全に分断された。ロシアは2021年以降、北極に関する多国間協議への参加を停止し、デンマークやノルウェーなど欧州諸国を中心に「反ロシア連帯」が形成されている。戦争の長期化でこうした構図が定着する中、今年の北極サークル総会は事実上、ロシアを非難する場と化した。
今月16日(現地時間)に開かれた総会初日の第1セッションは、「トランプ大統領とプーチン大統領──北極の多国間主義は生き残れるのか」をテーマに開催された。米国とロシアに象徴される「大国の一方主義」は、現在の北極圏で最も激しく議論されるテーマの一つだ。ロシア政府関係者の姿はなく、会場には立ち見が出るほど聴衆が詰めかけ、関心の高さを示した。
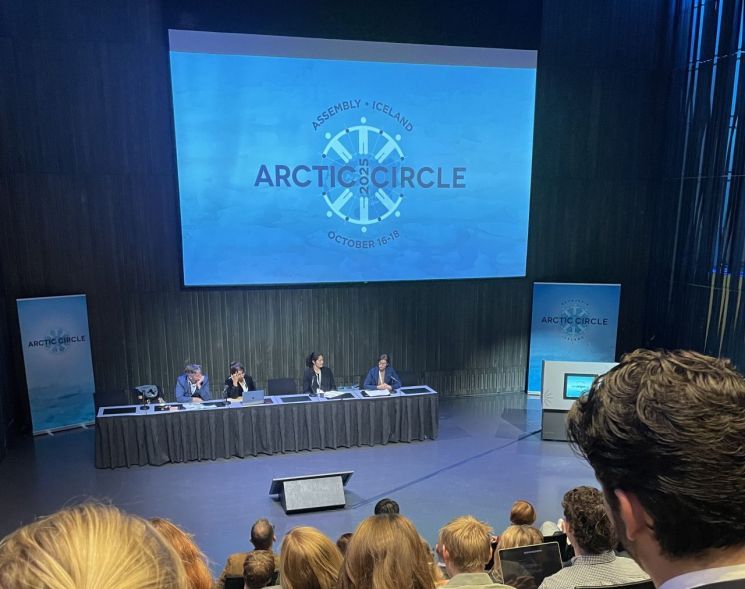
司会を務めたロンドン大学パリ研究所のエダ・アヤイディン国際政治学教授は、「制度を拒絶し、権力を個人に集中させるポピュリスト指導者にとって、北極は『政治的ショーの舞台』となる」と指摘し、「ウラジーミル・プーチン大統領による北極地域の軍事化は、その象徴的な例だ」と批判した。
さらに、「こうした行動は、北極ガバナンスを支えてきた協力と規範の秩序を根底から揺るがす」と述べ、ロシアを排除して評議会を再構築すべきだとの意見も上がった。ポルトガル・リスボン大学のセリーヌ・ロドリゲス博士は「多国間主義を再定義するには、北極評議会を再編成し、安全保障や防衛など、これまで除外されてきた分野の議論を含める必要がある」と提案した。
今年の議長国であるデンマークのラース・ルッケ・ラスムセン外相は開会演説で、「北極評議会は1996年の設立以来、協力の礎となってきたが、ロシアの全面侵攻以降、状況は一変した」と述べ、「残念ながら北極はもはや『低緊張地域』とは言えない」と懸念を示した。その上で、「北極で直面する課題は、狭い国益を超えて共通善のために集団行動をとれるかどうかが試されている」として、多国間主義の回復を呼びかけた。
もっとも、北極圏の欧州諸国がいくら反発しても、北極協議からロシアを完全に排除するのは現実的ではない。ロシアは北極沿岸の半分以上に面し、氷の融解で最も航行可能とされる北東航路(Northern Sea Route)の主要港湾など、重要インフラの大半を保有している。実際の運航経験を通じて蓄積されたノウハウも無視できない資産だ。今後北極航路の開発を目指す非北極圏諸国にとっても、ロシアは協力を避けられない存在である。
北極海の持続可能な利用には、多国間協力を通じた国際社会の共同対応が不可欠だ。








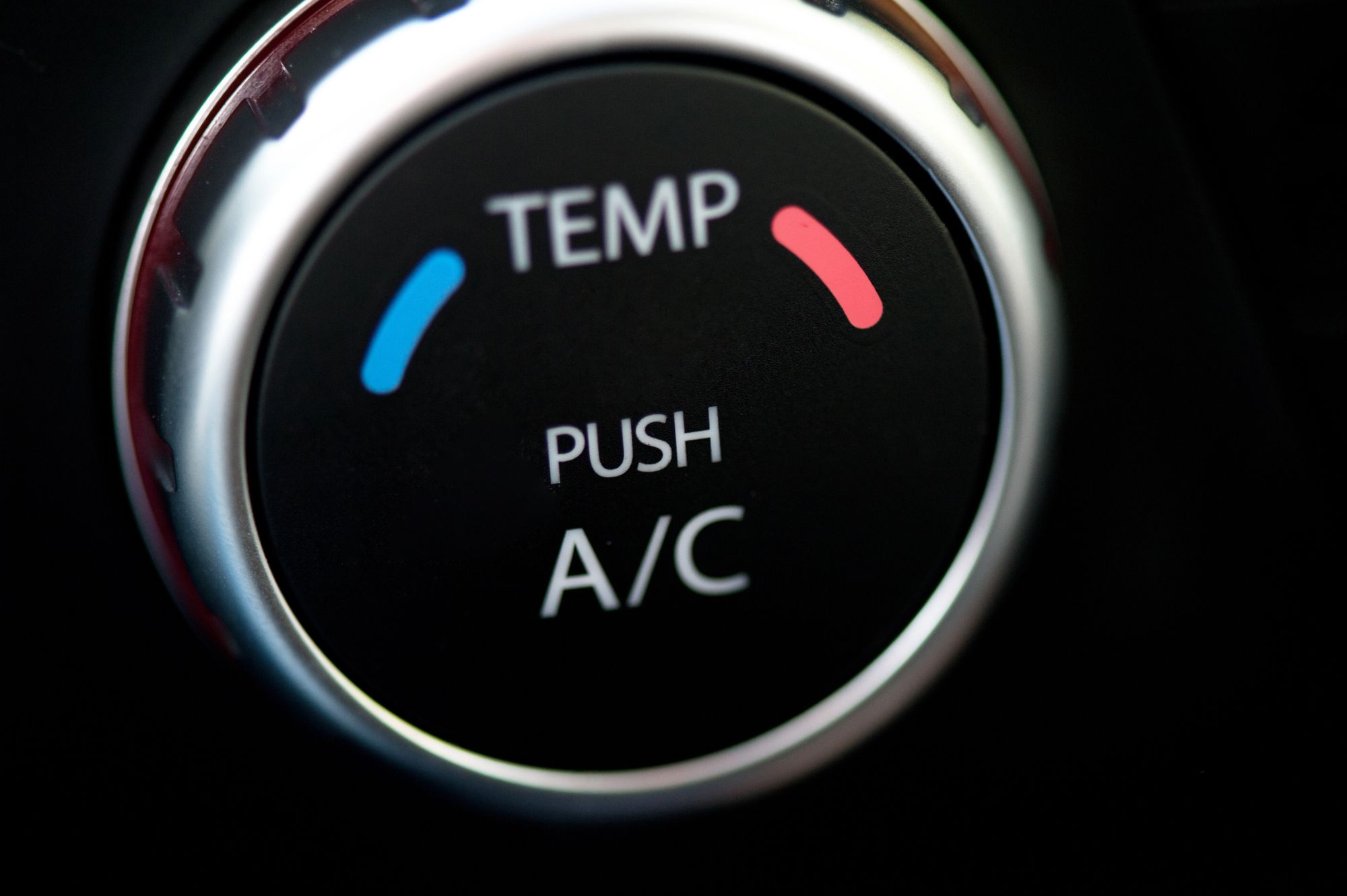



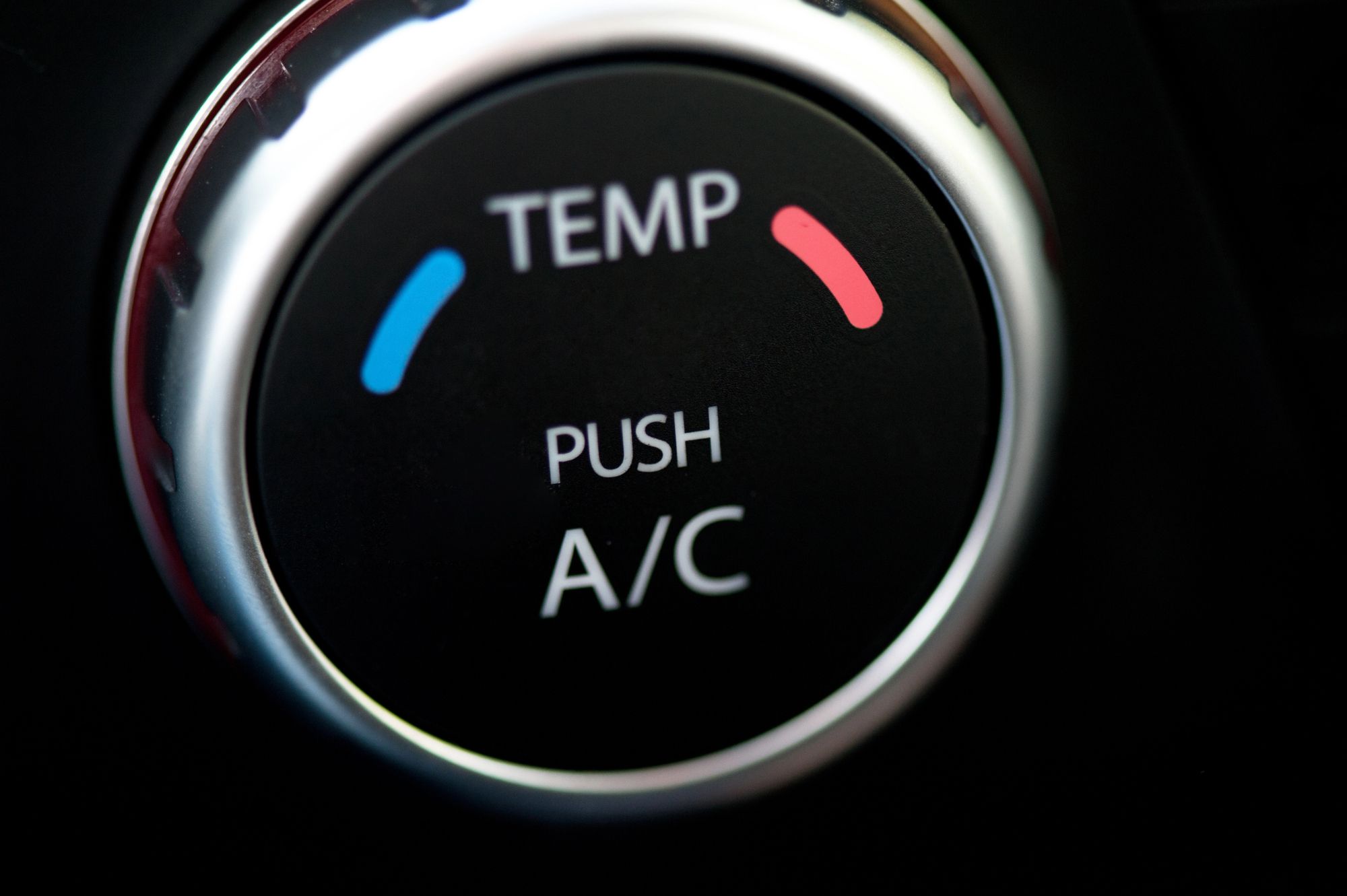








コメント0