中国がドル覇権に対抗し「人民元の力」を強化している。人民元を中心とした決済エコシステムを構築しつつ、低金利で発展途上国にドル負債を人民元に転換するよう促し、「人民元・ブロック」を形成している。デジタル通貨の分野でも米中間の通貨主権競争がますます激化している。

26日(現地時間)のブルームバーグによると、中国人民銀行は24日、潘功勝総裁主催の会議で「人民元の国際化を積極的に推進し、貿易での人民元活用を拡大する」と述べたという。海外メディアは今回の発表について「人民銀行が最近数年間、人民元の国際化政策に言及する際に『慎重かつ着実に』という表現を付けてきたが、今回は削除した」とし、「これはグローバル通貨システムにおける人民元の役割拡大に自信を示したもの」と分析した。
海外市場では人民元資産が爆発的に増加している。中国国家外貨管理局(SAFE)によると、中国銀行の対外債権・預金規模は過去10年間で2倍以上増え、1兆5,000億ドル(約227兆8,135億円)を超えたという。このうち人民元建て資産は今年第1四半期に4,838億ドル(約73兆4,775億円)で最大値を記録した。
特に発展途上国向けの人民元融資規模が拡大している。国際決済銀行(BIS)は、発展途上国向けの人民元融資が過去4年間で3,730億ドル(約56兆6,496億円)増加したと報告している。中国の相対的に低い金利がこうした需要を引き上げた。
今年、ケニア、アンゴラ、エチオピアなどは既存のドル負債を人民元負債に転換し、インドネシアとスロベニアも人民元建て債券の発行を推進している。先月にはカザフスタン開発銀行が年3.3%の金利で20億元(約428億422万円)規模の海外債券を発行した。
貿易金融分野でも人民元の存在感が急速に高まっている。国際決済システム(SWIFT)によると、過去3年間で人民元のグローバル貿易金融シェアは4倍に上昇し、9月時点で7.6%に達したという。人民元はドルに次いで2番目に多く使われる決済通貨になっている。実際の貿易決済段階でも人民元の使用が活発だ。
中国税関の統計によると、人民元による貿易決済規模は月1兆元(約21兆4,005億円)を超えているという。中国の全貿易の約30%、国境を越えた取引の半分以上が人民元で決済されている。それに伴い、中国が開発した決済網「人民元国際決済システム(CIPS)」も急速に成長している。現在CIPSの四半期ごとの取引規模は40兆元(約856兆207億円)を超えている。
特にBRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)諸国が人民元ブロックの中核になっている。BRICSではドル以外の様々な通貨を活用した決済が広がっており、この中で人民元はブロック内貿易の半分近くに使用されている。中国は各国との通貨スワップ協定を拡大し、人民元の基盤を広げている。
ただし、資本規制は依然として人民元国際化の最大の障害と指摘されている。国際通貨基金(IMF)によると、今年初めの時点で世界の外貨準備高における人民元の比率は2.1%に過ぎないという。投資可能な人民元資産が限られているためだ。これを改善するため、中国は香港を「人民元ハブ」として育成している。香港当局は人民元建て債券の発行と流動性拡大のための市場活性化のロードマップを発表した。
米中間の通貨主権競争はデジタル通貨領域にも及んでいる。米国は民間主導でドル連動型ステーブルコインを育成し、グローバル決済秩序におけるドルの地位をさらに強化している。7月に議会を通過した「ジーニアス法」はステーブルコインの法的地位と担保要件を明確にした。しかし、米国連邦準備制度理事会(FRB)は主要国と比べ中央銀行発行デジタル通貨(CBDC)の研究開発が遅れているとの評価を受けている。
これに対抗して中国はデジタル人民元(E-CNY)を金融主権の核心的なツールとして位置付け、市場育成を加速させている。中国は超高速決済が可能な独自の決済システムを基盤に、SWIFT依存度を低下させ、ドル中心の市場秩序に挑戦している。中国当局はアリババ、JD.comなどの大手IT企業が香港で発行しようとしていたステーブルコイン事業を全面的に中止させ、「通貨発行権は中央にある」という原則を強調した。





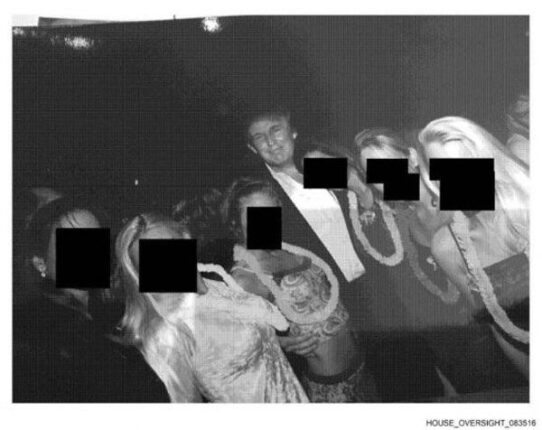







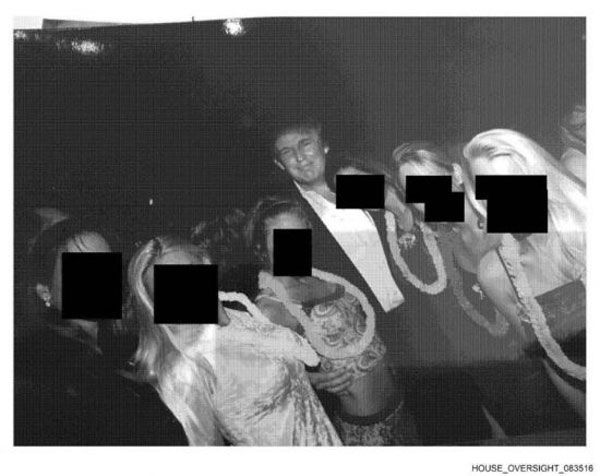








コメント0