
中国が世界の科学研究分野で米国に急速に迫っており、早ければ2027年から2028年には、両国の主導的地位が同水準に達するとの分析結果が発表された。
28日(現地時間)、米『ブルームバーグ』は、米国科学アカデミー紀要(PNAS)に掲載された最新の研究を引用し、米中の共同研究で「リーダー役」を担う中国在籍の科学者の比率が、2010年の30%から2023年には45%に上昇したと報じた。
研究は、「この傾向が続けば、中国は2027年または2028年には米国と並ぶ」との見通しを示している。
同研究は、中国の武漢大学と米カリフォルニア大学ロサンゼルス校、シカゴ大学の共同チームによって実施された。機械学習モデルを用い、論文内の著者データや「貢献説明」欄を分析し、誰が研究プロジェクトを主導したのかを特定した。
従来の論文数や引用指数といった統計指標よりも、実際の影響力を反映する「科学力(scientific power)」を追跡できると、研究チームは説明している。
この論文は、ドナルド・トランプ米大統領の第2期政権下で、大学を含む研究機関や科学関連機関が大幅な研究費削減方針に直面するなかで発表された。
『ブルームバーグ』によると、論文では、こうした政策的変化が「グローバルな科学研究の主導権が中国に移る流れを一段と加速させる恐れがある」と指摘している。
また、研究チームが「米中共同研究が半減した場合」と「完全に断絶した場合」をそれぞれシミュレーションした結果、いずれのケースでも中国の研究者が国際共同研究における「リーダー役」をさらに拡大させると予測された。これは、共同研究の相手が米国ではなく、欧州やその他の国の研究者に移るためだという。
論文はさらに、中国の科学研究における主導力が、特に「戦略分野」で急速に強まっていると分析した。
アメリカ国立科学財団(NSF)が定義する戦略分野は、AI、半導体、エネルギー、材料科学など11分野。このうち、中国の研究者が米国と同等のリーダーシップ比率に達するとみられる分野は、2030年以前に8分野に上るという。
論文はまた、中国が科学外交の一環として教育を活用している点にも言及している。
政府資料によると、中国はアフリカや南アジアなどからの留学生受け入れのために、2012年以降、総額333億元(約7,200億円)を拠出している。これは、2013年に打ち出された「一帯一路」構想の一環だ。
2018年以降、中国で学ぶ外国人留学生の約半数、あるいはそれ以上がアフリカや南アジア出身である。
論文はさらに、「一帯一路」対象国との共同研究では、中国側の研究者が主導的役割を担うケースが大半だとも指摘している。












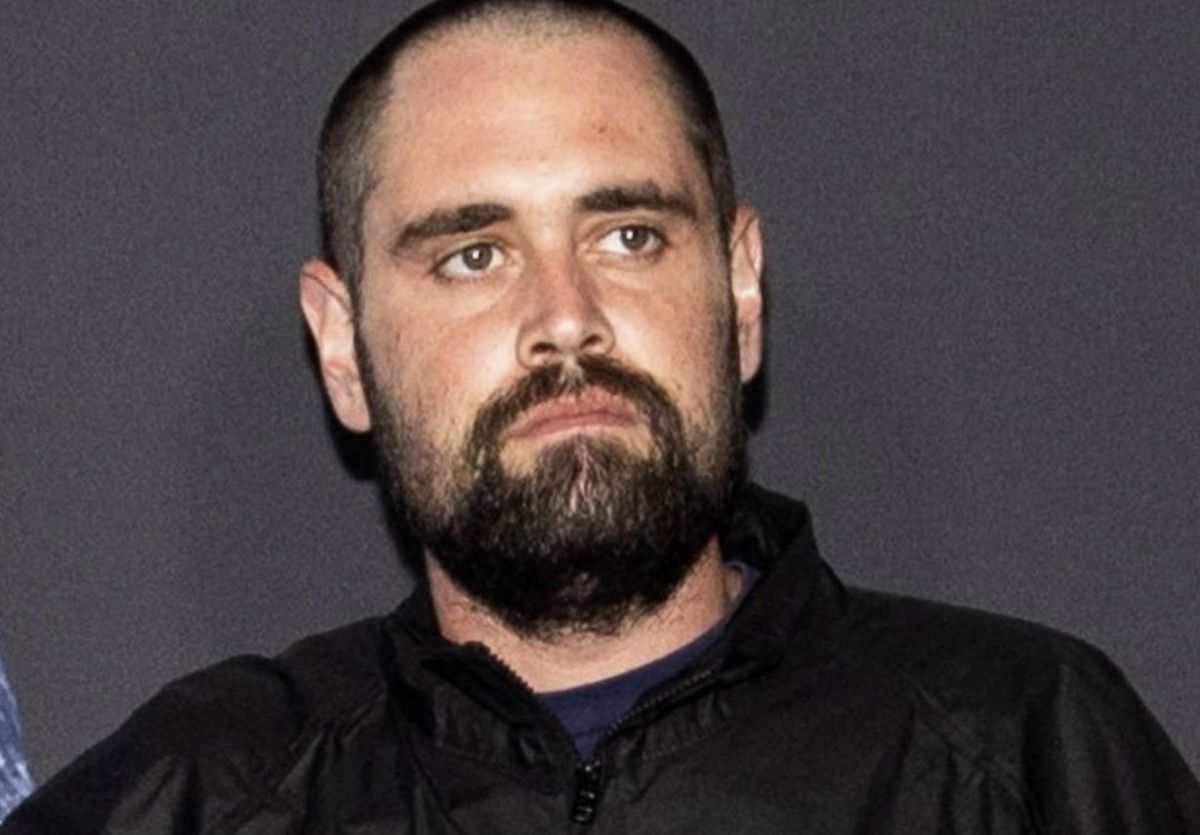








コメント0