
トヨタ自動車が2026年3月期の連結純利益見通しを従来の予想より2,700億円上方修正し2兆9,300億円にすると日本経済新聞(日経)が6日に伝えた。これは前期比39%減少した水準だが、当初予想していた44%減少幅より縮小した。同社は売上高を2%増の49兆円、営業利益を29%減の3兆4,000億円とそれぞれ5,000億円、2,000億円上方修正したと発表した。米トランプ政権の関税政策により営業利益が1兆4,500億円減少すると予想されるが、全世界でバランスの取れた販売戦略がこれを相殺しているとの分析だ。
トヨタの強みは特定地域に依存しない「全地域戦略」にある。北米市場での販売比率が28%でGM(56%)やホンダ(47%)より著しく低く、中国市場比率も17%程度でフォルクスワーゲンやGMの30%と対照的だ。トヨタ自動車の東崇徳経理本部は「どの地域が1位というわけではなく、非常に地域バランスの取れた収益構造を持っている」と説明した。この戦略が米国の関税政策や中国現地企業の攻勢の中でも安定した収益を確保する基盤になっているとの評価だ。
地域別の現地化戦略も成果を上げている。北米では現地の研究開発拠点を通じてピックアップトラック「タンドラ」と「タコマ」など現地需要に合った車種を投入した。中国では今年発売した電気自動車「bZ3X」を200万円台で価格設定し、現地市場の動向に対応した。
動力源戦略でも全方位アプローチを維持している。電気自動車の開発を推進しながらもハイブリッド車とプラグインハイブリッド車の開発を並行した結果、4~9月期のハイブリッド車販売比率が41%で前年同期比1ポイント増加した。この戦略の効率性は「トヨタ・ニュー・グローバル・アーキテクチャー(TNGA)」プラットフォームの共用化を通じて確保されている。プリウスを皮切りにクラウン、カローラ、RAV4など主力車種に適用した結果、TNGA導入前と比べて生産ラインあたりの設備投資額と開発工数を25%、車両原価を10%それぞれ削減したと同社は明らかにした。
トヨタ自動車の近健太最高財務責任者は「顧客の強い需要を受けており、これは長期間蓄積した商品力によるものだ」と評価した。2026年3月期の販売量見通しも史上最高の1,050万台で従来より10万台上方修正した。海外競合他社と比較してもトヨタの実績は良好だ。7~9月の3か月間の最終損益でフォルクスワーゲンが赤字に転落し、GMが60%減少の1,956億円を記録したのに対し、トヨタは62%増の9,320億円の増益を達成した。
日本経済新聞によれば、5日に発表した4~9月期の連結決算では売上高が前年同期比6%増の24兆6,307億円、純利益が7%減の1兆7,734億円を記録したという。同期間の全世界販売量は5%増の526万台で史上最高を達成したと発表した。






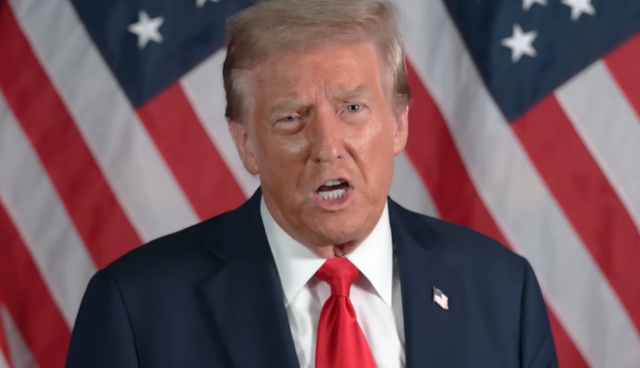







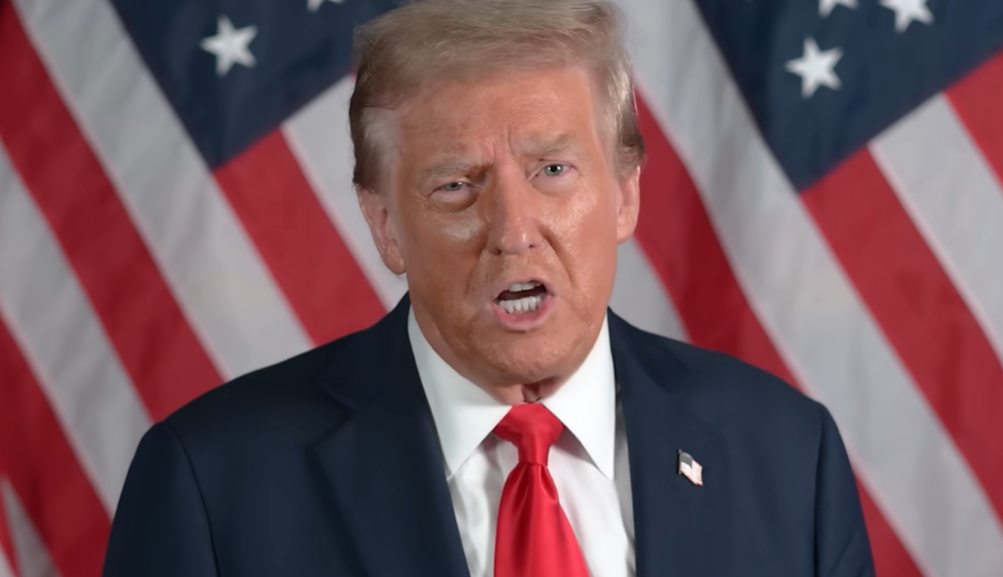






コメント0