
中国が小型原子炉を用い、数年間にわたり燃料補給なしで航行可能な大型貨物船の開発計画の詳細を公表した。特にウランではなくトリウムを燃料とする溶融塩原子炉を採用し、安全性を高めたと主張している。
香港の英字紙『サウス・チャイナ・モーニング・ポスト』は、中国船舶集団(CSSC)傘下の江南造船の主任技師、フークイ氏が、1万4,000個のコンテナを積載可能な原子力推進大型貨物船の仕様を明らかにしたと報じた。
先月刊行された貿易専門誌『船舶』によると、同商船はウランではなくトリウムを燃料とする熱出力約200㎿(メガワット)級のトリウム溶融塩原子炉(TMSR)を動力源とする。搭載される原子炉の出力は、米海軍の最新型攻撃型原潜に用いられるS6W加圧水型原子炉と同程度とされる。
ウラン炉は大規模な冷却系や高圧の格納設備を必要とするのに対し、トリウム溶融塩炉は冷却材として冷却水ではなく溶融塩を用いる点が特徴だ。これにより、プルトニウムのように核兵器に転用され得る副生成物を生じにくく、従来型のウラン炉に比べて小型で静音性に優れ、核拡散抵抗性も高いという。

トリウム炉の200㎿級の熱出力は直接船舶推進に使われるのではなく、ブレイトンサイクル(Brayton cycle)を用いて超臨界二酸化炭素(sCO₂)発電機に供給される。二酸化炭素を高温まで加熱し、タービンで膨張させて発電し、その電力で大型貨物船を長期間、燃料補給なしに航行させる仕組みである。
原子力推進船に対する最大の懸念の一つは炉心溶融や放射性物質の漏えいだが、トリウム溶融塩炉は溶融塩を冷却材として用いるため、冷却水不足による炉心溶融の可能性は低いと説明している。
中国国内には内モンゴル自治区などに豊富なトリウム資源が存在するとされ、単一の鉱山だけで中国全土に1,000年以上の電力を供給できるほどの埋蔵量があるとも指摘される。
米国でも1960年代、テネシー州のオークリッジ国立研究所でトリウム炉の試験が行われたが、溶融フッ化物塩による配管腐食など技術的課題が生じ、研究は中断された。

これに対し中国は、ゴビ砂漠に設置した実験用トリウム溶融塩炉で世界に先駆けて長期安定運転に成功したとし、現在はさらに大型の発電用試験炉の建設を進めている。
ただし、トリウム自体は即時に核分裂を起こす物質ではないものの、中性子吸収によってウラン233に変換されれば核兵器製造に転用が可能となる。このため、「商船」を名目に原子力空母や原子力潜水艦など戦略的軍用プラットフォームに発展する可能性を懸念する声もある。
なお、中国が最新空母「福建」に続いて建造中の4隻目の空母は、原子力推進方式を採用し、先進的な電磁式カタパルトを搭載するとみられている。







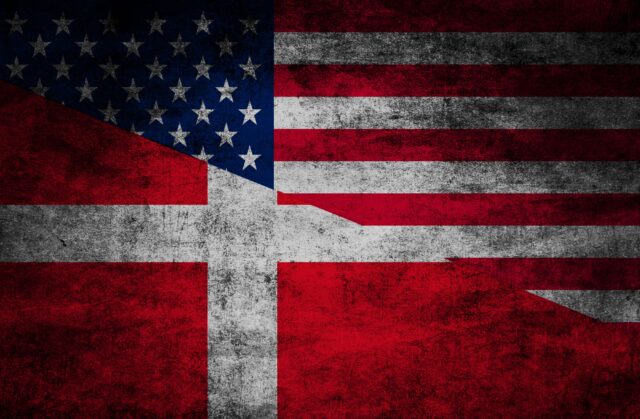













コメント0