メタ・オープンAI・xAI、AI投資で「フランケンシュタイン金融」を活用
過度な借入と債券発行、将来のAI関連企業と市場に負担の可能性
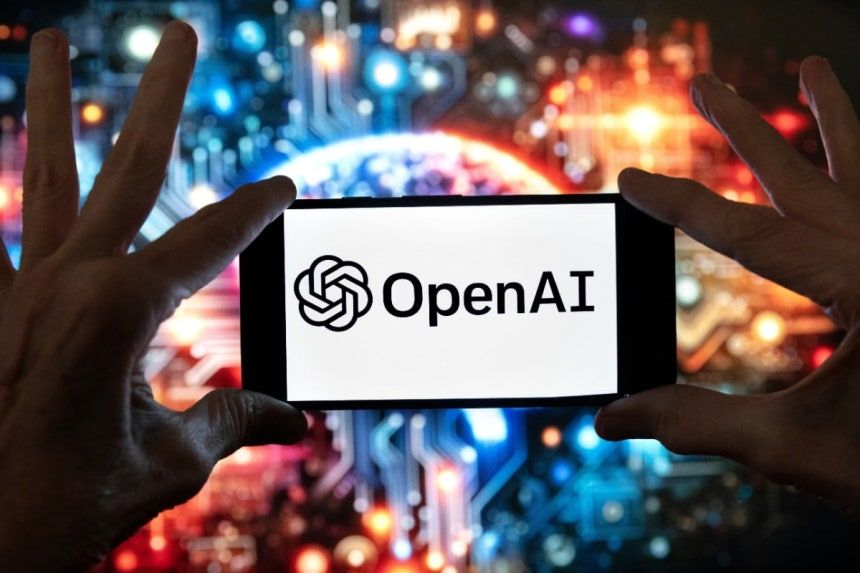
米ウォール街では、人工知能(AI)インフラへの投資ブームを背景に、前例のない資金調達手法が次々と打ち出されている。メタ、オープンAI、xAIなどの大手テクノロジー企業は、AIデータセンターの建設に数十億ドルを投じる一方で、投資銀行やプライベート・エクイティファンドは、リスク分散と収益最大化を同時に狙った「複合型金融構造」を設計している。
ただし、こうした複雑な金融構造や過度な借入、債券発行が、AIブームの終焉時にAI関連企業や金融市場に負担をもたらす可能性があるとの懸念も指摘されている。
賃貸と保証を組み合わせた「フランケンシュタイン金融」

『ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)』は11日(現地時間)、メタやオープンAI、xAIなどがAI投資のために複雑な資金調達構造を受け入れている点を集中的に報じた。
中でも注目されているのが、ルイジアナ州で建設中のメタの超大型データセンター「ハイペリオン」プロジェクトである。この事業は、プライベート・エクイティ(PE)、プロジェクトファイナンス、社債を組み合わせた複合的な金融構造で、市場では「フランケンシュタイン金融」と呼ばれている。
メタは、AI投資の拡大に伴い負債が急増する中、直接の借入を避け、合弁会社「ヴィーニー・インベスター(Vigne Investor)」を設立して資金を迂回的に調達した。「ブルー・アウル・キャピタル」は約30億ドル(約4,600億円)を投資し、80%のプライベート・エクイティを確保。メタはすでに投入した13億ドル(約2,000億円)で20%の持分を維持した。
この合弁会社はその後、2049年満期の債券270億ドル(約4兆2,000億円)を発行。そのうち180億ドル(約3兆円)をピムコが購入した。債券の利回りは年6.58%で、メタの一般社債より約1ポイント高い水準となっている。
この資金調達の核心は賃貸構造にある。メタは該当データセンターを「賃借人」として利用し、賃料を支払うことで、その賃料から債券の利息・元本や投資家への配当が支払われる仕組みだ。しかし、メタは4年ごとに契約を解除できる権利(オプション)を持つ。その場合、投資家や債権者の損失をすべて補填する「保証条項」が付いている。つまり、会計上は賃借人として扱われるものの、実質的にはメタが負債を間接的に保証する構造になっている。
ブルー・アウル・キャピタルはこの構造を、「債券のような安定した収益(固定収益リスク)と、株式のような高い利益の可能性を組み合わせた投資モデル」と評価した。ブルーアウルは、メタからの安定した賃料で利子収益を得る一方、データセンターの価値が上昇した場合には株式型の収益も期待できるとみている。
賃料が借入返済の原資に
二例目は、チャットGPTを開発するオープンAIとオラクル、さらに孫正義会長率いるソフトバンクが共同で進める「スターゲート」データセンタープロジェクトである。この事業の資金調達取引は「ジャカード」と呼ばれている。つまり、スターゲートがデータセンター事業の名称であり、ジャカードはその建設資金調達(ファイナンシング)の取引名という位置付けである。
データセンターの開発・運営を手掛けるバンテージ・データセンターズは、テキサス州とウィスコンシン州にそれぞれ約380億ドル(約6兆円)規模のデータセンターを建設しており、オラクルはこれらの施設と15年間の長期賃貸契約を締結した。最終的な利用者はオープンAIである。しかし、オープンAIは直接の借入能力が十分でなく、オラクルもビッグテックの中では信用格付けが比較的低い水準にある。
これに対して、JPモルガン・チェースと三菱UFJ(MUFG)が幹事を務め、銀行団がバンテージにプロジェクト・ファイナンス融資を提供した。オラクルはバンテージに賃料を支払い、バンテージはその資金を銀行団への融資返済に充てる。つまり、「オラクルの賃料 → バンテージ → 銀行団(債権者)」という順に現金が流れる構造となっている。
今回の取引には30行以上の銀行が参加しており、規模の大きさから一部の銀行はリスク分散のため、融資持分を投資家に再販売している。金利は年約6.4%で、オラクルの同程度の満期を持つ社債より約2ポイント高い。JPモルガンはこの融資について、比較的小規模な格付け機関「クロール」からBBBの格付けを受けており、融資債権担保付証券(CLO)への組み入れは難しい状況である。
チップ購入費用も民間の信用で賄う
イーロン・マスクが率いるxAIの二つ目の超大型データセンター「コロッサス2」でも、別の複雑な金融構造が適用されている。
マスクは、オープンAIを超えるという目標のもと、スペースXなど自身が関わる他企業の資金を動員しているが、エヌビディア製チップ30万個を購入するには約180億ドル(約3兆円)が必要となる。しかし、新興企業であるxAIがこの資金を一度に調達することは難しい状況である。
そこでマスクは、プライベート・エクイティ・ファンドのバロ・エクイティ・パートナーズとプライベート・クレジット運用会社アポロ・グローバル・マネジメントに協力を要請した。両社は特別目的会社(SPV)「バロ・コンピュート・インフラストラクチャー」を設立し、この法人が代わりにチップを購入、xAIはそのチップを一定期間賃借する仕組みに設計された。チップの法的所有権は投資家側の法人にあり、xAIは賃料を支払ってデータセンターの運営に使用する。この賃料こそが、投資家が融資の元本と利子を回収するための資金源となる。つまり、xAIはチップを所有せずに借りて使用し、チップを担保とした金融構造が資金調達の中核を成している。
xAIがこの「チップ賃借型資金調達」を選択した理由は、主に現金流動性の確保、資産リスクの回避、会計上の利点の三点にある。投資家が代わりにチップを購入し、xAIが借りて使用することで、初期の現金負担を大幅に軽減できる。また、GPUは技術進展の速度が非常に速く、数年後には旧型となる可能性が高いため、この方法は資産リスクの回避にもつながる。
チップ価格が下落した場合の損失は、チップを所有する投資家側が負担するため、xAIは賃料を支払うだけでリスクを外部に移転できる。xAIがチップを直接購入すれば大規模な負債として計上されるが、賃借方式を採用すれば会計上は運用費用として処理され、財務諸表上の負債比率は低下する。こうしてxAIは現金負担とリスクを軽減し、投資家はチップ資産の希少性とAI市場の成長性に賭ける形となる。
しかし一部の専門家は「エヌビディアとその顧客間の循環投資構造がAI資産市場のバブルを膨らませている」と指摘している。
「AIバブル崩壊で最初に揺らぐ可能性」
AIインフラ建設向けの超大型金融ディールが相次ぐ中、ウォール街では熱狂と不安が入り混じっている。ピムコのダン・イバスシン最高投資責任者(CIO)はウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)に対し、「長期的な景気後退を経験していない環境では、複雑さと安易さが同時に増大する」と指摘。「現在市場に流れ込んでいる負債ディールの規模は、過去の信用サイクル時をはるかに上回っている」と警鐘を鳴らした。
















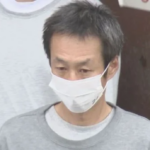




コメント0