
中国は人工知能(AI)競争に勝っているのか。
この問いの発端は、エヌビディア(NVIDIA)のジェンスン・ファンCEO(Jensen Huang)の一言だった。「中国がAIレースに勝つだろう」。彼は西側の冷笑、輸出規制、エネルギーへのアクセスなどを根拠に挙げた。その後、エヌビディアのX公式アカウントには「中国は米国より『ナノ秒』遅れている」という訂正メッセージが投稿された。利害関係のある発言かもしれないが、中国の追い上げを裏付けるシグナルは少なくない。
第一に、エネルギー・インフラだ。AI競争が大規模データセンターをどれだけ速く建設し稼働できるかの戦いであるなら、中国はスピードと調整能力で強みを持つ。政府主導の実行力、電力補助、簡素化された許認可が電力集約型施設の運営を支えている。
一方、米国は規制が分断的で電力コストが高い。都市ごとに電力網が飽和し、一部企業は自社発電所の建設を検討している。マイクロソフト(Microsoft)は「電力不足でGPUが『在庫』として残っている」と明かした。電力が次のボトルネックになるとの警告の中、北京は解決策の準備が速いという評価だ。
第二に、オープンソースの逆転だ。a16z(アンドリーセン・ホロウィッツ)は最近の報告書で、中国がオープンソースAIのダウンロード数で米国を上回ったと明らかにした。同社はこれを「スカルグラフ・モーメント(skull graph moment)」と呼んだ。格差を埋めた挑戦者が既存の強者を追い越す時点という意味だ。a16zのアンジニー・ミドハ(Anjney Midha)氏はディープシーク(DeepSeek)とR1を挙げ、米国企業がフロンティアチームにより多く投資し格差を縮めるべきだと促した。
第三に、最適化能力だ。ディープシークは「最初」を作らなくても、より速く安く、性能損失なく実装する能力を示した。テンセント(Tencent)のCALMモデルは、トークン単位の生成の代わりに連続ベクトル予測を導入し、効率を大幅に引き上げたと報告した。
ディープシークの新たなオープンソースモデルは、テキストを視覚表現に圧縮し、より多くの情報をより低コストで処理できるよう設計された。西側の研究所でも類似技法をすでに内部的に使用している可能性も指摘されているが、中国側が公開と拡散に積極的だという点が異なる。
もちろん、まだ結論を出すには早い。中国が確実な勝機を掴んだとは見難い。米国は超大規模モデル、チップ設計、エコシステムで依然として圧倒的な力を持っている。ただし、エネルギーアクセス、大規模インフラの実行力、オープンソースのダイナミクスにおいて中国の追撃は実際に速まった。AIの勝負所がアルゴリズムの微細な改善ではなく電力とデータセンターになる瞬間、力の均衡はさらに揺らぎうる。今の問いはシンプルだ。誰がより多くの電力をより安く調達し、より大きなモデルをより長く回すか。その問いに中国がますます準備された答えを出している。


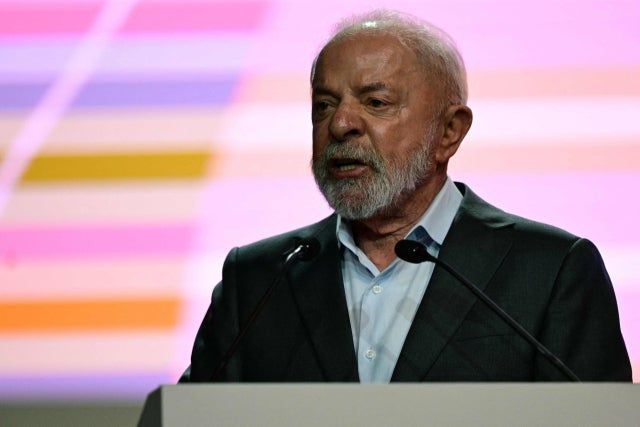











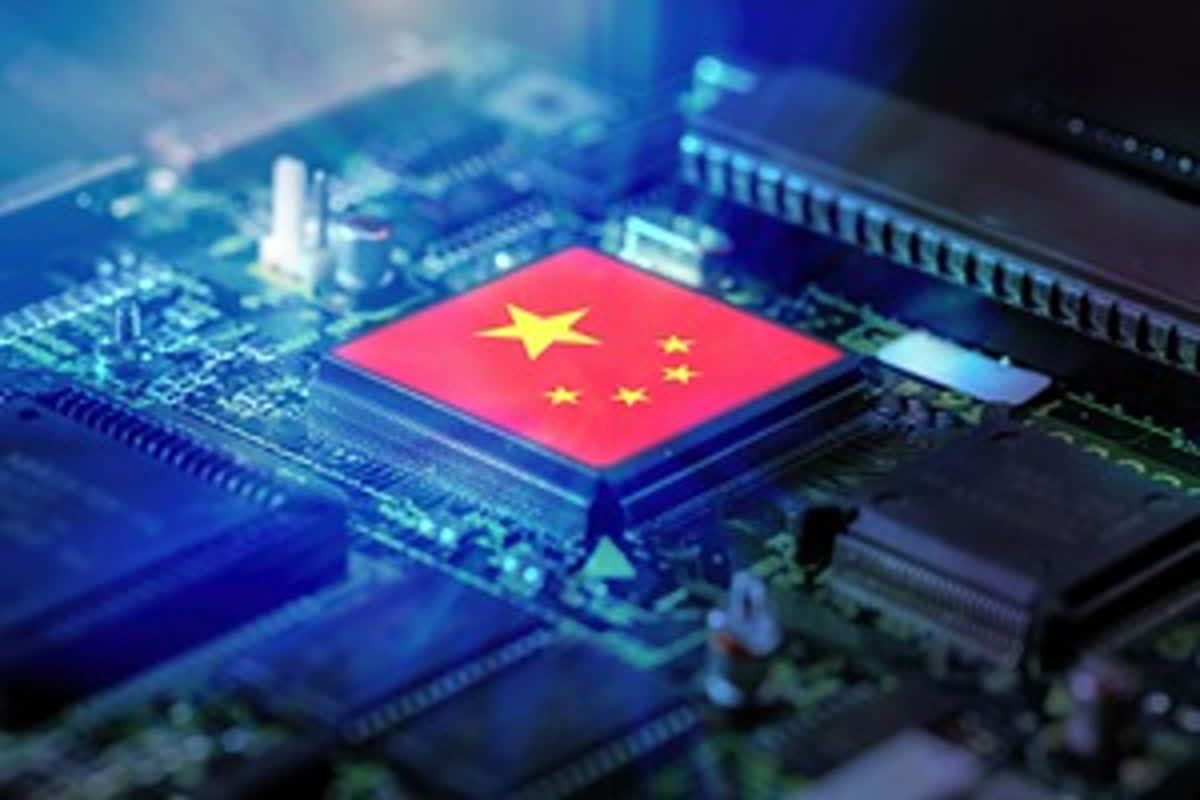






コメント0