米国の大型インフラ事業など2,500件に資金投入

過去24年間に米国が中国から受けた融資額が約30兆円規模に迫るとの調査結果が明らかになった。
中国の対外信用供与において、これまで大きな割合を占めた開発途上国向けは減少した一方、米国や欧州など先進国への資金提供が大幅に増加しているという。
18日(現地時間)、ロイター通信やワシントン・ポスト(WP)によると、米ウィリアム・アンド・メアリー大学の付属研究機関エイドデータは、2000年から2023年にかけて中国が217カ国に総額約2兆2,000億ドル(約341兆7,350億8,000万円)の信用供与を行ったとする報告書を発表した。
そのうち、米国向けの融資額は2,000億ドル(約31兆657億7,800万円)を超え、対象国の中で最も多かった。
この期間、中国の資本は米国内の主要インフラ事業など約2,500件のプロジェクトに投入されている。
中国の国有企業は、米国とカナダを結ぶ高圧送電線、テキサス州やルイジアナ州のLNG事業、バージニア北部のデータセンター、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港やロサンゼルス国際空港のターミナル整備、テキサス州のガスパイプライン建設などに資本を投じてきた。
さらに中国政府は、自国企業がアマゾン、AT&T、ベライゾン、テスラ、ゼネラルモーターズ、フォード、ボーイング、ディズニーといった米大手企業の株式を取得できるよう資金を提供していた。
また中国の銀行は、自国企業が半導体やDNA解析など先端技術を扱う米企業の株式を取得するため、数百億ドル規模の融資を行ったという。
こうした中国による米国へ巨額の資金供与について、複数の海外メディアは「先端技術を保有する西側企業への影響力や統制権を確保する狙いがある」と分析している。
今回の調査結果は、中国が「一帯一路」構想を通じ、最貧国を中心に融資してきたという従来の見方とは異なる傾向を示した点でも注目される。
報告書によると、中国の対外貸付の4分の3以上が現在、中所得国・高所得国でのプロジェクトに投じられていることが判明した。
中国の対外貸付に占める低所得国・下位中所得国の割合は、2000年の88%から2023年には12%まで急減した。一方、中所得国・高所得国向けの比率は同期間に24%から76%へと急増した。
また、中国が米国に供与した資金のうち、半分以上にあたる1,030億ドル(約15兆9,971億4,800万円)が2018年以降に貸し出されたことも確認された。
このため、発展途上国が中国からの借入による債務負担や主権侵害を訴えてきた一方で、米国や欧州などの先進国自身が巨額の対中融資依存について十分に把握してこなかったのではないかとの指摘も浮上している。












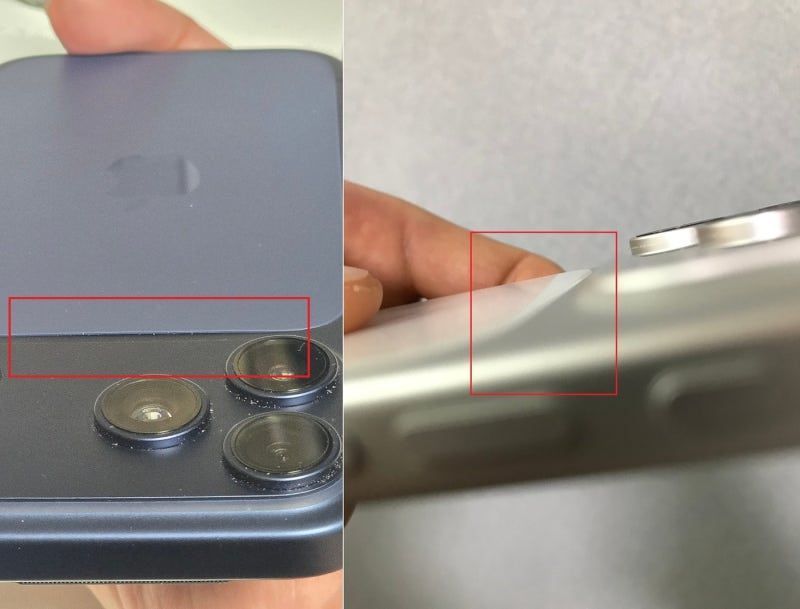
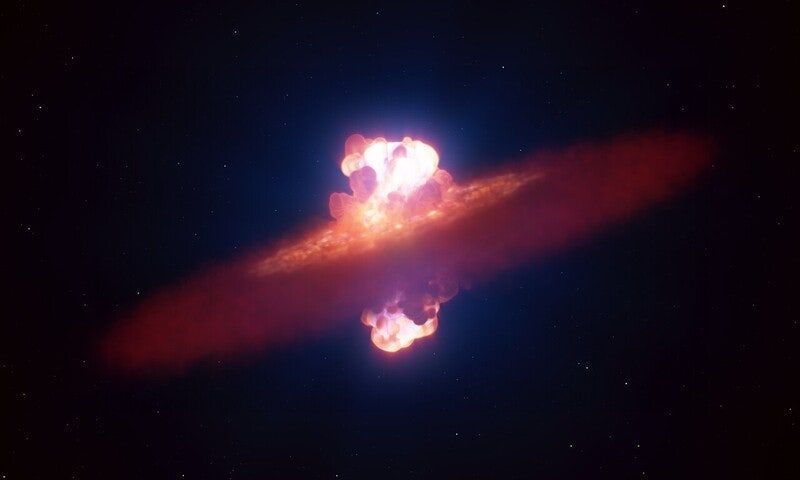







コメント0