かつて「欧州の病人」と呼ばれたイタリアが、再起の兆しを見せている。背景には財政改革の成果があり、フィッチなど国際的な格付け機関が相次いでイタリアの国家信用格付けを引き上げた。一方で、かつて「財政中毒」に陥り格下げを受けたフランスとは対照的だ。ただし、依然として欧州でも突出した国家債務を抱え、高齢化による低成長など課題は山積しているとの指摘もある。
数年ぶりの国家信用格付け引き上げ

フィッチは19日、イタリアの信用格付けを「BBB」から「BBB+」へ1段階引き上げ、見通しを「安定的」とした。2021年12月に「BBB-」から「BBB」に引き上げられて以来、4年ぶりの好評価となる。S&Pも今年4月にイタリアの格付けを「BBB」から「BBB+」に1段階引き上げ、2017年以来8年ぶりの引き上げとなった。
両格付け機関は、ともに引き上げの根拠として財政健全化を挙げた。フィッチは「歳入構造の改善と厳格な歳出管理により財政改善の成果が現れた。これによって財政健全性への信頼が高まり、政府の財政目標達成への意欲が強まった」と説明している。
IMFおよびイタリア政府によれば、イタリアのGDP比国家債務残高は2020年の154.3%から昨年は135.3%に低下。同期間のGDP比財政赤字比率も9.4%から3.4%まで縮小した。ジャンカルロ・ジョルジェッティ財務相は「今年の税収は堅調に増加しており、財政赤字比率をGDP比で3%未満に抑えることが可能だ」と述べた。
財政改善は国債利回りの低下にもつながった。10年物国債利回りは22日(現地時間)の終値で年3.574%となり、2023年の高値である年4.800%から1.226ポイント低下。これにより、直近で格下げされたフランス(年3.558%)との水準が接近した。なお、フランスの格付けはフィッチ基準でイタリアより2段階上の「A+」だが、国債市場では両国の信用リスクがほぼ同等と評価されている。投資会社BBVAの欧州債券ストラテジスト、フィリッポ・モルマンド氏は「イタリアは財政再建に向けて一貫した努力を続けてきた」と分析している。
異例の政治安定
イタリアの財政改善を支えた要因として、政治の安定が挙げられる。第二次世界大戦後70年以上で60回以上も政権交代を繰り返したイタリアだが、2022年10月に発足したジョルジャ・メローニ首相率いる右派連立政権は上下両院で安定多数を確保。この政治的安定が財政改革を進める推進力となった。
フィッチも「現在の安定した政治環境が財政改革目標の達成に寄与している」と指摘し、「過去のように政策が二転三転し、不安定だった時代とは対照的だ」と強調した。これに対しフランスでは、マクロン大統領の中道勢力、極右の国民連合(RN)、左派の新人民戦線(NFP)が拮抗し、国会は分断。法案成立は困難な状況にある。
また、イタリア政府が財政改革を段階的に進め、世論の反発を避けながら無駄な歳出の削減に取り組んだことも効果的だった。住宅の省エネ改修費用などを最大110%補助する「スーパーボーナス」制度を大幅に縮小したのがその一例である。メローニ政権はこれを「福祉削減ではなく、税金の無駄遣いを防ぐための措置」と説明し世論を説得。その後、中期財政改革案を発表し、3〜5年先の赤字・債務の見通しを先に示すことで政策の予測可能性を高めた。
低成長基調に懸念
税収基盤の強化も成果を上げた。電子インボイスや電子レシート、現金取引の追跡といったデジタル課税方式の全面導入により、昨年の脱税追徴額は過去最高の263億ユーロ(約4兆5,962億7,940万円)に達した。さらに、普遍的福祉から選別的福祉への転換も進められ、弱者支援と就労促進の両立が模索されている。
ただし、イタリア経済の将来が楽観視できるわけではない。最大の課題は成長率の低迷であり、2023年以降の実質GDP成長率は0%台にとどまり、EU平均を下回っている。少子高齢化による生産年齢人口の減少が成長の足かせとなっているとの懸念が根強い。



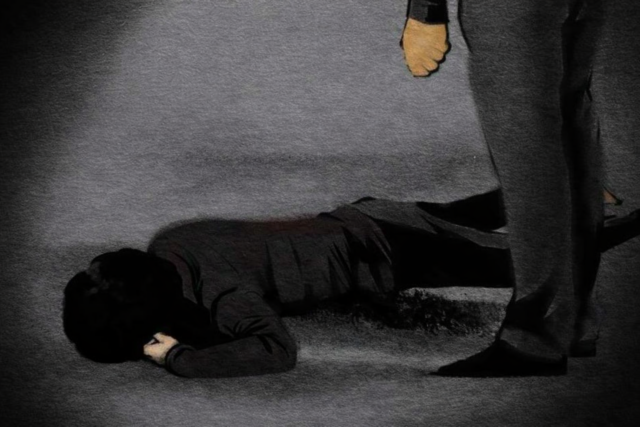
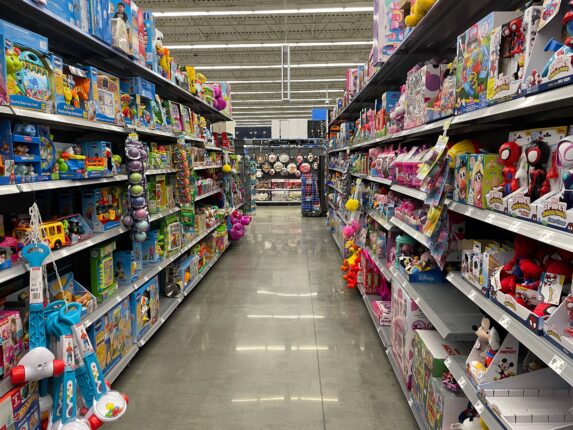





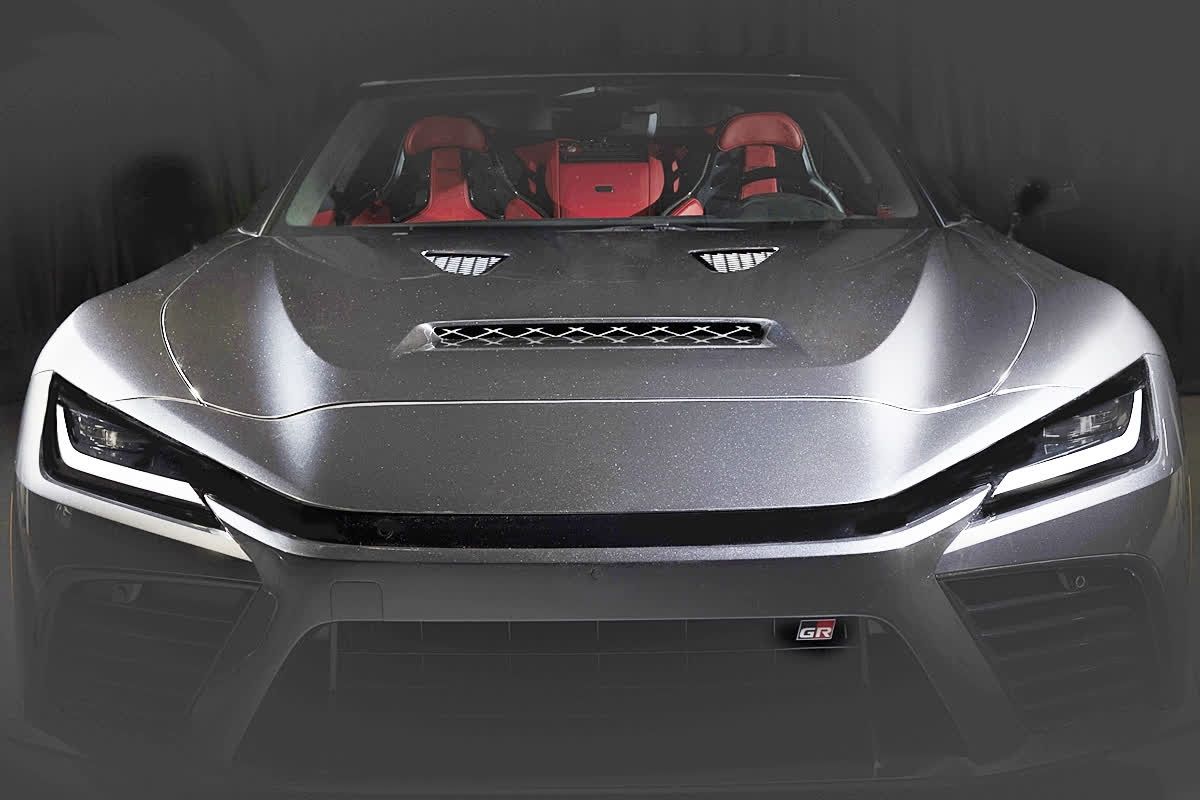










コメント0