オーストリアは中立国としての地位を基盤に、国際外交の舞台で影響力を拡大しようとする構想を打ち出した。これに先立ち、オーストリアは1955年に他国間の戦争に介入しない代わりに、自国の安全保障が保証される小規模な中立国であると宣言し、軍事同盟に加盟せず、外国軍の駐留も禁止するという意思を示した。

ブルームバーグなどの海外メディアは、ベアーテ・マインル=ライジンガー外務大臣が最近のインタビューで「北大西洋条約機構(NATO)に属さない点はむしろ長所である」と述べ、「常に対話に専念すべきだと認識している」と強調したと報じた。特定陣営に属さないオーストリアが国家間の紛争の仲介者として適しているとの発言と受け止められている。
マインル=ライジンガー外相は、3月に発足した3党連立政府(オーストリア国民党、オーストリア社会民主党、NEOS)の一員として外務大臣に就任し、国際外交におけるオーストリアの存在感を高めることに注力している。左派寄りのNEOSに所属する同外相は、ロシア・ウクライナ戦争の平和交渉を目的とした会談の開催地としてウィーンを提案するとともに、オーストリアに本部を置く国際原子力機関(IAEA)とイランとの間で核交渉を促すなどの行動に出ている。
特にマインル=ライジンガー外相は、中立国としてのオーストリアが持つ長い伝統を外交上の資産として強調している。かつてオーストリアはハプスブルク帝国時代から、戦争ではなく外交と婚姻同盟を通じて欧州内で影響力を拡大し、ナポレオン戦争後に欧州秩序を再建した外交でクレメンス・フォン・メッテルニヒを輩出するなど、仲裁国としての役割を培ってきた。
冷戦時代、オーストリアは旧ソ連の共産主義と西側資本主義陣営の境界に位置し、双方をつなぐ玄関口として評価された。1955年には連合軍占領の終了に伴い、軍事的非同盟路線を維持するとともに、欧州安全保障協力機構(OSCE)など主要な国際機関の本部誘致に成功し、中立国としての地位を確立した。
こうした中立路線は国民多数の支持を得ているが、ロシア・ウクライナ戦争以降、その実効性に疑問が投げかけられている。現在、オーストリアはNATOに加盟する隣国スロバキアとハンガリーの抑止力に依存しており、防衛費の支出は国内総生産(GDP)の1%程度にとどまっているため、安全保障上の空白に直面している。
ロシアと密接な関係を持つオーストリア経済にも、中立国としての在り方を巡る議論がある。首都ウィーンでは主にロシアの顧客を対象とする法律・コンサルティングネットワークが活発であり、ロシアの財閥がこの地域で多数の不動産を保有していることも知られている。現地のライファイゼン銀行はロシア関連事業からの撤退を先送りする中で、アメリカ合衆国や欧州中央銀行(ECB)から圧力を受けた。
一方、ロシア・ウクライナ戦争やトランプ大統領再任による安全保障環境の変化を受け、中立国としての立場が揺らいでいるとの見方もある。初の中立国であるスイスは今年4月、オーストリア・ドイツ合同訓練に陸軍を派遣し、2003年以降初めて外国軍の訓練に参加したことで注目された。その後、8月にアメリカから39%の関税措置を受けたことを契機に、欧州連合(EU)とより緊密な関係を築くべきだとの声が国内で強まった。




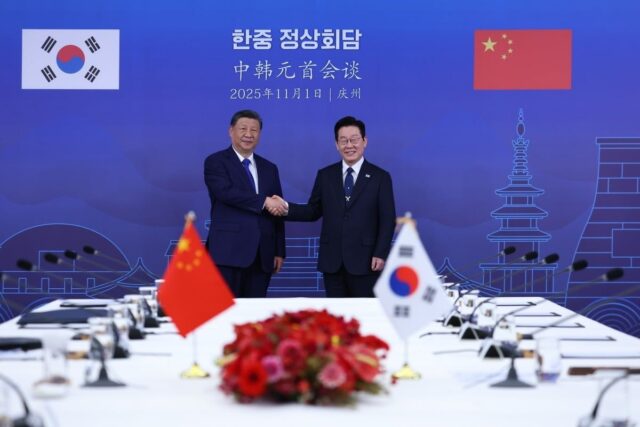







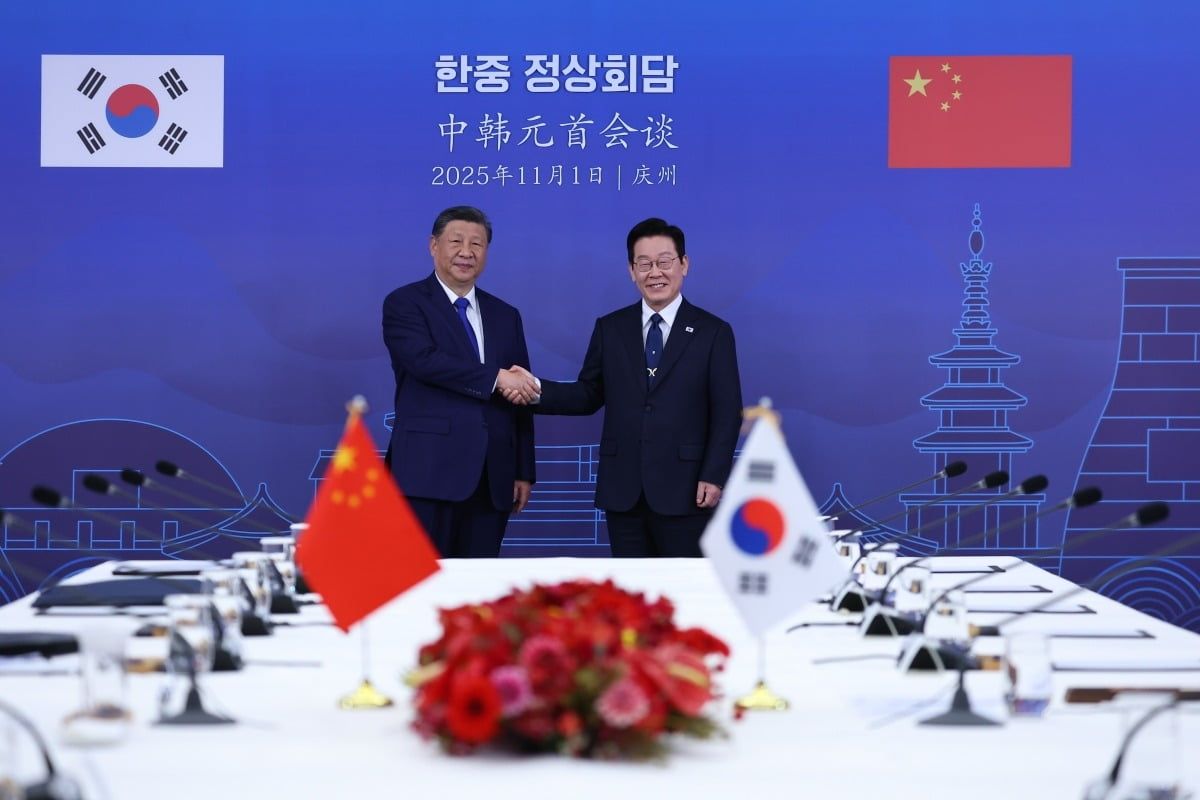



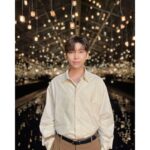




コメント0