オーストラリア・ジェームズクック大学研究チーム「進化的な遺物の可能性」を指摘
海で最も危険な生物の一つとされるサメも、逆さまにされて腹を見せると動かなくなり、まるで凍りついたかのようになる「緊張性不動(トニック・イモビリティ)」状態に陥る。なぜサメは腹を見せるだけで突然おとなしくなるのか。
IT系メディア「BGR」は、サメがこのような行動を示す理由に関する研究結果を報じた。このニュースは非営利学術メディア「ザ・コンバセーション」でも紹介された。
オーストラリア・ジェームズクック大学の海洋生物学者ジョディ・L・ラマー教授率いる研究チームは、サメやエイなどに見られるこの行動を調査した。サメやエイは腹を見せると即座に動きを止め、筋肉が弛緩し、まるで催眠状態のようになる。

緊張性不動は動物界全体で見られる現象だが、その原因は明確には解明されていない。特に海洋生物においてはなおさらだ。この行動は一般的に捕食者に対する防御機制と考えられることもあるが、それを直接裏付ける証拠は得られていない。
研究チームは、サメ、エイ、そして通称「ゴーストシャーク」とも呼ばれるギンザメなど13種を対象に、水中で体が逆さまになった時に緊張性不動現象を示すかどうか実験を行った。その結果、7種でこの現象が確認されたが、6種では見られなかった。
サメの緊張性不動を説明するために、3つの主要な仮説がある。1つは捕食者に食べられないよう「死んだふりをする」という仮説。もう1つは、オスのサメが交尾中に争いを減らすためメスを逆さまにすることから、生殖に関連しているという仮説。最後は、極度の刺激による感覚過負荷反応だ。
研究チームはデータを収集し、数億年にわたるサメの系統における行動パターンを比較分析した結果、サメのこの行動が上記3つの仮説のいずれも裏付けないことを明らかにした。サメが捕食者を避けるために動きを止めることは、サメにとってまったく利点がない。また、緊張性不動は性別に関係なく現れるため生殖仮説も妥当ではなく、感覚過負荷という概念も検証されていないと指摘した。
研究チームは、この特性が進化の産物である可能性を示唆した。「この特性は古代種の一部に見られたが、進化の過程で多くの種から消失した。しかし、一部の種は依然としてこの特性を保持している」としながらも、なぜこの特性が一部の種にのみ残っているのかは、まだ解明されていないという。







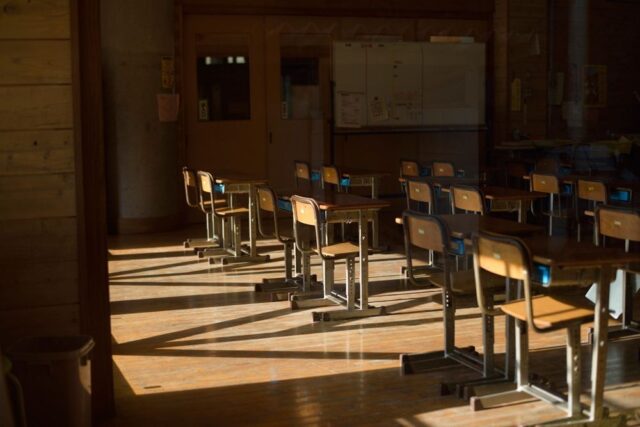





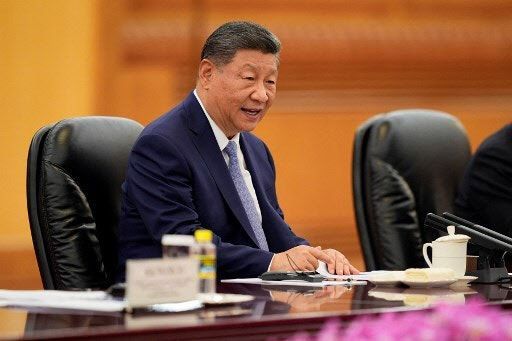







コメント0