AIが脳を怠けさせる時代へ
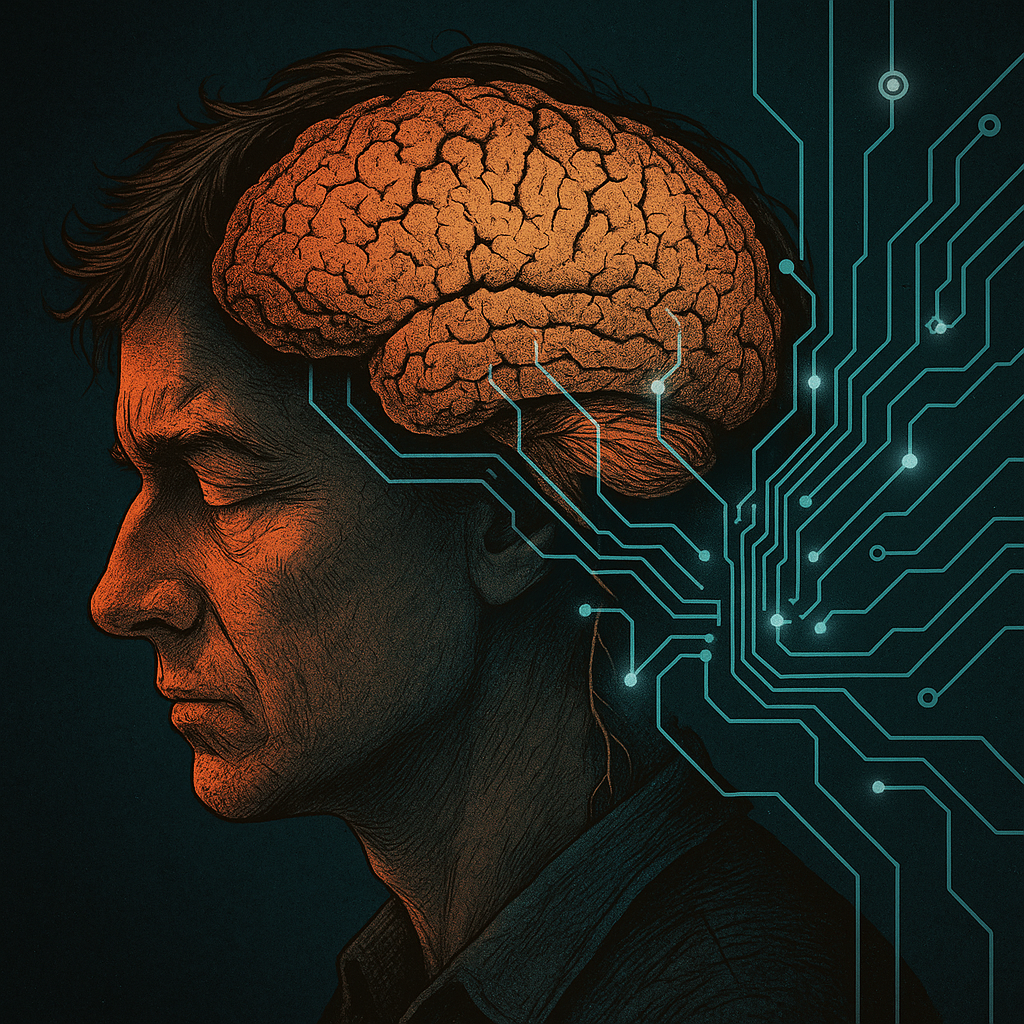
生成型人工知能(AI)を使用して文章を作成した学生は、使用しなかった学生に比べ、創造性や集中力に関連する脳活動が著しく低下していた。AIが人類の知的水準を低下させる可能性を示す結果となった。
22日(現地時間)、英エコノミスト誌によると、米マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボの研究チームは、大学生54人を対象とした文章作成実験の結果を発表した。
AIを用いて文章を作成した学生と、使用せずに作成した学生の脳波を比較した結果、AI使用グループでは創造性や注意力に関与する脳領域の活動が顕著に低下していた。また、AI使用グループでは、生成された文章の内容を正確に記憶できない傾向も見られた。
研究チームは、生成型AIが認知的負担を軽減することで脳活動を低下させると分析し、「短期的な利便性が、思考力の長期的低下に結びつく可能性がある」と指摘した。
同様の懸念は他の研究でも示されている。米マイクロソフトが知識労働者319人を対象に実施した調査では、AIを活用した業務のうち、半数以上は「ほとんど考えずに済む作業」と評価された。
スイスの経営大学のミヒャエル・ゲルリッヒ教授も、「AIを頻繁に使用する人ほど批判的思考力の評価スコアが低い」という研究結果を発表した。
専門家はこの現象を「認知的外部化(cognitive offloading)」と定義する。人間の脳が自律的な思考を放棄し、外部ツールへの依存を強める傾向を指す。
カナダ・ウォータールー大学のエバン・リスコ教授は、「AIは単なる計算にとどまらず、問題解決の過程全体を代替し得る。複雑な思考をAIに委ねる習慣は、脳の活動を鈍化させるおそれがある」と警告した。
AIの利用に対しては、回避ではなく適切な関与が求められるとの見方もある。「正解を提供する道具」ではなく、「思考を補助する手段」として位置づけるべきだとの助言が専門家の間で広がっている。
例えば、AIに旅行先を直接尋ねるのではなく、利用者が条件を明確に設定し、その条件に基づいて問いを立てる方が有効とされている。





















コメント0