
米国の大企業が出勤義務を強化しているにもかかわらず、従業員のオフィス出勤率は大きく変動していないことが明らかになった。
21日(現地時間)、ウォール・ストリート・ジャーナルは、米国企業が在宅勤務の割合を減らし、オフィス勤務を拡大する方向に政策を転換し、従業員の出勤率向上に努めていると伝えた。
職場研究所ワークフォワードが9,000の雇用主を対象に調査した結果、米国企業が昨年初めと比べて従業員にオフィス勤務時間を12%多く要求していることが分かった。
ニューヨーク・タイムズは現在、週3回の出勤を義務付けているが、11月からは週4日に増やす予定だ。マイクロソフトも来年2月から太平洋北西部の従業員に週3日の出勤を求める計画だと明らかにした。
映画会社パラマウントはニューヨークとロサンゼルスの従業員に対し、今年1月から週5日出勤するか、さもなければ退職を迫る最後通告を出した。NBCユニバーサルも来年から週4回の出勤を要求し、同様の選択肢を従業員に提示したと報じられている。
アマゾン、デル、JPモルガンなどの主要大企業も今年に入り、在宅勤務を縮小し出勤義務の強化を本格化させている。
実際にオフィス出勤者が増えた地域もある。ニューヨーク市では、JPモルガンやゴールドマン・サックスなどの大手銀行が全面出勤を要求し、地下鉄利用者数がパンデミック以降最高水準を記録。7月には歩行者数も2019年の水準を上回ったと報告された。
しかし、大企業の出勤要求強化にもかかわらず、在宅勤務の割合は依然として高いことが調査で明らかになった。
米国全体で見ると、パンデミック前の2019年と比較してオフィス出勤回数が約3分の1減少した状態だ。コロナ禍で在宅勤務が広まり、オフィス訪問が大幅に減少。その後も完全には回復していないと分析されている。
米スタンフォード大教授(経済学) ニコラス・ブルーム氏によると、米国全体で現在も従業員の約4分の1が在宅勤務を続けているという。
在宅勤務が根強く支持されるなか、企業側の悩みは深い。優秀な人材の流出を防ぐため、在宅勤務を許可する雇用主もいる。IT業界で長年人事責任者を務めたベス・スタインバーグは「企業は成果を上げている従業員が出勤しないことを罰することができない状況だ」と述べた。
役員層においても在宅勤務志向は強い。米国の給与労働者1,500人を対象にした調査では、高位管理職の約半数が在宅勤務のために給与削減も受け入れる意向があると回答した。
企業は出勤義務の強化が従業員の離職につながるとの懸念もある。実際、グローバル商業不動産専門会社CBREの調査によれば、週1回の出勤要求ではほぼ全従業員が従うが、週3日以上の出勤を要求すると75%以下の従業員しか従わないことが明らかになった。
ただし、一部の企業は出勤要件を通じて人員削減を誘導しているとの指摘もある。ニコラス・ブルーム教授は「出勤圧力は低コストの人員整理策だ」と述べた。
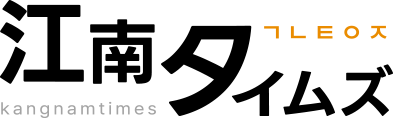





















コメント0