
超高齢社会に突入した日本で、高齢者医療費の急増に伴う健康保険料の引き上げに対し、若い世代から強い不満の声が上がっている。昨年は歴史的な賃上げの効果すら健康保険料の上昇に打ち消され、若い世代を中心に経済的負担が一層重くなっている。
日本健康保険組合連合会が25日に発表したところによると、昨年の高齢者医療拠出金は前年比5.7%増の3兆8,591億円となり、過去最高を記録した。平均保険料率も9.31%と前年度比0.04ポイント上昇し、過去最高を更新。今年は9.34%に達し、再び最高を更新する見通しだ。
特に保険給付費に占める高齢者医療拠出金の割合は40%に達し、現役世代が高齢者の医療費を支える構図が一層強まっている。全国約1,400の健保組合のうち、赤字に陥ったのは660組合で全体のほぼ半数に上り、保険料率が10%を超えた組合も334組合と全体の4分の1を占めた。
日本の健康保険制度は、大企業の健保組合、中小企業従業員向けの協会けんぽ、自営業者や退職者向けの国保と多層的に構成されている。保険料率が10%を超えると、大企業が独自の健保組合を維持する経済的メリットが失われる「解散ライン」とされる。実際、昨年は保険料引き上げの影響で10の健保組合が解散または合併した。
問題は、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者に突入し、医療費の急増が加速している点にある。昨年の日本の医療費総額は48兆円と4年連続で過去最高を更新し、このうち後期高齢者医療費は初めて全体の40%を超えた。2010年に12兆7,000億円だった後期高齢者医療費は、昨年には19兆6,000億円へと膨れ上がっている。
今年の春闘では大企業が平均5%超の賃上げを実施したが、保険料上昇によって実質的な所得増効果は限定的となった。健保組合の昨年の経常収支は145億円の黒字だったものの、これは賃上げによる保険料収入増1,069億円でようやく補った結果にすぎない。2023年には1,365億円の赤字を計上していた。
若い世代の負担増に懸念が広がる中、日本政府も対応に乗り出している。来月からは所得に応じて一部の後期高齢者の医療費負担を増やし、2028年までに所得や資産水準に基づく差別化された保険料制度を導入する方針だ。
日本経済新聞は「現役世代の保険料負担で高齢者医療制度を支える構造が、消費拡大など賃上げ効果を阻害しかねない」とし、「現役世代の負担抑制に向けた改革の試金石となる」と分析した。



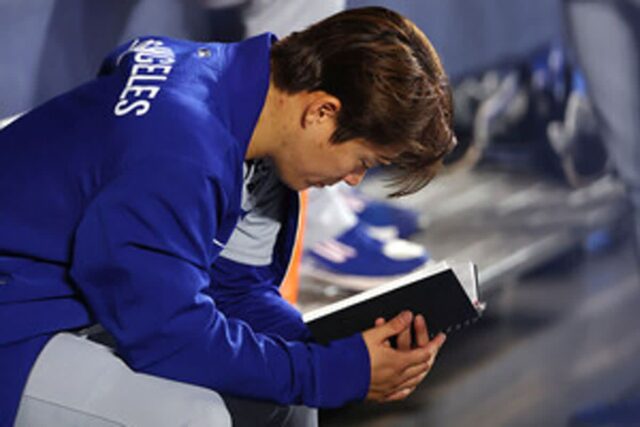






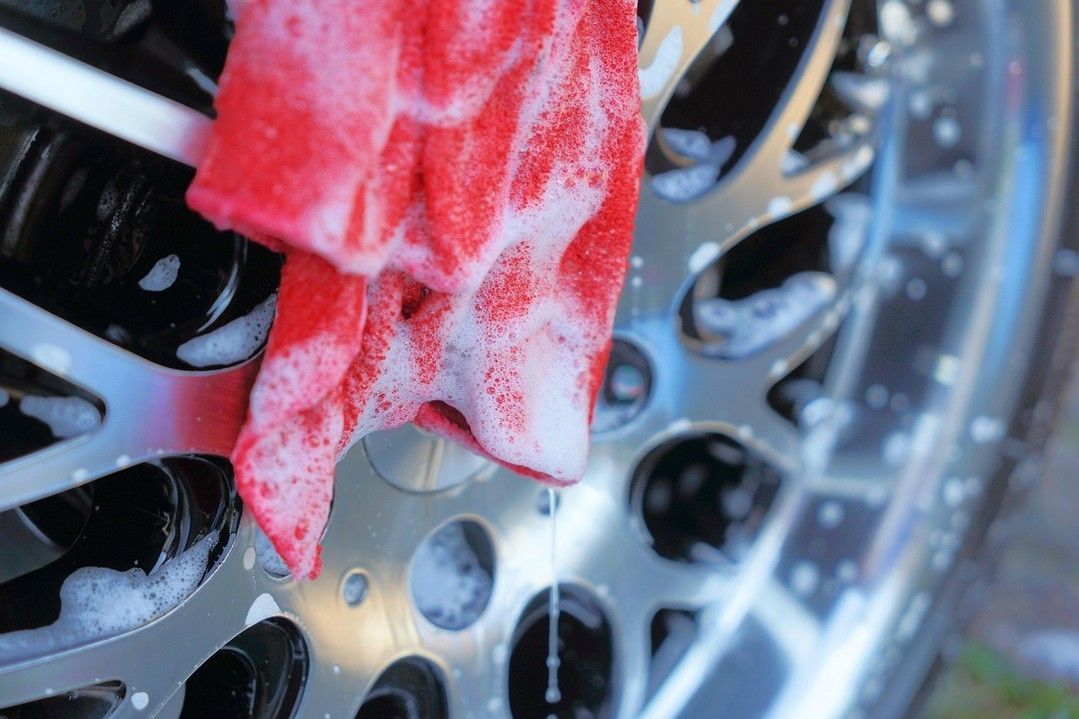


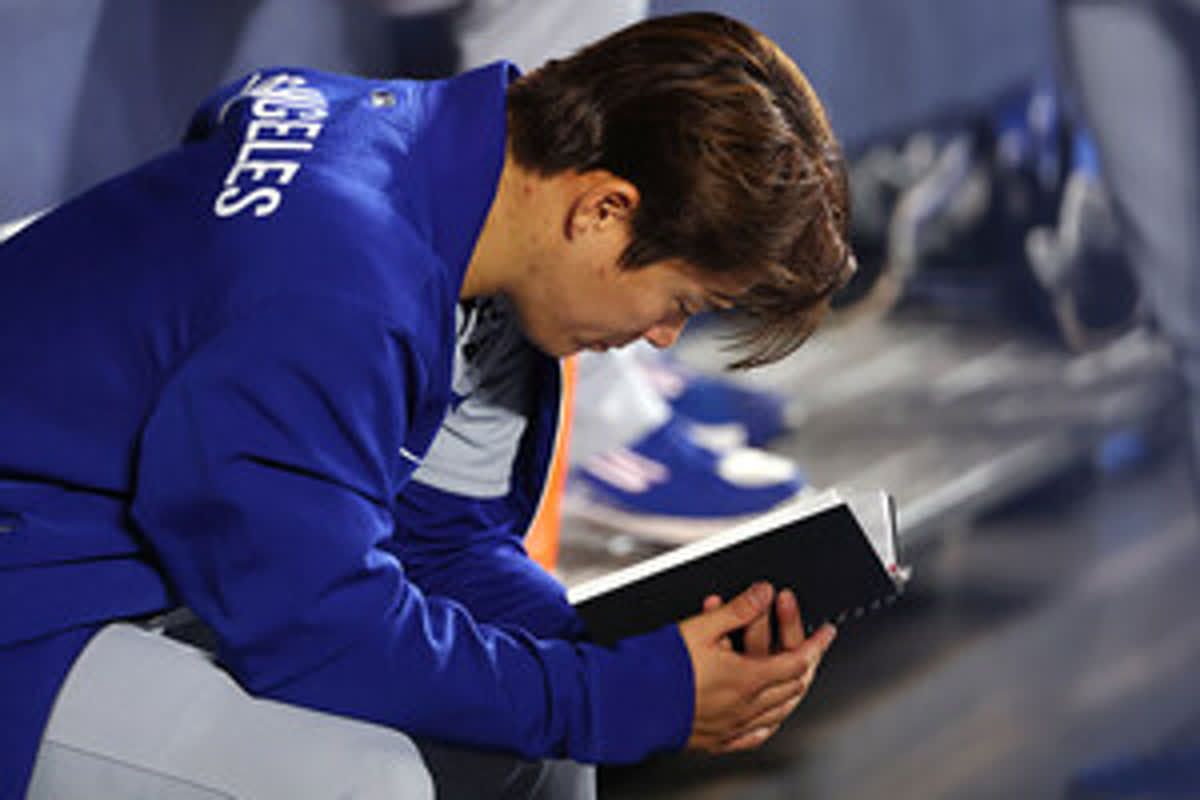
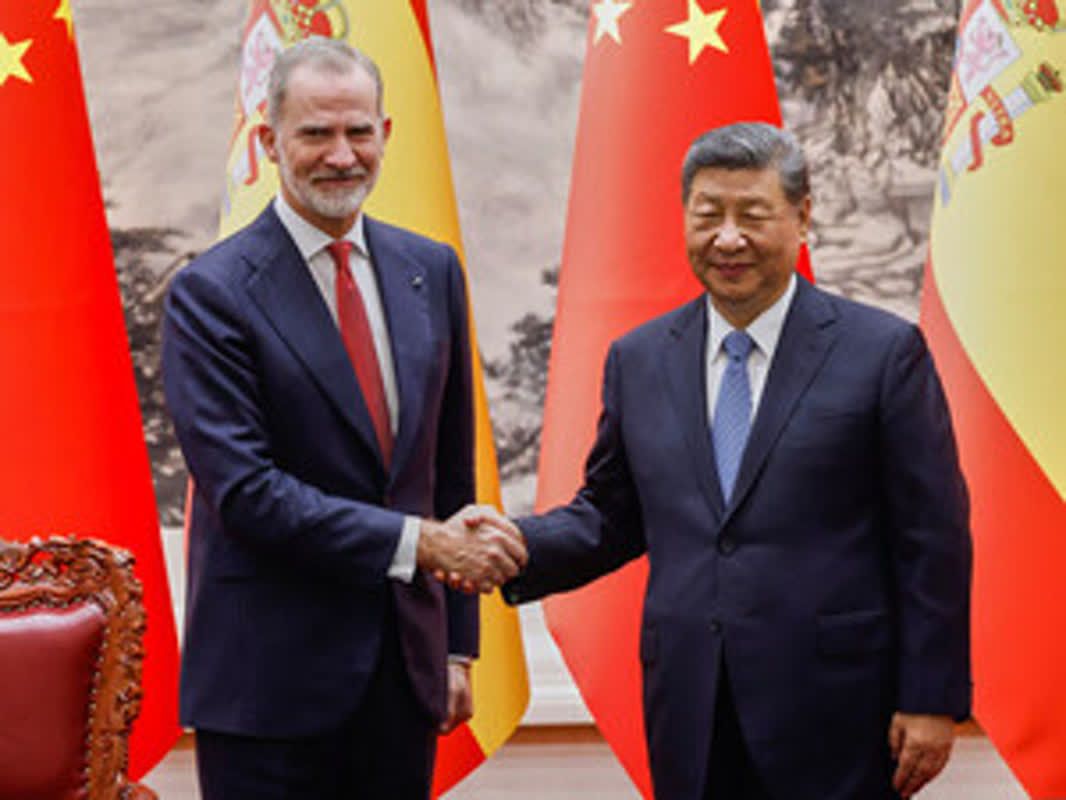





コメント0