
東京の公園で、中国人住民らが食用を目的にセミの幼虫を大量に捕獲しているとの報道が波紋を呼んでいる。
22日、『プレジデントオンライン』によれば、都内の複数の公園で夕方から深夜にかけて、中国人がセミの幼虫を袋いっぱいに捕まえる光景が頻繁に確認されているという。
中国では地域によってセミを食べる文化が根付いており、特に山東省(シャントン省)や河南省(ホゥーナン省)などでは、幼虫を使った料理が夏の風物詩とされている。近年は需要が高まり、高級食材として扱われることもある。
一方、東京都の「都立公園条例」や各区市町村の「公園条例」では、公園内の動植物の採取や捕獲を禁止、または制限している。学習目的などで事前に許可を得た場合は例外だが、子どもが数匹を捕まえる程度を超える大量かつ組織的な捕獲行為は、明確な違反にあたる。
中国人居住者が多い江東区(約1万8,000人)の猿江恩賜公園には、中国語で「セミの幼虫を採らないでください」と記された看板が設置されている。
東京都によれば、こうした看板は公園内の約30カ所に設けられており、夜間の巡回などに多くの人員と労力を要しているという。
江東区のほか、新宿区、足立区、江戸川区、板橋区など、中国人居住率の高い自治体でも同様の看板を掲示。中には、数年前に「食用目的でのセミ採取を禁ずる」と明記した文書を掲示した自治体もある。
セミの幼虫は、羽化直前の夜に地中から出て木に登る習性を持つ。中国人の一部はその時間帯を狙い、懐中電灯を手に幼虫を袋に詰めているという。
さらに問題なのは、セミの幼虫の捕獲を注意された中国人の一部が「差別だ」と反発するケースがあることだ。実際、ある民間放送局が夜間の公園を取材した際、中国人の男性が「ここは公園だろう。誰のものでもないのだから採ってもいい。中国人だからといって差別するな」と声を荒らげる場面が放送された。
中国SNSの影響拡大で事態悪化 取り締まり回避の手口も拡散
同メディアは、中国人による違法な採取行為は以前から問題視されてきたが、近年、中国国内でSNSの影響力が拡大したことで、状況がさらに悪化していると分析した。
例えば、SNS「小紅書(シャオホンシュー)」で「セミ取り」を検索すると、「○○公園の西側××エリアは採りやすい」、「見回りを避けるなら○○時以降が良い」といった具体的な場所や時間を示す書き込みが平然と投稿され、採取場所や時間帯に関する情報が細かく拡散している。
さらに深刻なのは、単なる場所情報にとどまらず、「こうすれば見つからない」、「この方法なら逃げ切れる」といった取り締まり回避の手口が共有されている点だ。
一部の投稿では、「看板が日本語だから読めないと弁解すればいい」、「日本人は『すみません』と言えば許してくれる」、「一度謝って後でまた来れば問題ない」など、取り締まりを逃れるための「実践的な指針」として機能していると指摘されている。
同メディアは、「中国人が日本社会の『性善説』を悪用している」と指摘。「本来、規則は守るものであり、注意されれば改め、真摯に反省すれば理解される――。そうした前提が今、踏みにじられている」と論評した。
7月、韓国・ソウルでも「中国人がセミの幼虫を大量採取」との通報
こうした事例は日本に限ったことではない。
今年7月には、ソウルでも中国人が食用目的でセミの幼虫を大量に捕獲しているとの苦情が市民から寄せられた。
ソウル市の公式サイト「応答所」には、「中国人が大きな容器を持って集団で繰り返し幼虫を採っている。警察に通報したが、処罰の根拠がなく釈放された」との投稿が掲載されている。
ソウル市当局は「汝矣島(ヨイド)の生態公園で中国人による無断採取が続いている。通報があれば職員を現場に派遣し、採取された幼虫は放してもらっている」と説明。釜山の生態公園でも同様の報道があり、波紋が広がっている。







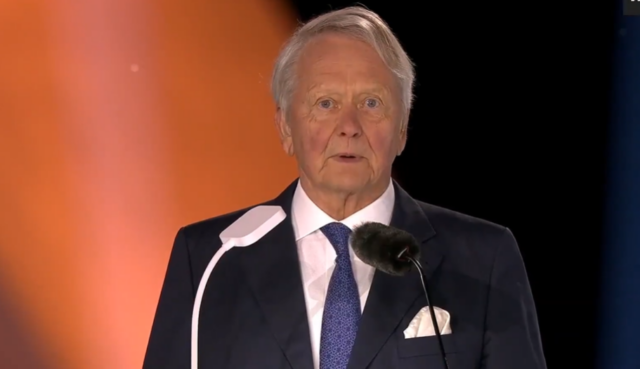













コメント0