溶融岩石と水素が反応する際、放出された酸素と水素が結合し水が生成
従来の「スノーライン形成説」を覆す

水は、惑星に生命が存在できるかどうかを判断する上で最も重要な条件の一つである。これまで、太陽のような恒星からある程度離れた地球型惑星で水が生成されやすいと考えられてきた。
しかし、アメリカ・アリゾナ州立大学のハリソン・ホン研究員らのチームは「岩石と水素の反応だけで水が生じる」という研究結果を発表し、この定説を覆した。論文は先月29日(現地時間)、英科学誌『ネイチャー』に掲載された。
2009年に打ち上げられた米航空宇宙局(NASA)の「ケプラー宇宙望遠鏡」は、地球よりやや大きく海王星よりやや小さい「サブ・ネプチューン級」と呼ばれる系外惑星が宇宙に広く存在することを発見した。これらの系外惑星は、水素が豊富な「乾燥型惑星」と、地球のように水に覆われた「湿潤型惑星」に分類される。
天文学者の間では、湿潤型惑星は「スノーライン」と呼ばれる、氷が安定して存在できる境界線の外側で形成された後、恒星の近くへと移動してきたものと考えられてきた。スノーラインの外側で形成された惑星であれば、氷が溶けずに残り、水の供給源になり得るとされていたためである。
だが、ホン研究員らはこの通説に疑問を呈した。惑星がスノーライン外側から移動したのではなく、もともと恒星の近くで誕生した可能性を探ったのである。
研究チームは、約40万気圧・3,000から4,000ケルビンという高温高圧環境を人工的に再現し、その中でケイ酸塩や鉄などを含む溶融岩石と水素を反応させた。これは、形成初期の惑星が高温・高圧下で水素に包まれていた状態を再現したものである。
その結果、水素がケイ酸塩を還元して鉄・ケイ素合金や水素化物が生成されると同時に、放出された酸素が水素と結合し水が生成されることが確認された。生成された水の量は最大で質量比20%に達し、惑星全体の質量のうち約5分の1が水になる可能性が示された。これは、従来の低圧環境での実験より2,000倍から3,000倍も高い効率で水が生じた計算となる。
実験結果を基に研究チームが計算を行った結果、地球の5倍の質量を持ち、水素が大気の5%を占める惑星では、内部で最大18%の水が生成され得ることが分かった。
研究チームは「惑星内部の対流が活発なほど、水は均一に拡散し大気層まで到達する」と説明した。さらに「長い時間が経つと水素大気が失われ、残った水が凝縮して『湿潤な超地球型惑星(ウェット・スーパーアース)』へと進化する可能性がある」とした。
また「岩石と水素の反応による水の生成は、惑星内部の核-マントル境界のような高温高圧環境で起こる可能性が高い」とし「恒星の近くを公転する高温惑星であっても、氷がなくても内部反応によって水に富んだ惑星に進化し得ることを示している」と述べた。
研究チームは、今回再現した水生成反応は地球より大きな質量を持つ系外惑星内部で数十億年単位で進行している可能性があると推測した。反応の速度は利用できる水素の量や核・マントル境界の温度に左右されるという。
今回の研究成果は、水素が豊富な惑星は時間の経過とともに自ら水を生成できることを示すものであり、従来の「湿潤惑星はスノーラインの外側で形成される」という理論を覆す重要な発見だとして注目を集めている。












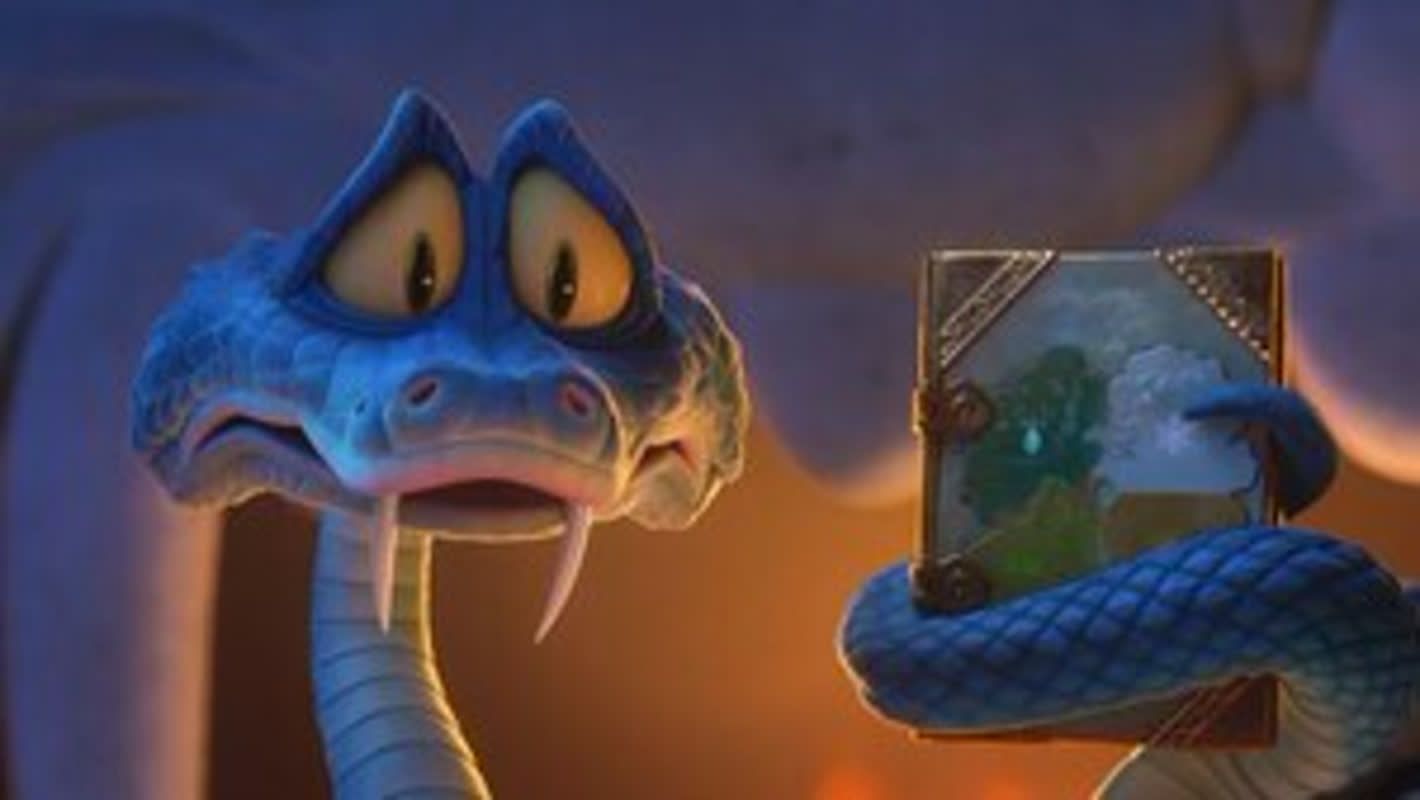









コメント0