
教師たちはいわゆる「モンスターペアレント」と呼ばれる一部の保護者の過度な要求により、極度の圧力を受けている。入学式に桜が十分に咲いていないという理由から、給食メニューが気に入らないという些細な問題まで抗議が続き、教師たちのストレスが深刻化している。
16日(現地時間)『サウスチャイナ・モーニング・ポスト』は、日本各地の学校で教師に無理な要求をする保護者が増加しているため、東京の教育当局が最近、教員保護と不当な苦情制限のための公式ガイドラインの策定に着手したと伝えた。
保護者の過度な干渉問題が社会的な論争になったのは2007年である。当時、教育専門家の向山洋一が昼夜を問わず教師に非現実的な要求をする親たちを「モンスターペアレント」と初めて表現したことがきっかけとなった。
メディアはその後、保護者の苦情の仕方がさらに執拗で巧妙に変化したと分析した。最近の日本の教師たちは、過去よりも保護者の権利主張の強度がはるかに激しくなったと口を揃える。
現場で受け付けられる抗議は種類も多様である。入学式当日に桜がまだ咲いていないと問題視したり、給食がまずいという理由で学校に責任を問うこともあれば、子供が虫に刺されたという理由で補償を要求するケースもあった。フジテレビは、子供が軽い怪我をした事件の後、保護者が治療費だけでなく夕食代まで請求した事例を報じたこともある。
このような苦情の爆発は教育者のメンタルヘルスにも悪影響を及ぼしている。文部科学省が公開した公立学校教職員の勤務実態資料によれば、2021年に精神疾患で長期病欠を取った教職員数は5,897人で、前年度(5,203人)より694人増加し、過去最高を記録した。
専門家たちはこの現象の背景に人口減少と社会構造の変化を指摘している。中央大学の辻泉文化社会学教授は「少子化の影響で親たちが子供の成果と安全にすべての関心を集中させている」と述べ、「過去のように大家族や地域共同体が助言を提供していた構造が消え、学校に不満が向かうケースが増えている」と説明した。




















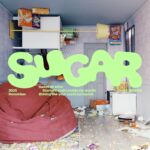
コメント0