
米を巡る政治的対立が深刻化している。政府は8月、「米増産」を宣言し、数十年間維持してきた生産調整中心の米政策を事実上、覆した。これにより日本の農政は重大な転換点を迎えている。これまでの米政策は、価格の安定を図るために生産を抑制する方向で進められてきた。今回の増産宣言は、その限界を認めるとともに、自民党内の農林族による従来の政策路線への否定的なシグナルと受け止められている。農林族議員の間では強い不満が噴出している。
5月、小泉進次郎農林水産相は、就任直後の米価格急騰に対応するため、政府備蓄米を迅速に放出した。しかし、党との十分な協議なしに随意契約方式を採用したため、農林族の反発を招いた。当時、小泉農相は「すべての案件を党に逐一確認していては、迅速かつ大胆な判断はできない」と反論した。
この見解の相違は、米増産政策においても覆い隠されていない。農林族議員は「拙速な増産は価格暴落を招き、農家の収益を圧迫する」と慎重論を唱える一方で、小泉農相は「米は誰もが躊躇なく買えるべきだ」と増産の必要性を主張している。結局、政府と党は「増産」ではなく「需要に応じた増産」という表現に落ち着いたが、対立の溝は依然として深い。
こうした中、自民党は8月26日に農林族議員会議を開催し、米増産と農業構造転換を議論する新組織「農業構造転換推進委員会」の設置を決定した。委員長には、5月に「米を買ったことがない」との発言が問題となり辞任した江藤拓
前農相が任命された。代表的な農林族議員でありながら、わずか3カ月前に退任した人物が再び象徴的な地位に就いたことで論議を呼んでいる。政府は米増産に向け、従来の水田政策を2027年から全面的に見直す方針を示した。これに伴い、来年度予算を今年度比17%増の2兆6,588億円に設定した。そのうち、農地の大区画化や基盤整備を進める農業・農村整備事業には前年比18%増の3,941億円を計上し、農地を集約して耕作希望者に貸し出す「農地銀行」事業には前年の3.7倍となる161億円を配分した。
また、生産者の収入減少時に一定割合を補填する「収入保険制度」関連予算も16%増の466億円を計上し、増産による米価下落が農家経営に与える影響を最小限に抑える方針だ。
結局、米増産政策は「農家と消費者間の価格バランス」という根本的な課題を浮き彫りにする結果となった。増産が本格化すれば消費者負担は軽減されるが、農家経営の安定性が不透明になる問題が生じるためである。現地では、自民党農林族が予算案審議を武器に政府を圧迫し、政府は消費者中心の論理を掲げて対抗する現在の構図が、農家や市場全体の不確実性を高めているとの指摘が出ている。






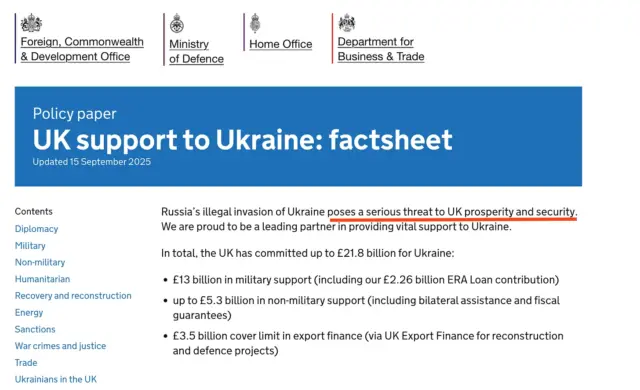





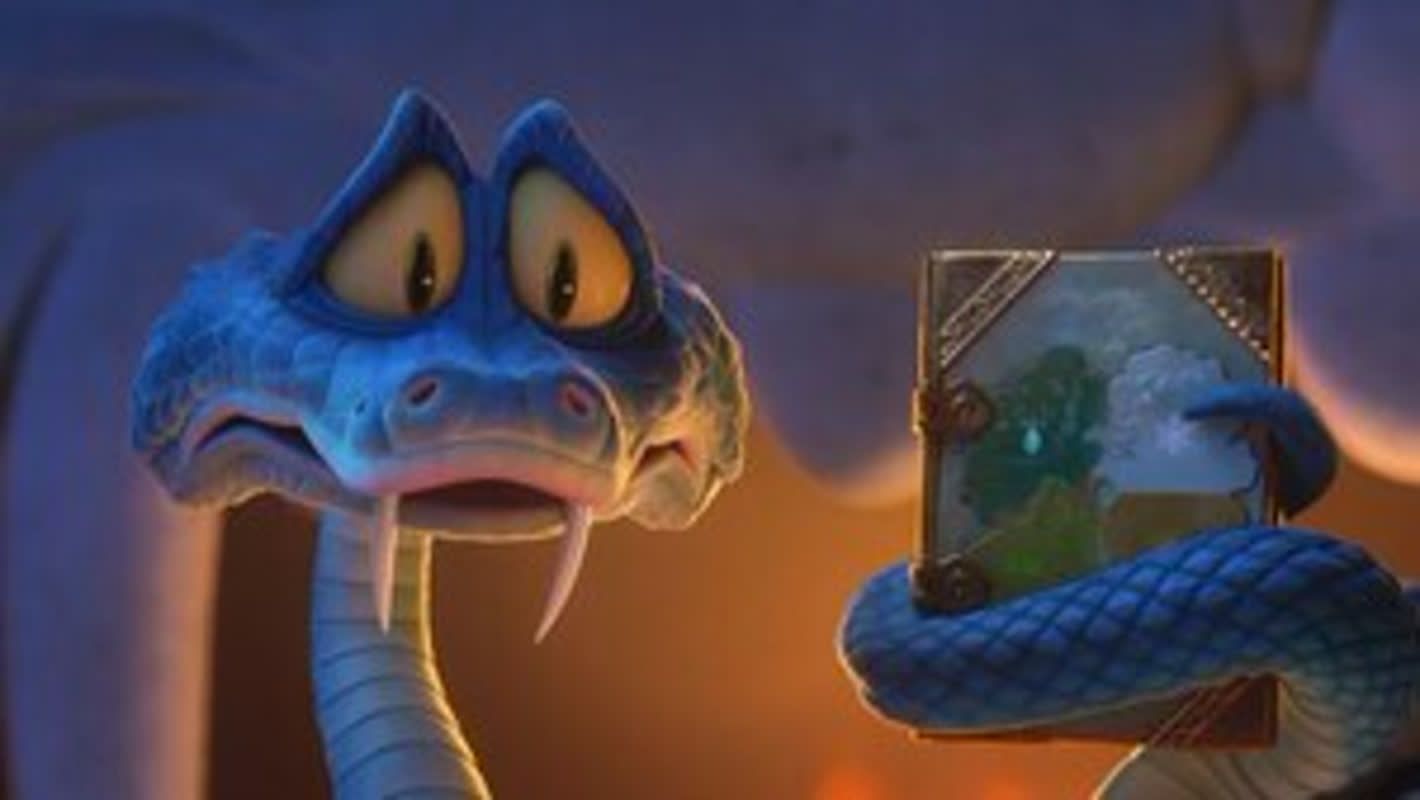







コメント0