欧州主要国が財政赤字と国家債務の二重苦に喘いでいるという。フランスは最近、国際信用格付け会社フィッチから国債格付けを引き下げられ、英国では国家債務が2兆ポンド(約400兆2,004億8,000万円)を突破した。かつて「財政の優等生」と呼ばれたドイツさえ、景気後退や失業率上昇、社会保障費の膨張に直面し、もはや緊縮路線を維持するのは難しい状況とされている。
国際金融市場からは「欧州はもはや財政規律の模範ではない」との批判が相次いでいる。実際、欧州連合(EU)の経済見通し報告書には、防衛費拡大と社会保障負担の増大が国債利回り上昇や投資停滞につながるとの警告が盛り込まれた。新型コロナ対応で膨らんだ歳出に加え、高齢化による年金・医療負担、さらにはウクライナ戦争に伴うエネルギー・安全保障危機が重なり、各国の債務は雪だるま式に膨張している。

フランス、利払いだけで年約11兆円の支出
ドイツ経済は不況の泥沼から抜け出せずにいるという。2023年はマイナス0.9%、昨年もマイナス0.5%と2年連続のマイナス成長に陥っている。米国の高関税措置はすでにドイツ経済に重い負担をかけており、欧米間の貿易協定が停滞する中、ドイツ経済の低迷は2025年第3四半期以降も容易に改善しない可能性が高いとされる。
現在、米国は欧州産品の大半に15%の関税を課し、自動車への27.5%の高関税が再び15%に引き下げられるかは依然不透明だという。ドイツ輸出の約1割が米国向けであることを踏まえれば、関税負担は成長率を大きく圧迫している。
今年第1四半期にはGDPが0.3%の小幅プラスとなったものの、第2四半期はマイナス0.3%に転落した。当初予測(マイナス0.1%)を下回る結果となった。景気回復の足取りが鈍い一方、政府支出は膨張を続けている。防衛やインフラ投資、電気料金引き下げなどの企業支援に資金を投じたが、その大半は年金・医療・福祉補填に吸収され、景気刺激効果は限定的となっている。まさに「底の抜けた桶に水を注ぐ」ように、増え続ける高齢化関連コストに財政が消費されている。
ドナルド・トランプ米大統領による防衛費増額圧力や地政学的リスクを受け、ドイツ政府は債務制限政策を修正したが、その効果は依然として不透明とされる。安全保障強化には時間を要し、景気押し上げ効果もまだ見えていない。
英国の財政も相次ぐグローバルショックで限界に直面している。2024年末の財政赤字はGDP比5.7%と、先進国平均より約4ポイント高い水準で、欧州28カ国で3番目、世界36カ国で5番目の高さだ。政府債務残高はGDP比94%に達し、日本・ギリシャ・イタリア・フランス・米国に次ぐ規模となった。
2010年以降に策定された財政運営枠組み9回のうち、8回に「GDP比国家債務縮小」目標が盛り込まれたが、過去15年間で英国家債務はGDP比24ポイント、過去20年間では実に60ポイントも上昇した。コロナ対応やエネルギー危機下での財政出動が膨れ上がり、企業・家計への支援策も国際的に見て手厚かった。増税や歳出削減の計画は度々頓挫し、結局イギリスは将来の衝撃に備える余力を失ったとみられている。イギリス財政の最大の負担は年金であり、現在の国民年金支出はGDPの5%に当たる1,380億ポンド(約27兆6,250億2,200万円)で、2070年代初頭には7.7%に膨らむ見通しだという。
フランスは欧州で最も深刻な財政危機に直面している国と見なされている。新型コロナや高齢化による年金負担、社会保障支出の拡大、エネルギー転換コスト、ウクライナ戦争によるエネルギー危機が重なり、財政赤字は制御不能に近い状況となっている。
財政危機克服のために打ち出した緊縮策はかえって政治的不安を増幅させ、この1年で首相が4度も交代する異例の事態を引き起こした。特にフランソワ・バイルー首相は祝日廃止や大幅歳出削減を柱とする緊縮策を打ち出したが、「富裕層増税なき庶民犠牲案」と批判され、高齢層・弱者層の反発に直面し、議会の不信任決議を受けて退陣した。結局、9月12日、フィッチはフランス国債の格付けを「AA-」から「A+」へと引き下げた。
フランスの債務残高はEU内でギリシャ、イタリアに次いで3番目に高く、財政赤字規模もEU加盟27カ国で最大とされる。利払いだけで毎年670億ユーロ(約11兆7,065億6,900万円)が費やされている。脱出の道は大規模な福祉改革や支出削減、または増税のみだが、すでに税負担率が高いフランスでの増税は強い政治的反発が避けられず、左右ポピュリズムが台頭する現在の政治環境では、超党派合意による債務削減も期待できない。
現状、フランス内部の問題のように見えるが、ユーロ圏第2位の経済大国であり、欧州の核心国であるフランスが揺らげば、欧州全体へ危機が波及する可能性が懸念されている。
高齢化、移民、安全保障…「財政危機」欧州の三重苦
欧州共通の構造的要因は高齢化とされる。ブリューゲル研究所は「国ごとに進行速度の違いはあるが、高齢化こそが財政圧迫の核心要因」と指摘する。年金・医療・介護費は年々拡大し、財政健全化を直撃する。
さらに移民問題も重なっている。労働人口減少を補うには移民流入が不可欠だが、短期的には福祉需要と社会統合コストを増加させる。イギリス予算責任局は「移民は税収増効果がある一方、公的サービス支出も刺激する」として、移民は財政の「解決策」であると同時に「新たな負担要因」だと分析する。
安全保障環境の悪化も無視できない。9月10日にはロシア無人機がポーランド領空を侵犯、20日にはロシア戦闘機がエストニア領空に無断侵入した。トランプ大統領の防衛費増額要求とは別に、欧州はもはや安保支出を先送りできない局面にある。しかし、高齢化や社会保障負担、深刻な財政赤字、景気低迷の中で、防衛費拡大に充てる余力は乏しいとみられる。
焦点は世論の動向だ。フランスでは緊縮策への反発から首相が次々と不信任に追い込まれ、英国では大企業・富裕層への増税要求が高まっている。ドイツでは難民受け入れを巡り社会の分断が深刻化しており、専門家は「防衛費を増やせば社会支出を削らざるを得ず、逆に社会支出を維持すれば防衛費拡充は難しい。結局は政治的選択だが、国民の同意を得るのは容易ではない」と指摘する。
欧州の危機は単なる財政赤字ではなく、政治・社会的合意の欠如から生じているとの見方が広がっている。財政健全性の回復には増税と支出調整を両立させる必要があるが、いずれも国民を説得するのは困難だとみられる。強力な政治リーダーシップと社会的合意がなければ、欧州は「債務の泥沼」から抜け出せず、金融市場の不安は長期化し、国際社会での影響力も一層低下しかねないと予測される。


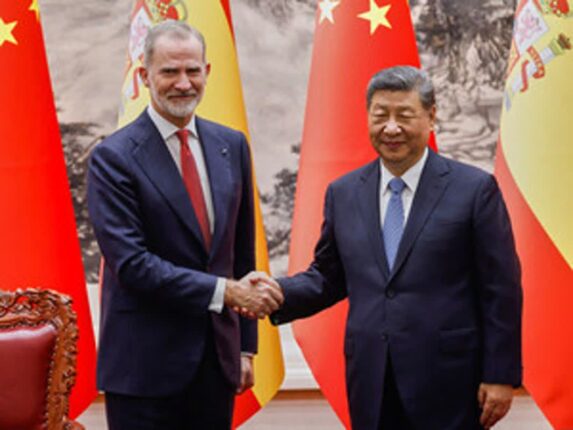







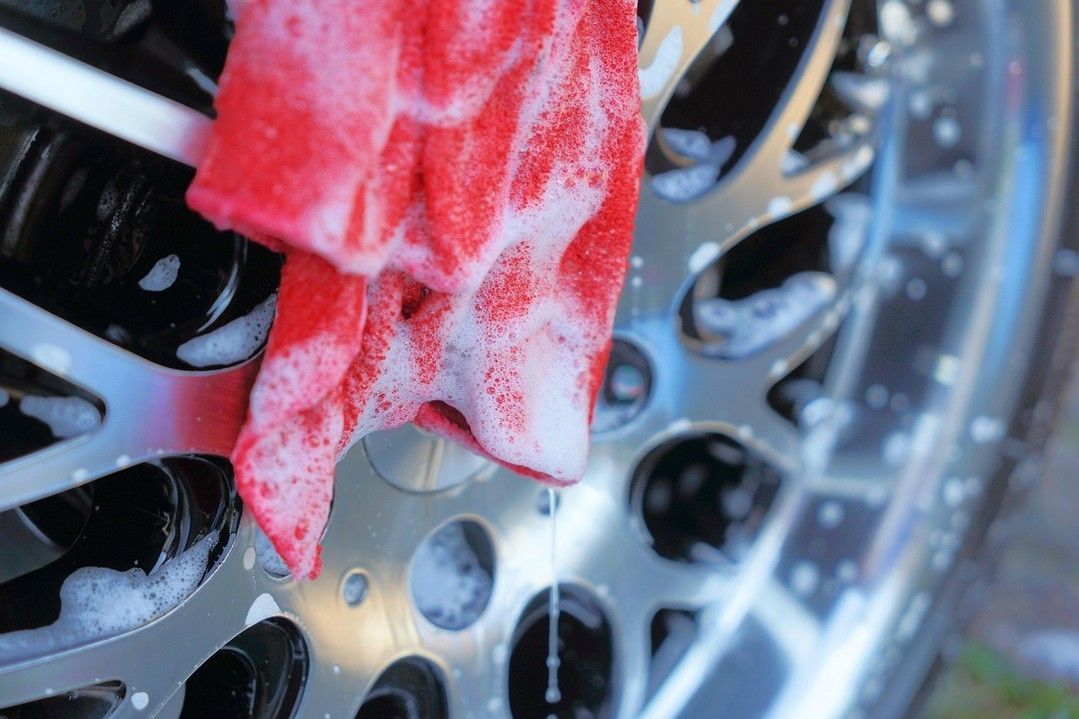


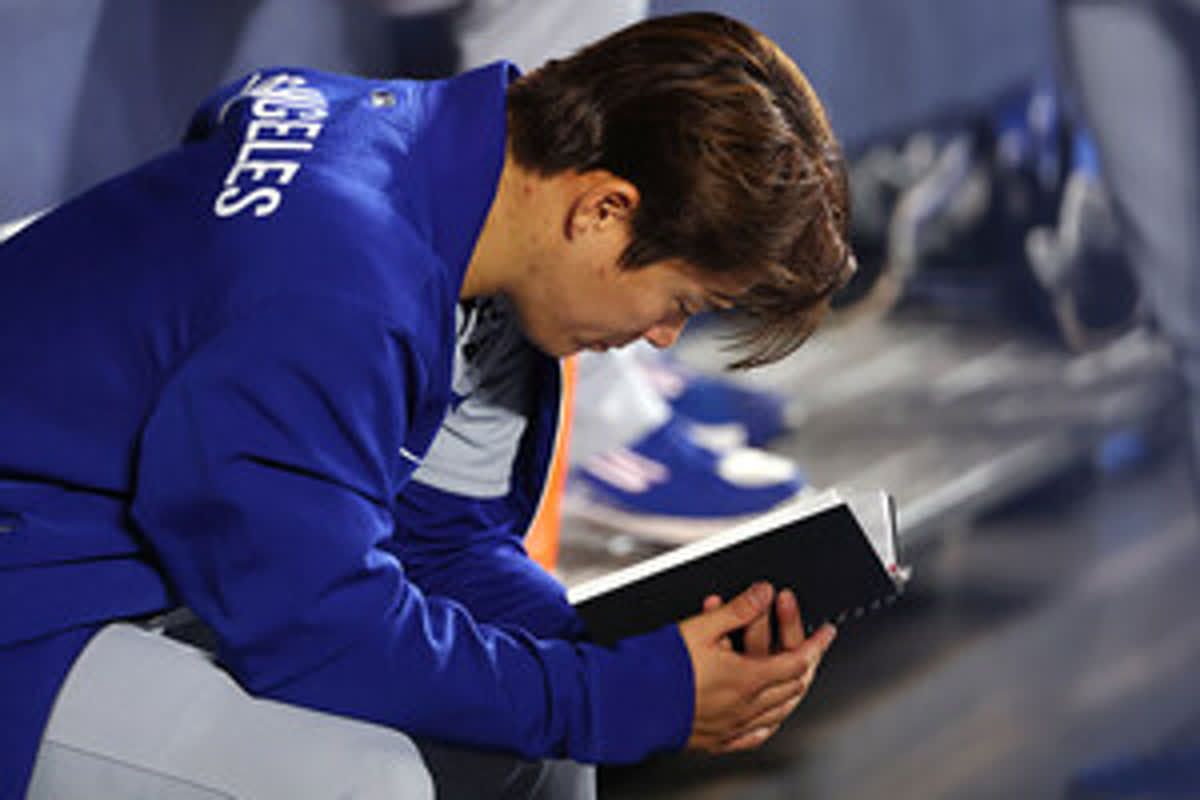
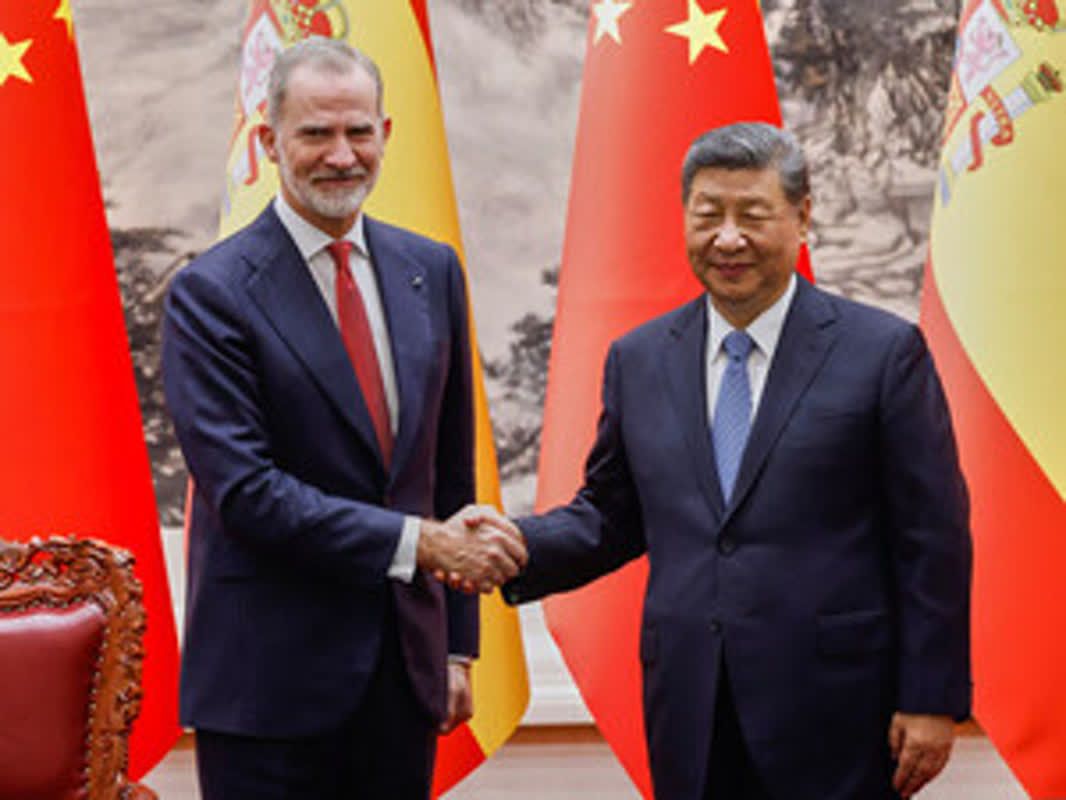







コメント0