
私たちはなぜあくびをするのだろうか。
人間をはじめ、脊椎動物の多くはあくび、もしくはそれに似た行動をする。群れで生活するサバンナモンキーもあくびをし、単独で過ごすことの多いオランウータンもあくびをする。オウムやペンギン、ワニも同様である。
しかし、動物がなぜあくびをするのか、その明確な理由はいまだ科学的に解明されていない。近年に至るまで研究者の間でも見解は分かれている。
一般的には「酸素が不足するとあくびが出る」と考えられているが、学界ではすでに1980年代に複数の研究を通じて、酸素濃度とあくびの発生には関連がないことが証明された。
例えば、被験者が吸い込む空気中の酸素や二酸化炭素の濃度を人為的に変化させた実験では、ガス濃度の変化が呼吸など他の生理反応には影響を与えたものの、あくびの回数には変化が見られなかった。また、肺疾患や呼吸器疾患のある人が、特別にあくびの回数が多い・少ないという傾向も確認されていない。

英紙「ガーディアン」は28日、あくびに関する新たな仮説を紹介した。米ジョンズ・ホプキンス大学の行動生物学教授アンドリュー・ギャラップ氏の研究によると「人間は脳の温度を下げるためにあくびをする」という。あくびが脳の温度調節と血流の促進に関与しているというのだ。

ギャラップ教授の研究チームは、120人の歩行者を対象に、冬季と夏季に屋外を歩かせ、あくびの回数と周囲の気温との関係を調べた。その結果、比較的温暖な条件ではあくびの頻度が高く、逆に気温が極端に高い、または低い場合にはあくびの回数が減少する傾向が見られた。
研究チームは、この現象が「あくびが脳の温度を調節する役割を担っているため」だと説明する。
脳の温度は通常3つの要因によって決まる。脳へ流入する血流量、血液自体の温度、神経細胞の活動による代謝熱などだ。あくびはこのうち前の2つを変化させることができる。あくびをすると、口や鼻、舌の表面を空気が通過し、熱が奪われるというのだ。
他の研究でも、周囲の気温とあくびの関係が確認されている。気温がやや高いとあくびが増えるが、気温がさらに上昇すると、吸い込む空気が温かくなり、かえって脳の温度が下がりにくくなるため、あくびの回数は減るという。逆に寒い環境では、すでに脳の温度が十分に低いため、さらに冷やす必要がなくなり、あくびが減るとされている。

ただし、他の説も存在する。医学研究者オリビエ・ワルシンスキー氏は「あくびは脳の覚醒状態を切り替えるために起こる」とする仮説を唱えている。つまり、あくびは脳が異なる状態へ移行する際のスイッチのような役割を果たすというのだ。例えば、眠りから覚めるときにあくびをするのは、脳が集中状態へと切り替わるためだと説明している。












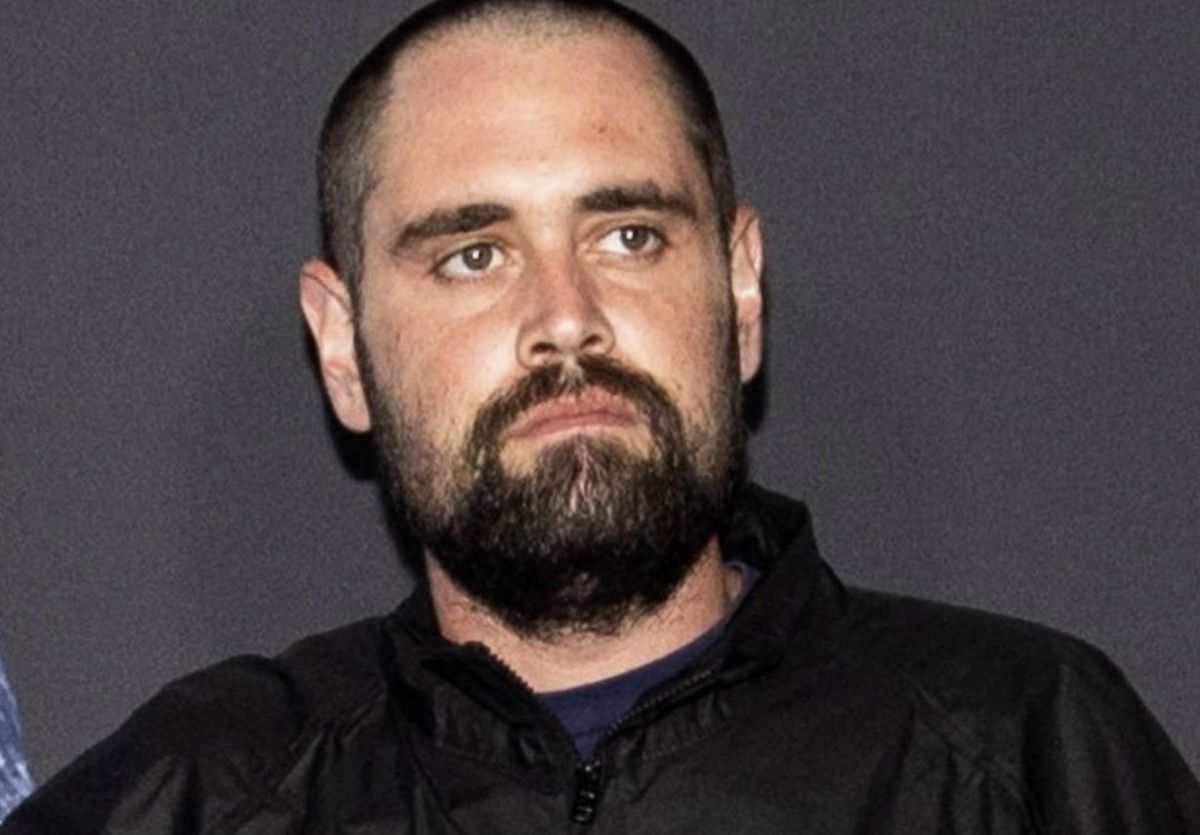









コメント0