
日本経済新聞によると、中国の電気自動車大手BYDとスズキが29日、軽の電気自動車を初めて公開し、日本のEV市場の新たな転換点を予感させた。
日本独自の規格である軽自動車は、新車販売の40%を占める中核市場で、航続距離に制約のあるEVと高い親和性を示す。
30日に開幕した「ジャパンモビリティショー 2025」で、BYDアジア太平洋地域販売責任者のリュウ・ガクリョウ(劉学亮)氏は「日本の消費者のために軽専用の電気自動車を開発した」と自信を示した。
BYDは軽自動車EV「ラッコ」を2026年夏の発売を目指して初公開し、広い荷物スペースの確保と日本の充電規格への対応を完了したと発表した。
軽自動車は車幅1.48m以下、長さ3.4m以下、高さ2m以下に制限され、普通乗用車に比べて税負担が大幅に軽減される。
軽EVは軽自動車と同じ税制優遇が適用され、購入翌年の軽自動車税減免などの固有の利点を持つ。
BYDは中国で軽自動車規格対応プラットフォームを独自に開発し、100台以上の試作車の走行テストを完了した。
価格競争力がEV普及の鍵として浮上している。総務省の小売物価統計によれば、2024年の軽乗用車の平均小売価格は163万円だった。
BYD日本法人の東福寺厚樹社長は「軽自動車購入者の予算感覚を参考にする」とし、軽自動車の一般価格帯を意識した価格設定を示唆した。国の補助金を含めると200万円未満の価格実現の可能性が高い。
スズキも2026年量産目標の軽EVコンセプト「Vision e-Sky」を公開した。鈴木俊宏社長は「他社を見ながら検討していく」とし、価格競争に慎重なアプローチを示した。
日本のEV普及率の遅れが軽EV集中の背景だ。日本の新車販売におけるEV比率は1-2%台で先進国最下位の水準であり、海外市場の20%とその差が顕著だ。
充電インフラ整備の遅れとEVが高価であることが主な要因として指摘されている。
しかし、軽EVは好調だ。2024年国内EV販売の中で、日産自動車「サクラ」が38%を占め、三菱自動車「eKクロス EV」と合わせて40%以上を記録した。
航続距離に制約のあるEVが近距離走行中心の軽自動車と高い相性を示し、普及を牽引する役割を担っている。
トヨタ自動車も「カローラ」のコンセプトカーを披露し、初めてEV参入への準備の意向を表明した。
「良品廉価」が開発コンセプトのカローラは、全世界で5,000万台以上販売された代表車種で、安価なEVの登場時には相当な需要の牽引が予想される。
中国は過剰競争に直面している。中国の乗用車業界団体幹部のチェ・トンス(崔東樹)氏の統計によれば、中国の新エネルギー車乗用車の平均価格は2025年1-9月で16万人民元(約343万3,500円)で、2023年のピークである18万4000元(約394万8,500円)に比べて10%下落した。
日本経済新聞によれば、日本でも価格競争の兆しが見られている。BYDは9月に期間限定の大幅割引を実施し、トヨタ自動車は10月に量産EV「bZ4X」の価格を従来より70万円引き下げた。
日本のメーカーは今後の価格競争に備えたコスト競争力強化が喫緊の課題として浮上した。




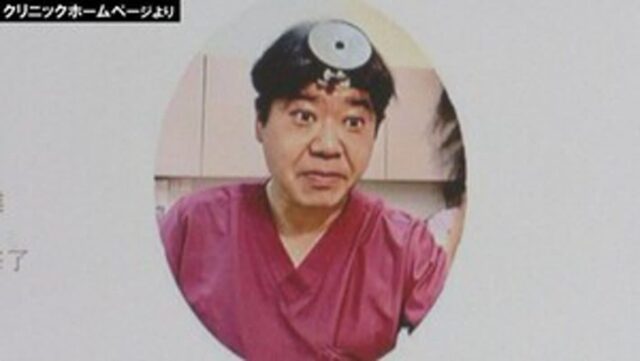

















コメント0